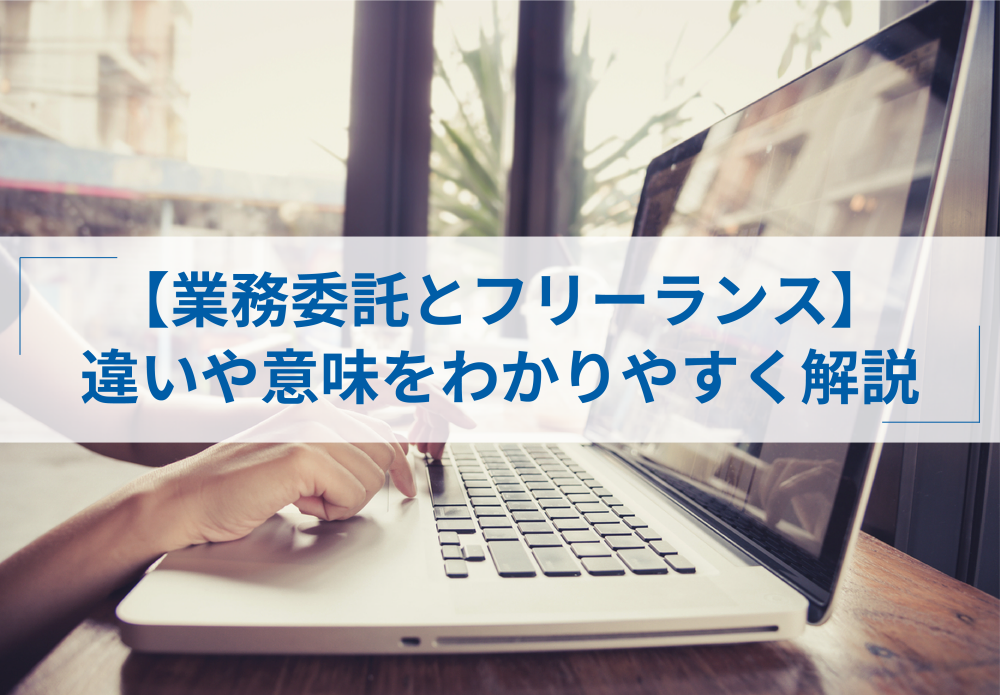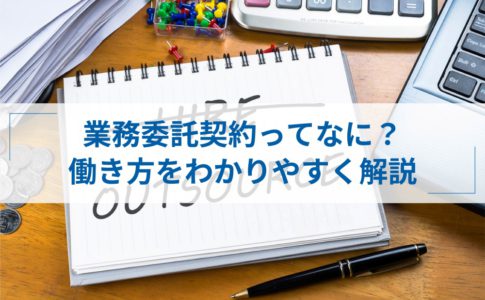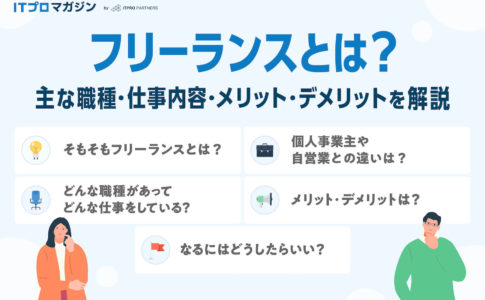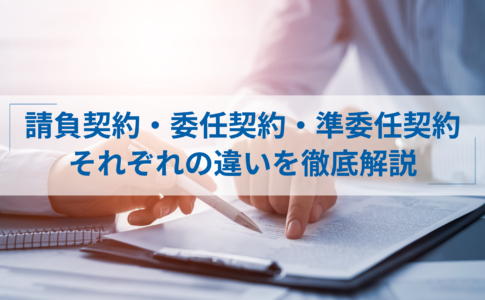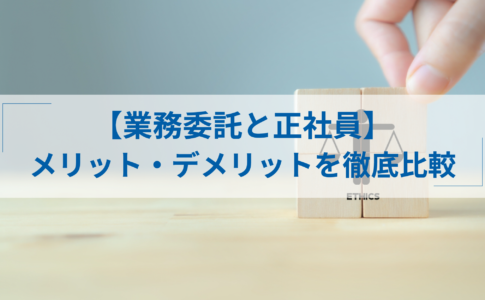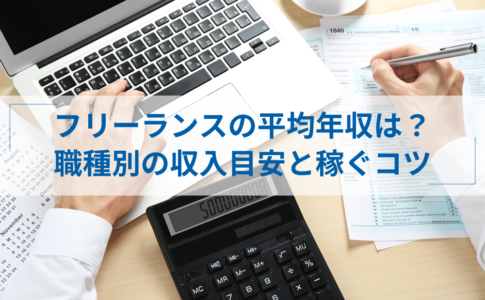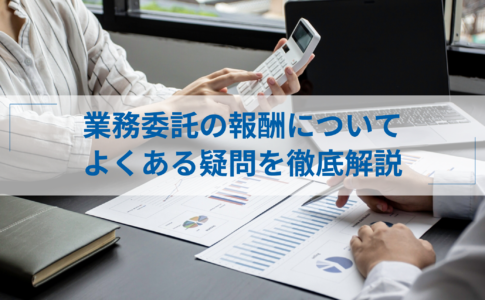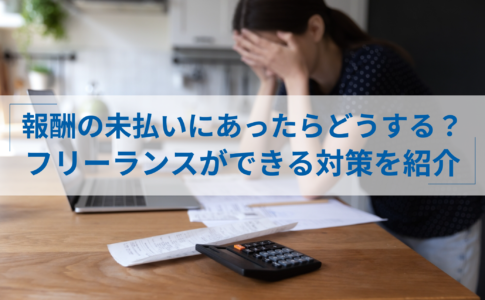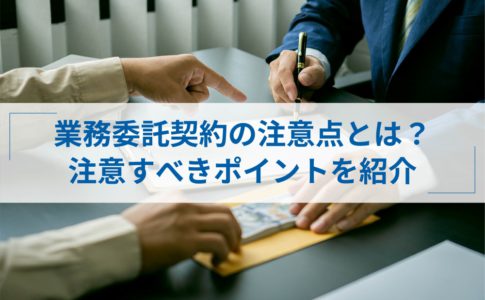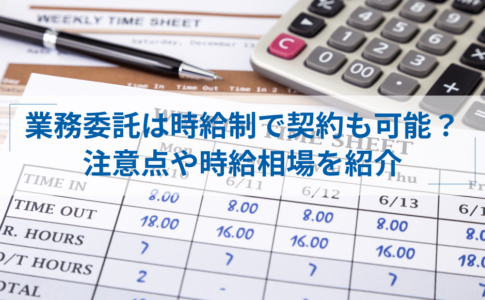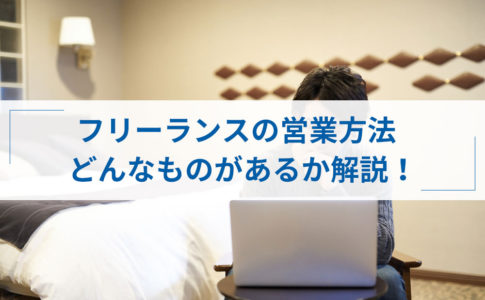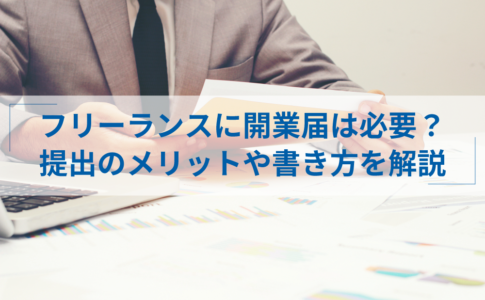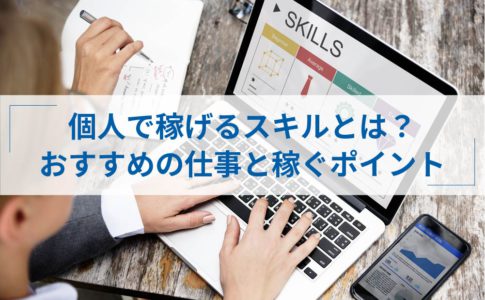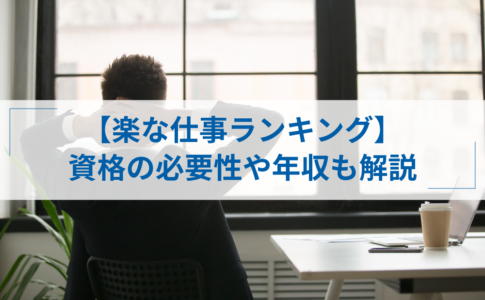こんにちは、ITプロマガジンです。
「業務委託」と「フリーランス」は、副業や独立について調べているとよく目にする言葉ですが、両者の違いについて、理解できていないという人は多いかと思います。
結論からお伝えすると「業務委託」は契約形態を指す言葉に対して、「フリーランス」は働き方を指す言葉という点で違いがあります。また、業務委託契約にはいくつかの契約形態の種類があるため、契約前に事前に理解しておくことが大切です。
そこでこの記事では、フリーランスと業務委託の違いから業務委託契約の種類、フリーランスが業務委託契約を結んで働く際の注意点、メリット・デメリットまで詳しく解説します。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
業務委託とフリーランスの違い

「業務委託」と「フリーランス」は同じように使われがちですが、言葉の定義としては異なります。業務委託は、契約形態を指す言葉です。一方で、フリーランスは働き方を指す言葉になります。
それぞれ具体的にはどういう意味なのか、以下で解説していきましょう。
業務委託とは「契約の種類」のこと
業務委託とは、仕事を発注する委託者と、請け負う受託者の間で取り交わされる契約です。
企業がフリーランスなどの個人に業務を依頼する場合は、基本的にこの業務委託契約を結びます。なお業務委託は企業と企業との間でも行われますので、必ずしもフリーランスだけが当事者となるわけではありません。
ちなみに業務委託契約という法律用語はなく、民法に規定された「請負契約」と「委任・準委任契約」を総称して一般的に業務委託契約と呼ばれています。
フリーランスとは「働き方」のこと
フリーランスとは、企業や団体などに所属せず自分の裁量で働くという仕事のスタイルです。以下のような職種に多くみられます。
- エンジニア
- プログラマー
- デザイナー
- カメラマン
- ライター・エディター
フリーランスは特定の企業や団体に所属せず、多くの場合、業務委託契約で仕事を請け負います。働く時間や場所などの制約がなく自由度が高い一方、会社員のような固定的な給与はなく、請けた仕事量の増減が収入にダイレクトに反映されるのが特徴です。
近年は、多様な人材が活躍できる社会を目指して働き方の多様化が推進されており、柔軟な働き方も可能なフリーランスに注目が集まっています。
常駐型とリモート型
フリーランスという働き方には、主に大きく分けて「常駐型」と「リモート型」があります。
常駐型フリーランスは、クライアントが指定した場所へ出勤して作業をします。「週5日出勤で9時から18時まで」のように勤務時間が決められていることが多く、スケジュールとしては一般的な会社員とほとんど変わりません。
一方でリモート型フリーランスは、出勤せずに自宅やコワーキングスペースなどで作業をします。勤務時間に関しては、ある程度決められていることもあれば、全く決まっておらず納期までに成果物を納めるだけでよいという場合もあり、一概には言えません。
このほか、「全体ミーティングの日のみ出勤で、残りはリモート」のようなハイブリッドな働き方も存在します。
業務委託契約の種類
業務委託で取り交わす契約には、「請負契約」と「委任・準委任契約」という2種類があります。この2つの契約について詳しく解説しましょう。
請負契約
請負契約とは、受託者が依頼された仕事を完成させ、その結果に対して委託者が報酬を支払うことを約束する契約です。
報酬は成果物への対価であり、途中のプロセスや割いた人員・時間は報酬の対象とはなりません。また成果物にミスや欠陥が発見された場合や、契約時に取り決めた内容・品質を満たしていない場合、委託者は成果物の修繕などを要求できます。
民法632条では請負について「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。
「リモート型」のフリーランスでは、この請負契約の形がとられることが多いです。
委任・準委任契約
委任契約とは、法律行為にあたる業務(弁護士や会社役員など)を相手に委託する契約です。また準委任契約とは、法律行為ではない業務(時間給でのシステム開発・デザイン制作など)を委託する契約です。いずれも民法643条で定義されています。
前述の請負契約と委任・準委任契約の大きな違いは、報酬の対象です。
請負契約では成果物が報酬の対象となるのに対し、委任・準委任契約では労務の提供やその成果が対象になります。例えば、弁護士の訴訟委任契約は委任契約ですが、たとえ裁判に勝てなくても弁護士の労務に対する報酬は発生します。
また、請負契約では成果物に対して受託者に担保責任が発生しますが、委任契約・準委任契約では、受託者への担保責任は発生しません。
委任契約・準委任契約は、「常駐型」のフリーランスで採用されるケースが多い契約方法です。ただしフリーランスエンジニアの場合は清算幅ベースで固定単価で働くため、準委任でもリモートで働くケースも多いです。
業務委託と雇用契約の違いは?

フリーランスがクライアントと業務委託契約を結ぶのに対し、会社員や派遣社員などは企業と雇用契約を結びます。
ここでは、業務委託と雇用契約の違いについてもみていきましょう。
使用従属性の有無
業務委託と雇用契約の違いは、使用従属性があるかどうかです。使用従属性とは、労働者と企業の間での「使用する・される」という関係性のことです。雇用契約の場合は使用従属性があるので、労働者に対して業務の指示や勤務場所・勤務時間の指定などが行われます。
一方、業務委託の場合は使用従属性がありません。フリーランスへの指揮命令権もないので、決められた成果物さえ納品すれば、どのように仕事をするかは労働者側が自由に決められます。
業務委託なのに勤務時間や勤務場所を拘束されたり、仕事の依頼や業務指示に対して諾否の自由がなかったりする場合は、使用従属性があると判断されます。偽装請負にあたる可能性があるので注意しましょう。
偽装請負については後章「フリーランスが業務委託で働く際の注意点」にて詳しく解説します。
労働法適用の有無
雇用契約の場合は労働法が適用されますが、業務委託は労働法の適用外です。雇用契約では、以下のように労働者を守るためのルールが適用されます。
- 法定労働時間・・・1日8時間、週40時間以上は労働させてはならない
- 労働保険・・・失業した際の失業保険、業務中の怪我や病気に対する労災保険の給付
- 最低賃金・・・都道府県で定める最低賃金の適用
- 解雇規制・・・正当な理由なく会社側から即時解雇することはできない
一方、業務委託の場合は上記のようなルールは適用されません。フリーランスは自由度が高い分、自己管理や自分で自分を守るための対策が必要です。
業務委託で働くフリーランスのメリット
フリーランスが業務委託で働くことには、次のメリットがあります。
- 自分で仕事を選べる
- 高い報酬が期待できる
- 人間関係のストレスが減る
- 自分のペースで働ける
それぞれのメリットについて、詳しく解説します。
自分で仕事を選べる
業務委託契約は業務単位で契約を結ぶので、得意分野の仕事を選んで契約できます。一方、会社員は対応する業務の幅が広く、人事異動によって仕事内容がガラッと変わることもあります。
基本的に業務委託で仕事をするフリーランスなら、苦手な分野の仕事はそもそも契約しなければよいので、仕事に対するモチベーションも上がるでしょう。
実力次第で高い報酬が期待できる
成果物の納品で報酬がもらえる請負契約なら、高いレベルで仕事をこなせばこなすほど高収入を得ることができます。得意な分野で効率よく仕事を進められれば、それだけ収入が増えます。
会社員の場合は、多くの仕事をこなすほど給与が増えるというケースばかりではないので、業務委託で働くフリーランスならではのメリットです。
人間関係のストレスが減る
フリーランスは「どの仕事を請けるか」「どのような方法で仕事をこなすか」といったことを自分で決められるため、人間関係のストレスも減らせます。
フリーランスと契約を結ぶクライアントは、「フリーランス側から仕事を断れない状況にする」「業務の遂行方法を細かく指定する」といったことはできません。こういった指揮命令を行うと「雇用している」とみなされ、罰則の対象となるためです。フリーランスは自分に裁量がある分、ストレスから解放されます。
また、常駐先で人間関係のトラブルがあったとしても、案件が完了すれば関係が切れることから、長期にわたって悩まされることもないでしょう。
自分のペースで働ける
業務委託は案件ごとに契約する・しないを選べるので、自分のペースで働けるのもメリットです。「先月は忙しすぎたから、今月は契約数を少しセーブする」など、自分で仕事量を調整できます。
一方、雇用されて働く場合は自分の意思に関係なく繁忙期が訪れるので、自分のペースで働くのは難しいケースも多いでしょう。
業務委託で働くフリーランスのデメリット

フリーランスが業務委託で働く場合、以下のようなデメリットもあるので注意してください。
- 仕事が途切れる可能性がある
- 確定申告・経費処理を自分で行う必要がある
- 労働法が適用されないため自己責任になる
- さまざまな審査で不利になりやすい
それぞれのデメリットについて、詳しくみていきましょう。
仕事が途切れる可能性がある
業務委託は案件ごとの契約なので、1つの案件が終わったタイミングで新しい案件を受注できなければ仕事が途切れてしまいます。仕事がなくなると当然収入も途切れてしまうので、注意しなければなりません。
案件をこなしながら新規案件の営業をする、常に複数の案件を持っておくなど、全く仕事がない時期ができないように工夫が必要です。
フリーランス向けのエージェントを利用するのもおすすめです。「忙しくて自分では営業ができない」という人の代わりにエージェントが適した仕事を探して紹介してくれるため、仕事が途切れるリスクを軽減できます。
弊社ITプロパートナーズでは、IT人材を探している2,000社以上の企業が利用しており、高単価の魅力的な案件を数多く取り揃えています。関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
確定申告・経費処理を自分で行う必要がある
会社員の場合は税金が給与から天引きされますが、フリーランスの場合は自分で確定申告をして税金を支払わなければなりません。これは非常に手間がかかります。正しく確定申告を行わなければ脱税と見なされてしまうこともあります。
また、「源泉徴収の会社員よりも確定申告で多くが戻ってくるフリーランスのほうが得だ」と思われがちですが、実際には自分で所得税・住民税や国民年金、国民健康保険料などを払わなければならず、トータルでは収入が減ってしまうケースも多くあります。
さらにフリーランスになったら開業届を出しておくことも必要です。開業届を出して個人事業主になっておくと、確定申告時に控除額の大きい青色申告が可能になったり、赤字を繰り越せたりするメリットがあります。
労働法が適用されないため自己責任になる
業務委託で働くフリーランスには、労働法が適用されません。仕事を詰め込みすぎて休日がなくなったり、収入が減ったりした場合も、全て自己責任です。働きすぎや低賃金になってしまわないよう、自分自身で管理する必要があります。
一方で雇用されて働く会社員は、労働法によって守られています。例えば労働に従事する際の最低基準を定めた労働基準法では、「労働時間は1日8時間、週40時間まで」「休日は少なくとも週1日、もしくは4週間で4日以上」などのルールがあり、雇用側が好き勝手に働かせることはできません。
労働基準法に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
さまざまな審査で不利になりやすい
フリーランスは、クレジットカードや住宅ローンなど金融系の審査が不利になりやすいとされています。定期的な収入が保証されておらず、会社員に比べて社会的信用が低いとみなされてしまうためです。
また、体調不良などの事情で本人が一時期働けなくなった場合に、会社員には傷病手当などがありますが、フリーランスだと収入が完全に途絶えてしまうのもマイナス要因となっています。
もちろんフリーランスの人でもローンは組めるのですが、審査される基準は会社員よりも厳しくなります。独立後3年以上経過していることを条件としているケースが多いようです。
フリーランスとして業務委託で働く時の基本的な流れ
フリーランスが業務委託で働く時の基本的な流れは、次の通りです。
- 契約内容の交渉・すり合わせ
- 業務委託契約の締結
- 業務開始・成果物の納品
- 検収・報酬の受け取り
それぞれについて詳しく解説します。
1.契約内容の交渉・すり合わせ
フリーランスが業務委託契約で働く際には、事前に契約内容の交渉とすり合わせをします。業務内容や業務の範囲、流れ、納期などについてはお互いに認識の違いが発生しないよう丁寧に確認しておきましょう。
報酬や報酬の支払い時期、経費の支給についても確認しておくことが重要です。言い出しにくいからとよく話し合わないまま契約してしまうと、割の合わない仕事をすることになりかねません。
他にも、契約更新の取り決めや禁止事項についても確認・すり合わせをすることが重要です。業務委託の報酬相場や決め方などについては以下の記事を参考にしてください。
2.業務委託契約書の締結
契約内容の交渉・すり合わせが終わったら、合意した内容を業務委託契約書として残します。
業務委託契約書とは、具体的な業務の内容や報酬の金額などを細かく記載した文書です。契約内容について、後から言った・言わないで揉めるのを防ぐ役割があります。業務委託契約書が作成されたら、内容に間違いはないかよく確認したうえで署名・捺印しましょう。
ただし、クラウドソーシングやエージェント経由で業務委託契約を結ぶ場合は、エンドクライアントとは直接業務委託契約書を交わさないこともあります。この場合は、仲介するエージェントなどを通して契約内容を詳細に確認しておきましょう。
業務委託契約書に記載すべき項目やテンプレートは、以下の記事で詳しく紹介しているので、こちらもご確認ください。
3.業務開始・成果物の納品
業務委託契約が成立したら、業務を開始します。請負契約なら納期までに成果物を制作して納品し、準委任契約なら契約した内容の仕事を遂行します。
業務に取り組むなかで委任契約の内容と違う部分があれば、速やかに先方に問い合わせてください。また、契約違反になるか分からないことがある場合もすぐに問い合わせることが重要です。契約違反を犯すと契約解除になるだけでなく、賠償金の支払いなどが生じることもあるので注意しましょう。
4.検収・報酬の受け取り
成果物の納品・業務の遂行が完了したら、クライアントの検収・確認を経て報酬が支払われます。この際、受託者側から発注書や請求書を送る場合もあります。書式を指定されることもあるので確認しましょう。
なお、クラウドソーシングやエージェントなどの仲介業者を挟んで契約している場合は、契約業者を介して報酬が支払われます。
その過程で仲介業者にマージンが発生することはデメリットですが、契約手続きなどを代行してもらえる点や報酬未払いなどのトラブル防止になる点はメリットです。
フリーランスとして業務委託で働く際の注意点

フリーランスが業務委託で働く際には、以下の点に注意しましょう。
- 契約の種類を確認する
- 不利な条件が含まれていないか十分に確認する
- 偽装請負に注意する
それぞれの注意点について、詳しく解説します。
契約の種類を確認する
フリーランスが業務委託で働く場合は、まず契約書をチェックして契約の種類を確認しましょう。「請負契約」なのか、それとも「準委任契約」なのかによって、報酬の対象となる業務や負う責任などが異なるためです。
請負契約であれば、クライアントから求められる成果物を納品することで、その成果物に対する報酬が支払われます。
準委任契約であれば、基本的にはクライアントから求められる業務を遂行することで、その履行の割合に対して報酬が支払われます。
例えば「SNSを運用しフォロワーを増やしてほしい」という仕事を請けた場合、請負契約ではフォロワーが増えない限り報酬が支払われないことがあるため注意が必要です。一方では、準委任契約であれば、代行する業務そのものに報酬が発生します。
トラブルを避けるためにも、契約ごとの違いを把握しておくことが大切です。
不利な条件が含まれていないか十分に確認する
委任契約を結ぶ際は、受託側に不利な条件が含まれていないか十分に確認しましょう。
主なチェックポイントは、以下の通りです。
- 委託業務の内容
- 報酬・経費・手数料
- 報酬の支払期限
- 業務が中止となった場合のキャンセル料と着手金
- 成果物の著作権の取り扱い
- 損害賠償が発生した場合の責任の所在
- 情報流出を防ぐための対策
- 契約の有効期限
例えば成果物の著作権は、納品した時点でクライアントに渡ることが多いです。しかし、納品後も成果物を自由に使いたい場合は「ライセンス契約」を結ぶことも可能です。必要があれば検討してみましょう。
また、トラブル発生時の責任の所在を確認することも重要です。責任の所在があいまいだと、クライアントの都合で起きた問題でも受託者が責任を負うことになりかねません。
業務委託契約の注意点についてさらに詳しくは、以下の記事で解説しています。
偽装請負に注意する
偽装請負とは、実態は労働派遣であるにもかかわらず、契約上は請負契約と偽装する違法行為です。フリーランス向け案件のなかには、偽装請負のものが潜んでいる可能性があり、受けてしまわないように注意しておきましょう。なぜなら偽装請負はクライアント側にとって都合がよく、受注側にとって不利となるものがほとんどだからです。
すでに解説したように、フリーランスは指揮命令を受けません。仕事の進め方を細かく命令される案件は、偽装請負の可能性があります。
また、「勤務時間が時給制の案件は偽装請負では」というイメージを持つ人もいますが、業務委託でも時給制で契約することもあるため、一概にはいえません。不利益を被らないためにも、偽装請負の定義をしっかり把握しておきましょう。
時給制の業務委託契約で働く場合の注意点に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
フリーランスが業務委託の仕事を探す5つの方法
フリーランスが業務委託の仕事を探す方法として、次の5つの方法があります。
- フリーランスエージェントを活用する
- HP・SNSでの情報発信
- 営業活動を行う
- 業務委託の求人サイトを利用する
- オンラインコミュニティやスクール
それぞれの方法について、以下で詳しく解説します。
1.フリーランスエージェントを活用する
フリーランスエージェントとは、フリーランスに仕事を依頼したい企業とフリーランスを仲介するサービスのことです。登録すると自分のスキルや希望に合致する案件を紹介してもらえるため、自分で営業を行う必要がありません。
フリーランスエージェントが扱う案件には業務委託契約のものが多く、特に準委任契約の案件を探すのにおすすめです。弊社ITプロパートナーズでは、「週に2~3日稼働」「フルリモート勤務可能」など、業務委託でフレキシブルな働き方がしたい人向けの案件も豊富に取り扱っています。ぜひ公式Webサイトで案件をチェックしてみてください。
2.クラウドソーシング・求人サイトで検索する
クラウドソーシングとは、インターネット上で仕事を発注したい企業と仕事を受けたい個人を結びつけるサービスです。「Webデザイン」「動画編集」「データ入力」など、さまざまな仕事が掲載されています。クラウドソーシングが扱う案件は多くが業務委託で、なおかつ初心者向けから上級者向けまで幅広い難易度の仕事があり、自分に合ったものを見つけやすいのが特徴です。
また、正社員やパート・アルバイトの仕事探しに使われる一般的な求人サイトにも、業務委託の仕事が掲載されています。キーワード検索などを駆使してチェックしてみましょう。
業務委託の仕事を探せるWebサイトについては、こちらのページで紹介しています。
3.人脈を使って紹介を受ける
同僚や取引先、友人・知人といった人脈を活用して仕事を紹介してもらうのも有効な方法です。「そもそも人脈をつくるにはどうすればよいのか」と思うかもしれませんが、場合によっては「フリーランスとして仕事を請けている」と周囲の人に言っておくだけで仕事が舞い込むこともあります。まずは身近な人に、仕事を紹介してもらえないか聞いてみましょう。
ただし、業務委託契約を締結することに慣れていない企業の仕事を請ける時は、知識不足から意図せず偽装契約になってしまうこともあるため、注意が必要です。自衛するためにも業務委託契約についてしっかり学んでおく必要があります。
4.自分で営業する
営業スキルに自信がある人は、業務委託のフリーランスを積極的に活用している企業に直接連絡し、営業をかけてみましょう。営業にはメールで連絡したり、ポートフォリオを送付したりと、さまざまな方法があります。
また、「X(旧Twitter)」や「Instagram」といったSNSやブログを使って発信することも、重要な営業活動です。「この人に仕事を依頼したい」と考える企業から連絡が来ることがあるほか、ポートフォリオとしても使用できます。自分の職種やパーソナリティーに合った営業方法を見つけましょう。
5.オンラインコミュニティやスクールを活用する
さまざまな職種のフリーランスが集まるコミュニティに顔を出してみてもよいでしょう。仕事を紹介してもらえたり、プロジェクトに誘われたりして、仕事につながることがあります。フリーランスは職種を問わず業務委託で働く人が多いため、業務委託の仕事が見つかりやすいでしょう。
また、スキルを身につけるためのオンラインスクールによっては、卒業後に提携している企業の案件を紹介してもらえることがあります。スクールに通うことを検討している場合は、案件獲得のサポートが受けられるかどうかも確認しておくのがおすすめです。
まとめ
フリーランスは働き方、業務委託は契約の種類を指す言葉です。よく理解しておかないと混同しやすい言葉なので、本記事で紹介した内容を覚えておいてください。
業務委託で働くことは自由度の高さや高い報酬が期待できることがメリットですが、確定申告が必要なことや労働法が適用されないなどのデメリットもあります。不利益を被らないように、業務委託契約書を取り交わしておきましょう。
弊社「ITプロパートナーズ」はIT/Web分野に特化したフリーランスエージェントで、案件探しや契約のサポートも提供しております。エンジニア・デザイナー・マーケターとして仕事探しをしたい場合はもちろん、契約方法についてもサポートを受けたいという場合でもぜひご活用ください。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)