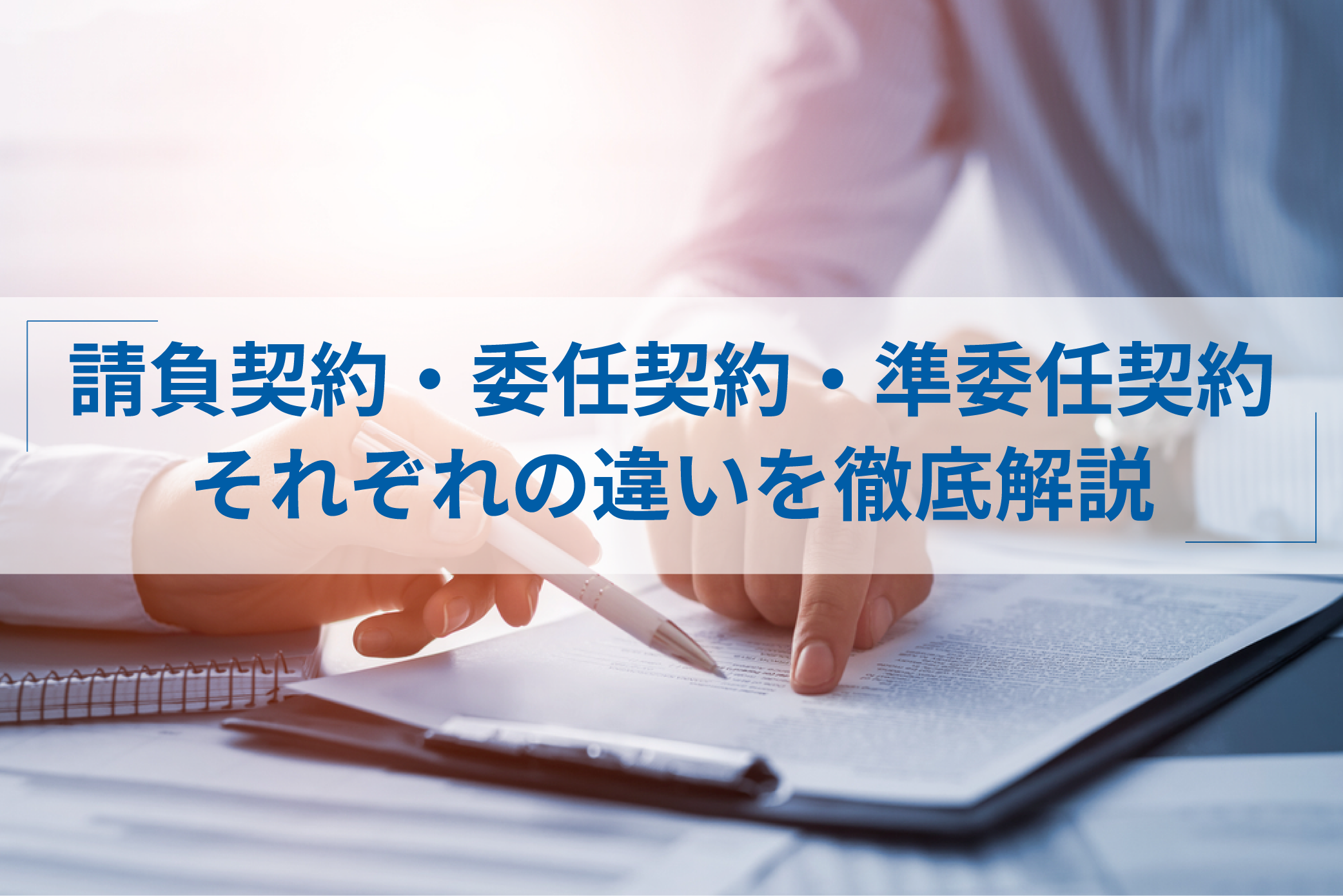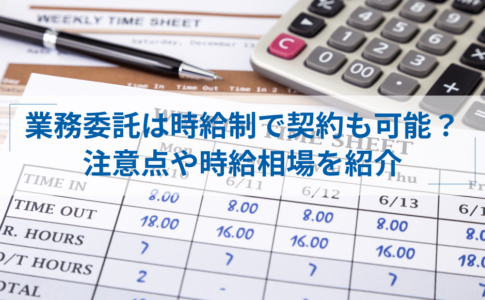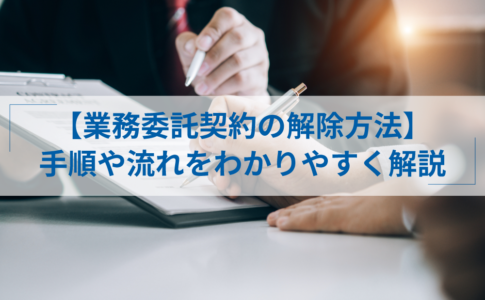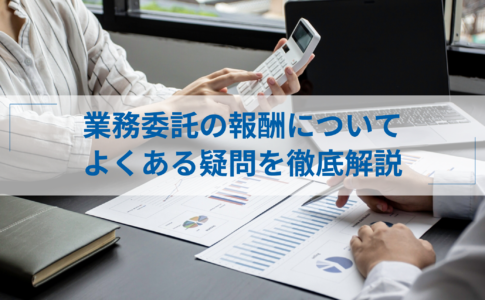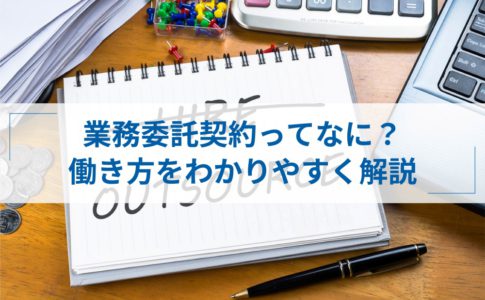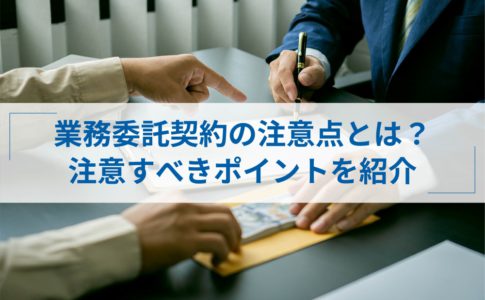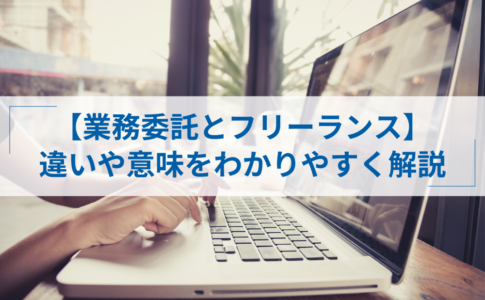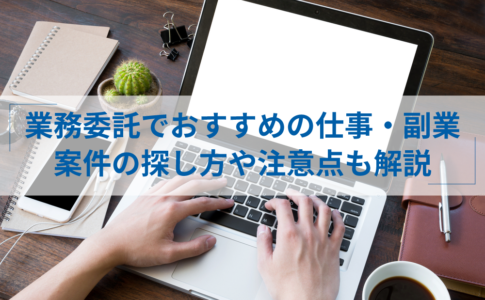こんにちは、ITプロマガジンです。
フリーランスになると、クライアントと契約を結んで働くことになります。業務を委託する際に結ぶ契約である「業務委託契約」には委任契約や準委任契約などがあり、「自分はどの契約を結べばよいのか分からない」と悩む人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「委任契約」・「準委任契約」・「請負契約」の違いを解説しつつ、契約に関してフリーランスが知っておくべきことを紹介します。契約で損をしないためにも、ぜひ参考にしてください。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
委任契約とは

「委任契約」とは、「法律行為を委任する契約」と法律で定義されています。例えばコンビニへ行く友人に「缶コーヒーを買ってきてほしい」と頼むことも委任契約です。買い物とは、お金を払って缶コーヒーの所有権をコンビニから買った人へ移すという売買契約であり、法律行為だからです。
とはいえ、コンビニで買い物をしてもらうために契約書を交わしたり、報酬を支払ったりすることはほぼないでしょう。このように、委任契約とは本来無償契約であり、報酬が発生する場合は別途定めておかなくてはなりません。
ビジネスの場でいう委任契約とは、一般的には報酬を支払って法律行為を代行してもらう有償契約のことを指します。具体的な例は次の通りです。
- 弁護士に刑事裁判の弁護人になってもらう
- 司法書士に不動産登記を代行してもらう
- 税理士に確定申告の手続きを依頼する
ビジネスにおいて委任契約で求められることは、業務を遂行することです。成果に関係なく報酬が発生します。
準委任契約とは
「準委任契約」とは、法律行為とはならない事務を委託する契約のことです。例を紹介します。
- セミナー講師として登壇を依頼する
- 医師に診察してもらう
- Webサイトの保守管理を依頼する
準委任契約では、委任契約と同じく成果は求められないのが特徴です。例えば医師の診療を受け、適切な治療がなされたとしても、全ての病気が100%治るわけではありません。しかし患者側は、治療の結果という成果にかかわらず、決められた代金を支払う必要があります。
「法律行為とはならない事務」の定義は幅広く、ビジネスの場においてはさまざまな行為が準委任契約の対象となります。
請負契約とは

「請負契約」とは、仕事を完成させることに対して報酬が発生する契約のことです。具体例は次の通りです。
- イラストレーターに頼んで似顔絵を描いてもらう
- デザイナーに名刺やパンフレットをデザインしてもらう
- 建築会社に依頼して自宅を建ててもらう
請負契約の仕事では、何よりも成果が重要です。例えば住宅の建築を請け負った建築会社は、建物を契約通りに完成させる義務があります。もしも「仕事はしましたが、完成させられませんでした」となれば、損害賠償問題に発展しかねません。
この「仕事の完成」が、委任契約や準委任契約との大きな違いだといえるでしょう。請負契約での仕事を請けた側は、成果物と引き換えに報酬を得るのが一般的です。
委任契約・準委任契約・請負契約の違い
「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の違いは以下の通りです。
| 委任契約 | 準委任契約 | 請負契約 | |
|---|---|---|---|
| 契約対象とする業務 | 法律行為の提供 | 非法律行為の提供 | 成果物の納品 |
| 報酬の基準 | 仕事をした日数や時間 | 仕事をした日数や時間 | 成果物の納品 |
| 報酬発生タイミング | 業務の遂行時 | 業務の遂行時 | 成果物の納品時 |
| 善管注意義務の有無 | あり | あり | なし |
| 契約不適合責任の有無 | なし | なし | あり |
| 再委託の可否 | 不可 | 不可 | 可 |
各項目を詳しく解説します。
契約対象とする業務・行為が異なる
委任契約は法律行為を委任する契約であるのに対し、準委任契約は法律行為ではない事務行為などを委託する契約を指します。委任契約と準委任契約の共通点は、成果を問われないことです。
また、請負契約は、行為ではなく仕事の完成を目的とする契約です。成果が重要な一方で、完成までのプロセスは問われません。
報酬の基準
委任契約や準委任契約では、行為を提供した時間や日数に対して報酬が発生します。例えば準委任契約でセミナー講師を引き受けた場合、講演の時間や回数によって報酬が変わります。
一方で請負契約では、成果物を納品したことに対して報酬が支払われます。例として似顔絵を1枚を5,000円で引き受けた場合、描くのにかかった時間が1時間であっても10時間であっても、報酬は変わりません。
報酬発生のタイミング
委任契約と準委任契約では、基本的に稼働することで報酬が発生します。業務が完了しているかどうかは関係ありません。
請負契約では、成果物の納品時に報酬が発生することがほとんどです。場合によっては、着手金やマイルストーン報酬(中間報酬)を設定するケースもあります。
善管注意義務の有無が異なる
「善管注意義務」とは、「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」のことです。これは、業務を遂行するにあたって、一般的に要求される注意を払わなくてはならないというものです。
委任契約と準委任契約には善管注意義務があります。例えば医師が行う診療という準委任契約では、医学的な知識や技術に基づいて最善の注意を払いつつ診療する義務があるというわけです。エンジニアとしてWebサイトの保守管理を請け負うのであれば、知見やスキルを駆使し、ベストを尽くすことが求められます。
一方で請負契約では、善管注意義務を負いません。請負契約の案件では納品物を完成させるためにどのような方法を用いてもよく、最終的に納品物さえあれば問題ないからです。
契約不適合責任の有無が異なる
「契約不適合責任」とは、契約内容と異なる成果物を納品した場合に売り主側が負う責任のことです。
請負契約では、契約不適合責任を負うことになります。例えばイラストを10点納品する契約の仕事で5点しか納品しなかった場合、数量が不足しているため、追加の納品や報酬の減額に応じなければなりません。場合によっては損害賠償を請求されることもあります。
一方で、委任契約と準委任契約では基本的に、契約不適合責任を負いません。ただし、前述の「善管注意義務」があるため、仕事内容に問題があれば責任が問われる点は共通しています。
いずれの契約でも、業務の過程や成果物に問題があった場合は、何らかの責任に問われる可能性があると考えておきましょう。
再委託の可否が異なる
「再委託」とは、平たくいえば自分で請けた仕事を下請け業者などの第三者に依頼することです。
委任契約や準委任契約の場合、労務を提供する個人への信頼が重要視される仕事が多く、原則的に再委託はできません。例えば「評判を調べたうえで信頼できそうな人にセミナー講師を依頼したら、断りなく別の人が来た」ということがあっては、依頼者は困ってしまうでしょう。
一方で請負契約では、原則として再委託が可能です。これは、請負契約では納品物を完成させるためにどのような方法を取ってもよいからです。自分1人でこなしても、別の人に依頼しても、成果物さえ完成させれば問題ありません。
ただし、契約内容によっては「請負契約だけれど再委託は禁止」「準委任契約だけれど再委託可能」など、例外を定めることもできます。契約時に確認しておきましょう。
委任契約・準委任契約・請負契約の共通点

「委任契約」「準委任契約」「請負契約」はそれぞれ細かい部分が異なりますが、共通点もあります。どういった点が共通しているのかを知っておきましょう。
中途解約ができる
企業が人を雇う雇用契約の場合、よほどの事情がなければ基本的に解雇できませんが、委任契約・準委任契約・請負契約では、いずれの場合でも中途解約ができます。代表的なのは、「作業を行ったのに報酬が支払われない」「期日になっても成果物が納品されない」といった債務不履行があった場合です。加えて、「プロジェクトが中止された」「フリーランス側の都合が付かなくなった」など、一方的な理由で契約解除に至ることもあります。
ただし、中途解約によって損害賠償や違約金などが発生する可能性もあるため、気軽に中途解約してよいというわけではありません。フリーランス側の事情で中途解約をすれば、信頼も失いかねないでしょう。
クライアントの指揮命令権の対象外
「指揮命令権」とは、業務上の指示を出す権利のことです。具体的には、「仕事の進め方を細かく指定する」「働く時間や場所を指定する」といったことが該当します。
会社員であれば、会社や上司の指示に従うのは当たり前のことです。これは、会社に雇用されている労働者には、労働契約に基づいて職務をこなす義務があるからです。しかし、委任契約・準委任契約・請負契約の場合は、指揮命令権の対象外です。例えば「イラストを納期までに10枚描く」という請負契約では、「1枚につき1時間以内で描くこと」などといった命令はできません。
労働基準法の対象外
フリーランスは基本的に労働基準法の対象外です。
労働基準法とは、「労働時間は1日8時間、1週間で40時間」「時間外労働には割増賃金を支払う」など、労働条件の最低基準を定めた法律のことです。労働基準法の対象となるのは企業などに雇用されている人であり、フリーランスは該当しません。会社員は就業規則で勤務時間や休日が決められていますが、フリーランスは働く時間や日数、休日などもすべて自分で決めることになります。
フリーランスは労働基準法に守られていないため、収入を得るために休みなしで働くことも可能です。しかし自由度が高いと同時に、自己管理が重要であることを覚えておきましょう。
委任契約・準委任契約のメリットとデメリット
「委任契約」や「準委任契約」で働くメリットやデメリットは次の通りです。
| メリット | ・収入が安定する ・さまざまな業務を経験できる ・成果を求められない |
| デメリット | ・働き方が制限されることが多い ・労働基準法に守られない ・業務内容によっては不公平感が出る |
それぞれ詳しく解説します。
メリット
委任契約・準委任契約には長期にわたるプロジェクトも多く、安定して収入を得られることが多いのがメリットです。また、成果物を求められないため、企画や戦略立案、コンサルティングといった、目に見える成果がない業務を幅広く行える点も魅力だといえるでしょう。
デメリット
委任契約・準委任契約のデメリットは、業務をこなすために働く時間や場所が制限されるケースがある点です。「出社したうえで社内サーバーの保守管理をしてほしい」という仕事では、社員と同じように出勤する必要があります。
また、職種によっては行う業務が社員とほぼ同じになることも多く、不公平に感じることも珍しくありません。
請負契約のメリットとデメリット
「請負契約」で働くメリットやデメリットは次の通りです。
| メリット | ・働き方の自由度が高い ・副業との相性がよい ・収入アップしやすい |
| デメリット | ・成果を出さなければ収入を得られない ・継続性が低い ・労働基準法に守られない |
それぞれ詳しく解説します。
メリット
請負契約では成果物さえ完成させればよく、自分のペースで作業ができます。夜間や早朝に仕事をしても問題ありません。働き方の自由度が高いのが大きなメリットです。休日や空き時間を活用して業務をこなす副業との相性もよいといえるでしょう。
また、多くの仕事をより短時間でこなすことで収入アップが実現できます。1時間かかる仕事を30分でできるようになれば時給換算で倍となり、大きく稼ぐことも可能です。
デメリット
デメリットは、基本的に成果を出すことで初めて報酬が発生することです。完成までに数ヶ月かかるような仕事の場合、その間は無収入になってしまうケースもあります。さらに完成までに予想より時間や手間がかかった場合は、時給換算で収入ダウンとなってしまう可能性もあるでしょう。
このほか、単発の案件が多く、成果物が完成したら終了になることも珍しくありません。職種によっては継続案件を見つけるのが難しい場合もあります。加えて、労働基準法で守られないのは委任契約や準委任契約と同様です。
委任契約・準委任契約・請負契約の見分け方
案件が委任契約・準委任契約・請負契約のどれに該当するかは、業務内容などからある程度推測が可能です。見分け方を解説します。
委任契約・準委任契約の場合が多い業務内容
まず、「裁判の弁護人になってほしい」など、依頼内容が法律行為の場合は委任契約です。
法律行為以外の要件定義や設計、戦略立案など、明確なゴールや成果物が存在しない業務の多くは、準委任契約を締結します。こういった業務は調整や話し合いをしながら進めていく必要があるため、幅広い業務に柔軟に対応できる準委任契約が適しています。
Webサイトの運営やSNS運用なども、「このような状態になったら完成」といえるものではないため、準委任契約が採用されることがほとんどです。
請負契約の場合が多い業務内容
Webサイトやイラストの制作、アプリ開発といった明確な納品物が存在する業務は、請負契約の場合がほとんどです。
準委任契約が多いWebサイトの運営でも、「アクセス数を倍にしてほしい」などの明確な目的がある場合は、請負契約が採用されることがあります。しかし請負契約では目的を達成しない限り報酬が支払われないため、割に合わないケースも出てきます。「準委任契約だと思っていたら実は請負契約だった」となれば、報酬を受け取れるタイミングや負う責任などが異なるため、注意が必要です。
まとめ
フリーランスがクライアントと契約を結ぶ際は、「準委任契約」なのか、それとも「請負契約」なのか、契約内容を確認しましょう。契約内容によっては、フリーランス側に不利になるケースも出てくるからです。トラブルを避けるためにも、契約に関する基礎的な知識を身につけておきましょう。
「直接企業と契約するのはハードルが高そう」と不安なときは、フリーランスエンジニア向けの案件を多数取り扱っている「ITプロパートナーズ」にご相談ください。専属スタッフがご希望に合う案件を紹介し、契約をサポートします。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)