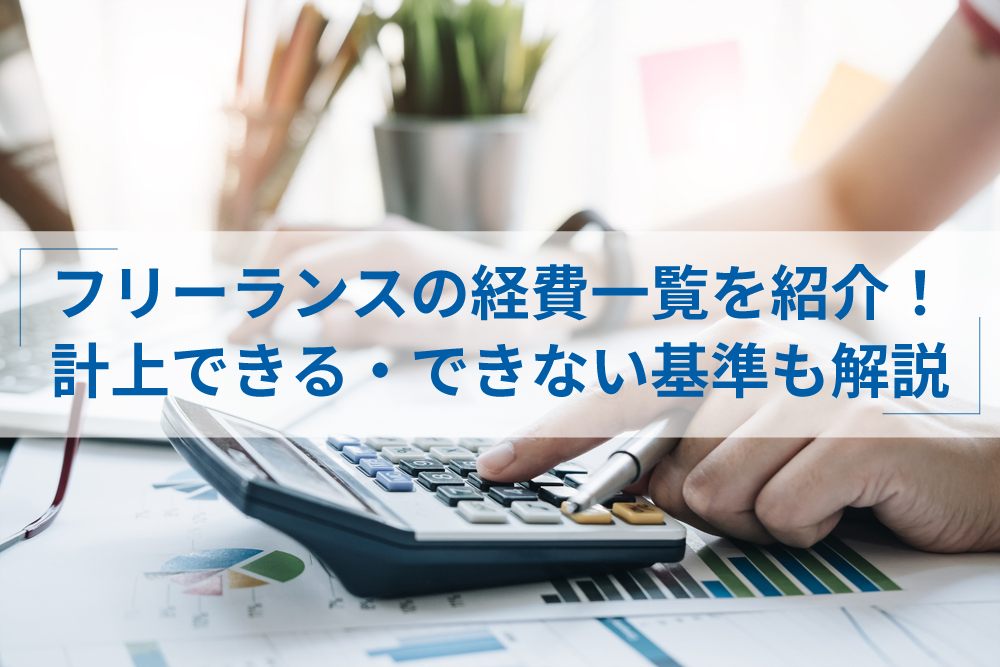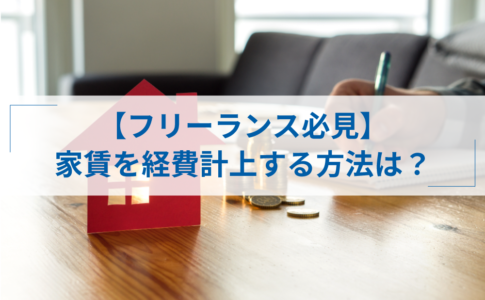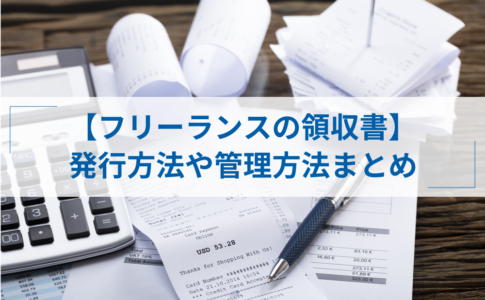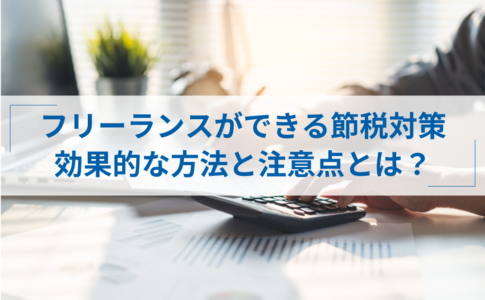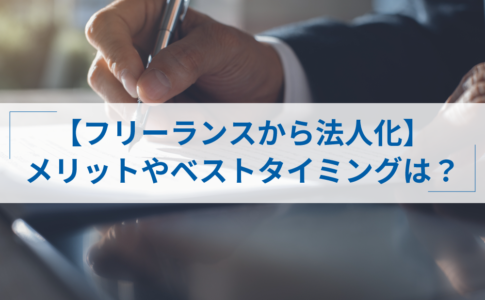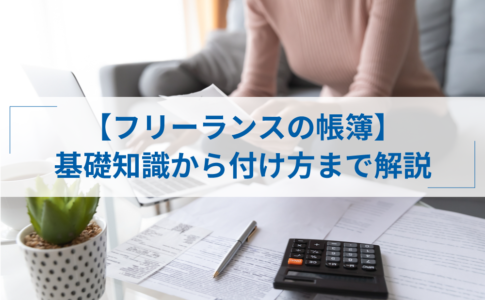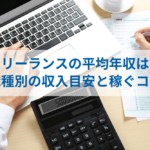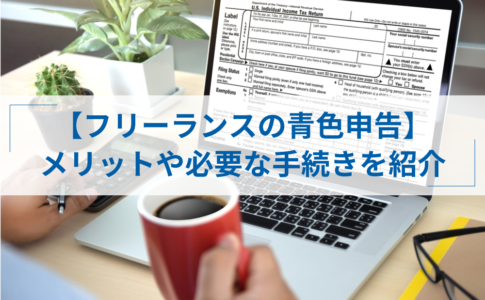こんにちは、ITプロマガジンです。
フリーランスや個人事業主として収入を得る際にも、会社で働いていた時のような、所得税に対する年末調整のように、所得に対して支払った税金の調整として確定申告が必要になります。この確定申告においては、経費を活用し税金の控除となる仕組みを便利に使うことにより、適切な税金を納めることができ、また節税対策にも繋がります。
しかし、どんなものが経費として計上できるのか?を理解していないと、節税どころか脱税となってしまうリスクもあります。そこで今回は、フリーランスなら必ず知っておくべき経費についてまとめました。
- フリーランスが経費にできるもの・できないものの基準
- フリーランスが経費にできる項目一覧
- 経費を計上する上での注意点
などわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
なお、まずフリーランスの税金周りについて理解しておきたい人は「フリーランスが支払う税金の種類」の記事も参考にしてみてください。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
フリーランスにおける経費とは
経費とは、事業を行うにあたって必要な費用を指します。よく使われているのが「必要経費」という言葉で、事業で使用する設備機器や取引先との飲食代、移動時の交通費など、経費として計上できる費用はさまざまです。
会社員にとっての経費は、会社のお金で購入できる「自分の負担にならない費用」というイメージですが、フリーランスは自分で経費を負担しなければなりません。しかし、フリーランスにとって経費を計上することはメリットでもあります。詳しくは次項で解説します。
フリーランスが経費を記録・計算する必要性とメリット

フリーランスにとって経費はメリットでもあるとお伝えしました。ここではその理由と経費の必要性について解説します。
確定申告・節税・還付金のために必要
フリーランスは確定申告を行うことにより税金を納めますが、経費は確定申告で記入する所得金額に影響を与える費用です。確定申告では、総収入から経費や各種控除金額を差し引いたものが「課税所得」となり、課税所得に税率を乗じて所得税を算出します。課税所得の算出方法は以下の通りです。
仮にあなたがフリーランスデザイナーの仕事をしていて、画材や道具の購入に1万円の必要経費がかかったとしましょう。確定申告時に総収入から経費の1万円を差し引くことで、納めるべき税金額を抑えられます。
同じ売り上げでも経費が多いほど所得は少なくなり、節税につながるのです。さらに報酬から源泉徴収され還付金が発生する場合、還付金額が多くなるというメリットもあります。
帳簿作成・税務調査のために必要
事業所得の確定申告をする方には、帳簿の作成義務があります。確定申告時に帳簿は提出しませんが、税務調査の際には提示を求められることがあります。帳簿作成のために経費の金額を詳しく控えておき、レシートや領収書などの明細も保存しておきましょう。
帳簿付けには会計簿記の知識が必要ですが、会計ソフトを活用することで効率的に作業ができます。また、2022年からは電子帳簿保存法が施行され、要件を満たせば電子データによる保存が可能になりました。ペーパーレス化やコスト削減などの観点からも会計ソフトの利用がおすすめです。
フリーランスはどこまで経費にできる?基準について解説

支出が経費として認められるかどうかは「事業に関係している費用であるか」が判断基準となります。ただし、「家事按分(かじあんぶん)」と「減価償却」については注意が必要です。
家事按分とは、「プライベートと事業の両方を兼ねる支出」を一定の割合で事業分のみ算出する方法。減価償却とは固定資産の費用を耐用年数に応じて配分し、毎年経費として計上する方法です。それぞれの詳しい算出方法は別項でお伝えします。以下ではフリーランスが悩みやすい経費の例を紹介しましょう。
例1:カフェで仕事した場合コーヒー代は経費になる?
カフェで仕事をした際にかかったコーヒー代は、一定の条件を満たせば経費として計上可能です。例えば、取引先との打ち合わせや一人で仕事を進めるためにカフェを利用したなら、かかった費用を経費にできます。この場合、カフェのコーヒー代は業務に直接関係する費用として認められるためです。
ただし、プライベートの利用は経費の対象にはなりません。
例2:引越し代は経費として計上できる?
フリーランスとして仕事をするための事務所の引越しをした場合、それにかかった費用は経費として計上できます。事務所は事業を営むために必要なものだからです。
なお、フリーランスのなかには、自宅の一部を事務所として使用している人もいるでしょう。そのようなケースでは、事務所として使用している部分の引越しにかかった費用のみを経費として計上できます。
例3:フリーランスでも接待交際費を経費にできる?
業務上の妥当性がある支出であれば経費として計上できます。接待交際費は、取引先との付き合いに対して発生した費用に用いる勘定科目です。例えば、取引先との商談のために開催した食事会の費用は、接待交際費として計上できます。
ただし、取引先と食事をしたとしても、業務上の妥当性が認められなければ経費としては計上できません。接待交際費を計上する際は、内容をしっかり吟味したうえで正確に判断する必要があります。
フリーランスが経費にできるもの15項目一覧まとめ
家事按分を理解したうえで、経費として考えられるものについて15項目を一覧でまとめました。
| 勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 開業費 | 開業にかかった費用 |
| 地代家賃 | 事務所等の家賃 |
| 水道光熱費 | 電気・水道・ガス代など |
| 広告宣伝費 | 名刺など |
| 支払い手数料 | 振り込み手数料など |
| 旅費交通費 | 電車代・タクシー代、宿泊費など |
| 新聞図書費 | 書籍や雑誌など |
| 通信費 | インターネットや電話代など |
| 接待交際費 | 取引先との食事など |
| 外注工賃 | 外注にかかった費用 |
| 租税公課 | 個人事業税、固定資産税、自動車税など |
| 給料賃金 | 従業員へ支払った給料 |
| 諸会費 | 自治会費など |
| 消耗品費 | プリンターのインク代など(10万円未満のもの) |
| 減価償却費 | パソコンや車など(10万円以上のもの) |
フリーランスが経費にできるものとしては、このようにさまざまな種類があります。開業準備のために支払った費用は開業費として計上が可能です。開業費は「繰延資産」として特殊な処理が必要となりますが、詳しくは次項で解説します。
パソコンなど長期間使用できる物品の購入費用で10万円以上のものは、一括ではなく「減価償却費」として毎年少しずつ経費にしましょう。詳しくは「フリーランスの経費として減価償却費を計上する方法」の章で解説します。
さらに自宅と事務所を兼ねている場合、「地代家賃」「水道光熱費」「通信費」などは家事按分が必要になる可能性があります。家事按分の詳しい算出方法は「フリーランスの経費における家事按分の方法」で解説します。
フリーランスが開業費を経費として計上する方法
開業費とは、開業準備のための支出を指します。以下は開業費として認められる支出の一例です。
- 事務所の賃貸費用(敷金・礼金は除く)
- パソコン購入費
- 広告宣伝費
- 打ち合わせ費用
これからフリーランスとして活動を検討している方は、独立準備にかかった費用の領収書を保管しておくとよいでしょう。ただし、10万円を超えるものや仕入れ代金は対象となりません。
開業費は「繰延資産」という科目で一旦計上し、毎年「償却」することで経費にします。償却方法は、事業者が任意の金額を償却費として認める「任意償却」と、5年間に分けて毎年少しずつ計上する「均等償却」の2種類。利益が生じた際に自由に経費計上できる「任意償却」で処理するのが一般的です。
フリーランスの経費における家事按分の方法

家事按分をする際は、客観的かつ合理的に説明できる割合を意識する必要があります。誰から見ても適切であると認められるように経費を計上しましょう。
たとえば、50平方メートルの自宅のうち、10平方メートルを事務所として使用しているとしましょう。この場合、事務所として使用している割合は20%です。この自宅の家賃が10万円であれば、事務所の家賃として経費に計上できるのは2万円となります。
また、光熱費は、業務時間をもとにして計算する方法があります。たとえば、1ヶ月の電気代が2万円、1週間のうち業務時間が25%であれば、経費として計上できるのは5,000円です。なお、自宅のコンセントの差込口の数を数え、業務に使用している割合をもとに電気代を計算する方法もあります。
フリーランスの経費として減価償却費を計上する方法
減価償却費は、固定資産を耐用年数に応じて配分し、毎年一定額ずつ経費として計上するための科目です。高額かつ長く使う資産に対する費用を分割して計上することで、実態に近い形で会計数値を表す効果があります。
個人事業主の場合、事業とプライベートの両方で使用するものについては、減価償却費も家事按分が必要です。減価償却費の処理方法は、大きく分けて「一括償却資産」と「通常の減価償却」の2種類に分けられます。
10万円以上20万円未満の一括償却資産の場合
一括償却資産とは、経年劣化などによる資産の価値減少に合わせて、毎年経費に計上する方法です。ただし、10万円以上20万円未満の資産に限ります。固定資産の耐用年数は法令で定められており、パソコンの耐用年数は4年となっていますが、一括償却資産であれば3年の均等償却が可能です。
例えば、15万円のパソコンを購入した場合を例に挙げてみましょう。
- 購入時:パソコン購入代金15万円を一括償却資産として計上
- 決算時:3年間、減価償却費として毎年5万円を計上
購入したパソコンをプライベートでも使用する場合には、家事按分が必要です。利用時間の割合を算出し、事業用とされる分のみ減価償却費として計上します。
一括償却資産として計上できない場合
一括償却資産にできない場合は、通常の減価償却で処理します。減価償却は月割り計算が必要となり、計算方法は「定率法」「定額法」の2種類です。法定年数が経過後も資産は残っていることから、どちらも最終年度には1円の価値を残して処理します。300万円の普通自動車(耐用年数6年)を新車で購入した例をもとに、計算方法についてそれぞれ説明します。
定率法での計算方法
定率法は、一定の償却率を乗じて毎年同じ割合を償却処理する方法です。償却率は耐用年数ごとに定められており、耐用年数6年の償却率は0.334となります。300万円の普通自動車(耐用年数6年)を新車で購入した際の計算方法は、以下の通りです。
- 1年目:100万2,000円(300万円✕0.334)
- 2年目:66万7,332円(199万8,000円✕0.334)
2年目は、購入代金300万円から1年目の減価償却費を差し引いた金額に償却率を乗じます。さらに、事業で利用する割合が80%として家事按分する場合は、240万円✕0.334となり、1年目の減価償却費は80万1,600円です。
定額法での計算方法
定額法では、取得額に償却率を乗じて毎年同じ額を償却処理します。個人事業主は税務署に届け出をしない限り、定額法が原則となるため注意しましょう。耐用年数6年の定額法償却率は0.167です。300万円の普通自動車(耐用年数6年)を新車で購入した際の計算方法は、以下になります。
- 1年目~5年目:50万1,000円(300万円✕0.167)
- 6年目:49万4,999円
事業で利用する割合が80%として家事按分する場合は、240万円✕0.167となり、1年目~5年目の減価償却費は40万800円、6年目は39万5,999円となります。
フリーランスの経費に関する領収書の扱い方・保存方法

経費を計上する場合、業務として購入した商品などの領収書を7年間保管しておく必要があります。
何故なら、確定申告の際に領収書を提出する必要はありませんが、税務調査が入った場合に、正しく経費計上をしていたか?の証明として領収書やレシートの提出を求められることがあるからです。
青色申告をした場合、経費計上した領収書は7年間の保管義務があるので、捨てずにきちんと保管しておきましょう。(白色申告の場合は5年間)
領収書でチェックすべきポイント
経費を計上するうえでは、領収書に必要な情報がきちんと記載されている必要があります。領収書をもらう際は、以下の項目が書かれているかチェックしましょう。
- 宛名
- 支払った日付
- 購入金額
- 購入したモノやサービスの内容
領収書に不備があると経費として認められなくなる恐れがあるため、よく確認してください。
電子データで保存する方法
電子帳簿保存法の改正により、領収書はデジタルでも保管できるようになりました。ただし、デジタルでの保管については細かいルールがあるため、よく確認したうえで対応する必要があります。たとえば、もともとデジタルで発行された領収書は、そのままデジタルで保管しなければならなくなっています。
一方、紙で発行された領収書をデジタル化して保存する場合は、クラウドでの保存やタイムスタンプの付与などの条件を満たさなければなりません。
詳しくは、国税庁資料の「電子帳簿保存法が改正されました」をご確認ください。
領収書を紛失した場合の対処方法
領収書を紛失しても、出金伝票を作成しておけば経費の計上が可能です。出金伝票は取引内容を記録するためのものであり、取引の実態が分かるように作成する必要があります。日付、勘定科目、金額などの情報をしっかり記載しましょう。
フリーランスの経費における注意点
ここからは、フリーランスにおける経費の注意点を解説します。
不正計上は罰則を受けることになる
経費を計上すれば節税になるため、経費をなるべく多く計上したいと考える人もいるでしょう。しかし、経費を正しく計上しないと罰則を受ける恐れがあるため、注意が必要です。事業との関係を説明できない費用を経費に計上すると、不正計上とみなされるリスクがあります。経費を計上する際は、事業とどのような関係があるか必ず確認してください。
フリーランスの経費は戻ってくるわけではない
フリーランスの経費は自分自身が負担する費用です。節税になるとはいえ、会社員のように負担分が戻ってくるわけではないため経費の使いすぎには注意しましょう。経費が増えるということは、それだけ出費も増え所得が減るということ。所得金額があまりにも少なすぎると、事業運営や生活にも影響が出かねません。経費が多いほど得になるとは考えず、備品などの購入は計画的に行いましょう。
個人と法人では経費にできる項目が異なる
個人と法人では経費として認められる対象が異なり、フリーランスでも法人化することで経費対象の範囲が広がります。法人では、個人が計上できる経費に加えて給与や賞与なども含まれるため、自分自身に支払った給与も収入から差し引きが可能です。そのため大きな節税効果が期待できるといえます。また、物件の賃貸契約を法人名義とすることで家事按分が不要となります。
フリーランスの経費についてのよくある疑問
開業費として認められる期間やフリーランスが経費にできる割合など、経費に関する疑問についてお答えします。
フリーランスの開業費はいつまでさかのぼれる?
開業準備に何ヶ月・何年など長い期間がかかった場合、いつまでさかのぼって開業費を計上できるのかが分かりにくいことがあります。開業費として認められる期間については定められておらず、開業前の支出であれば何年前の費用でも計上は可能です。ただし、開業費として証明および説明できる必要があり、開業前6ヶ月~12ヶ月程度が一般的とされています。
フリーランスが経費にできる割合はいくらまで?
現在の確定申告の仕組みは、収入金額から必要経費を引いたものが所得となり、この所得に対する税金を納めるというものです。従って、所得が少ない場合には税金も少なくなるので、「できるだけたくさん経費として計上したい」と考える方もいるでしょう。
しかし、収入に対して経費が多すぎると税務署からチェックが入りますので注意が必要になります。では、フリーランスが経費にできるのはいくらまでなのでしょうか?
実はこれは業種や人によって様々なので一概には言えません。ただし、一般的にフリーランスの場合は経費率がおよそ6割程度を超えてしまうと脱税が疑われ税務調査の対象となる可能性があると言われています。例えばフリーランスエンジニアの経費率は4割〜5割程度が一般的と言われています。
もしも不正に経費を計上しすぎた結果、税務調査が入った場合、重い追徴課税の納付を求められる可能性があります。
しかしもちろん、正しく経費を計上した結果、高い経費率になってしまっている場合は万が一税務調査が入ったとしてもきちんと証明ができれば問題ありません。正しい経費計上をしているか証明するためには領収書をきちんと保管するなどの必要があります。
フリーランスの経費精算業務を効率化するには?
フリーランスの経費精算には手間がかかるため、効率化も意識すべきです。事務作業を効率化できれば、メインの業務に専念しやすくなります。
たとえば、確定申告ソフトやオンラインアシスタントなどを活用すると、スムーズに経費精算や確定申告の作業を進められます。より適切に経費精算を行うためには、税理士に依頼するのもおすすめです。節税について専門家の視点からアドバイスをもらえます。
まとめ:フリーランスは経費の管理も大切
いかがでしたでしょうか。
フリーランスにおいても、費用計上をしっかりとしてれば節税に役立つことになります。
ただくれぐれも業務利用、私的利用を明確にする、家事按分は重要ですので、しっかりと管理をしていきましょう。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)