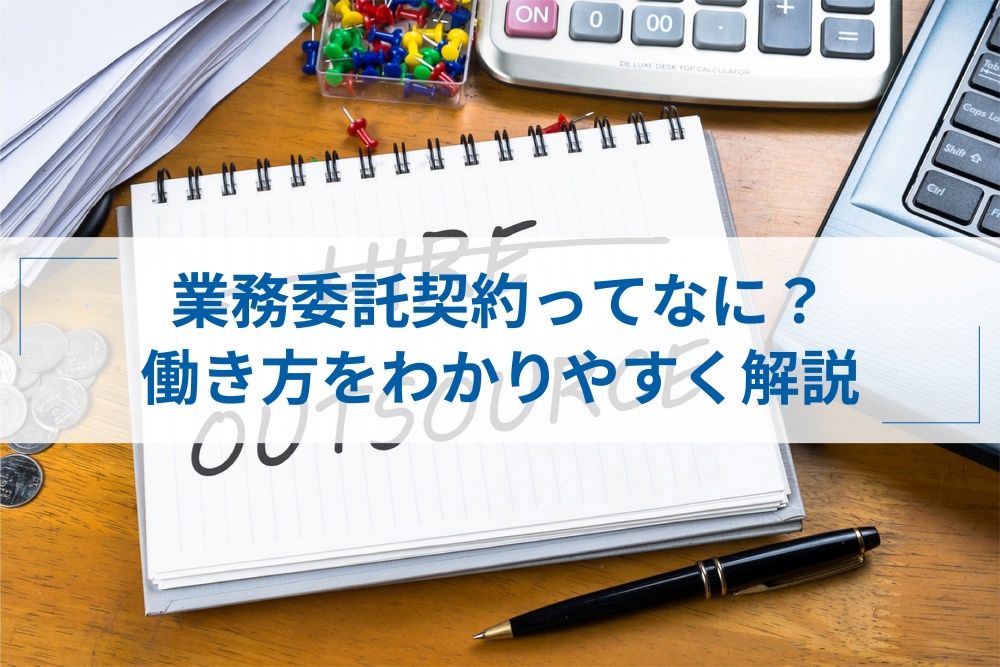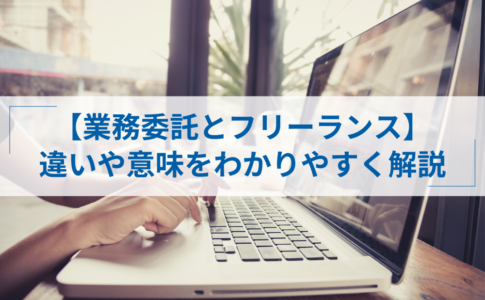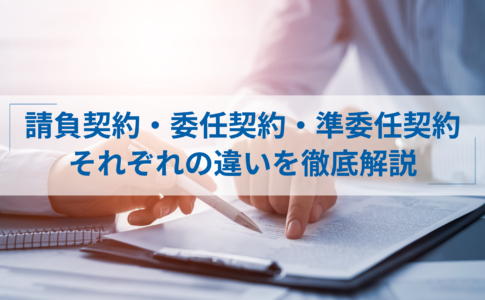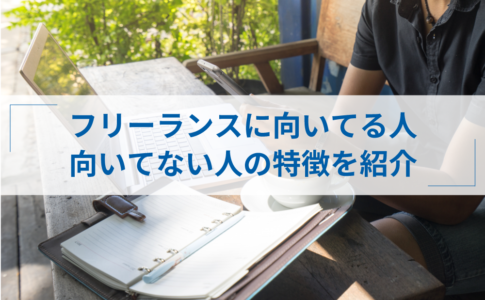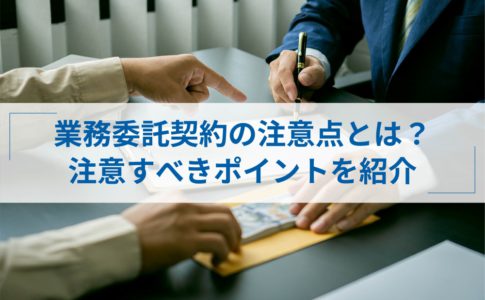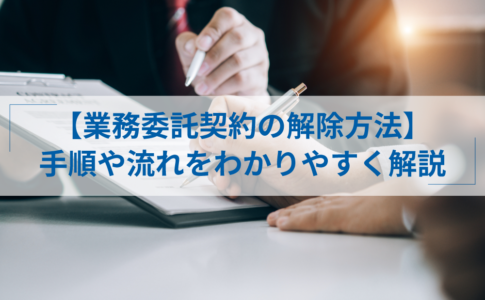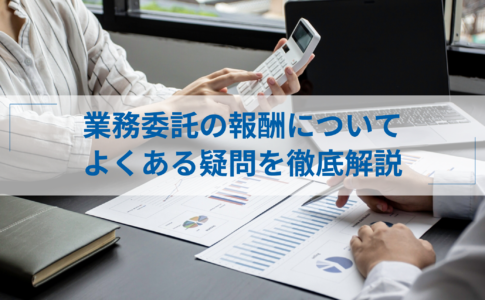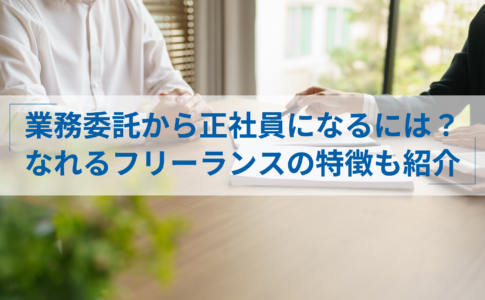こんにちは、ITプロマガジンです。
近年、副業やフリーランスなど働き方が多用化していることもあり、業務委託として働く人も多くなっています。
しかし、すでに副業やフリーランスとして活躍していても、業務委託契約について実はあまりよく理解していないという人もいるでしょう。また、これからフリーランスになりたいと考えており、業務委託契約について確認したいという人もいるのではないでしょうか。
この記事では、業務委託契約の概要や具体的な契約内容、契約を結ぶ際の注意点などを紹介します。業務委託契約について正しく理解するために、ぜひ役立ててください。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
業務委託契約とは?

業務委託契約とは、企業が業務の一部を第三者に依頼する際に結ぶ契約です。業務を引き受けた人は社員のように労働力を提供するのではなく、仕事の成果を提供する必要があります。
雇用契約を結んでいる社員には時給や月給などの給与が支払われるのに対し、業務委託契約を結んでいる人には仕事の成果に対する報酬が支払われる仕組みです。
一般的に「業務委託契約」や「業務委託で働く」などとよく耳にしますが、実は法律上には「業務委託契約」というものはありません。契約については民法が規定しているのですが、そのなかでは明言されていないのです。
業務委託契約と雇用契約の違い
業務委託契約と雇用契約にはさまざまな違いがあります。業務委託契約と、雇用契約の雇用形態ごとの違いをまとめると、以下のとおりになります。
| 業務委託 | 派遣社員 | 契約社員 | バイト | |
|---|---|---|---|---|
| 雇用関係 | なし | 派遣先と締結 | あり | あり |
| 契約期間 | あり | 契約に基づく | 有期or無期 | 有期or無期 |
| 指揮命令 | なし | あり | あり | あり |
| 労働法 | 適用外 | 適用 | 適用 | 適用 |
| 提供するもの | 成果物 | 労働力 | 労働力 | 労働力 |
業務委託契約はあくまでも仕事の成果を提供するだけであり、労働法は適用されません。それに対して派遣社員、契約社員、バイトはいずれも雇用契約を結んで労働力を提供しているため、労働法の対象になります。
なお、業務委託とは、企業の業務を外部へ委託するための契約方法を表しています。それに対してフリーランスとは、個人で仕事をする働き方のことです。つまり、フリーランスとして働く人は、仕事を受注する方法の1つとして業務委託を選択します。詳しくは以下の記事も参考にしてください。
業務委託契約の3つの種類
業務委託契約は、請負契約、委任契約、準委任契約の3種類に分かれています。
| 請負契約 | 委任契約 | 準委任契約 | |
|---|---|---|---|
| 契約対象とする業務 | 成果物の納品 | 法律行為の提供 | 非法律行為の提供 |
| 報酬の基準 | 要求されるレベルを満たした成果物の納品 | 仕事をした日数や時間 | 仕事をした日数や時間 |
| 報酬発生タイミング | 成果物の納品時 | 業務の遂行時 | 業務の遂行時 |
| 善管注意義務の有無 | なし | あり | あり |
| 契約不適合責任の有無 | あり | なし | なし |
| 再委託の可否 | 可 | 不可 | 不可 |
以下にて、それぞれの業務委託契約の特徴を解説します。
1.請負契約
請負契約は、成果物と納期が決まっている契約のことです。発注者は成果物の完成をもって請負人に報酬を支払う形式になります。
例えば、システムエンジニアの場合、決められた納期までに受注したシステムなどを完成させて納品することが契約です。
請負契約では、成果物が発注された通りに完成しているか、不具合や問題点はないかという点に責任を負いますが、決まりがない限り、開発した場所などについては、責任を追いません。簡単にいうと、「この仕事やってきたら、その成果分だけお金あげるね」という契約です。
請負契約には「善管注意義務」がない代わりに「契約不適合責任」があります。善管注意義務とは、常識的なレベルで注意しつつ業務に取り組むことです。契約不適合責任は、要求されるレベルを満たした成果物を納品する義務を指します。
また、成果物を納品できれば手段は問わないため、請負契約は再委託できます。ただし、再委託先を選ぶ際は、業務に見合う力があるか、情報漏洩が起きないかに注意してください。また、契約書で禁止されていれば、請負契約でも再委託できません。
請負契約を締結する職種の一例を以下に示しました。
- デザイナー
- ライター
- プログラマーなどエンジニア(成果物の完成責任あり)
- コンサルタント(成果物の完成責任あり)
2.委任契約
委任契約は、行為(業務)の実行について相手側にその遂行を委任(任せて委託)する契約です。ですから、成果物はなく契約不適合責任はありません。業務自体が対価となる契約のため、善管注意義務を果たしながら業務を果たすと、契約を全うしたことになります。なお、業務遂行が条件のため、委任契約では再委託が認められません。
委任契約を締結する職種の一例を以下に示しました。
- 弁護士
- 税理士
- 司法書士
- 不動産関連の職種
3.準委任契約
委任契約では法律行為を提供しますが、準委任契約では非法律行為を提供します。ただし、善管注意義務を果たしながら業務に取り組み、契約不適合責任を問われないところは、委任契約も準委任契約も同じです。
簡単にいうと、「この仕事やらなくちゃいけないんだけど、代わりにやっておいて」が、準委任契約となります。
この準委任契約は、必ずしも結果を出さなければならないというわけでもなく、コンスタントにさまざまな仕事ができるというメリットがありますが、一方で準委任契約の性質上、継続してその仕事を行えるというわけではないことがデメリットともいえます。
仕事内容の変更や更新はクライアント側に権限があるので、自分の意思とは反した仕事を任される時もあるのが事実です。
そのようななか、自分が理想としている仕事を追い求めることに疲れてしまうフリーランスの方もいます。
準委任契約を締結する職種の一例を以下に示しました。
- 美容師
- エステティシャン
- コンサルタント(成果物の完成責任なし)
- エンジニア(成果物の完成責任なし)
業務委託で働くメリット・デメリット
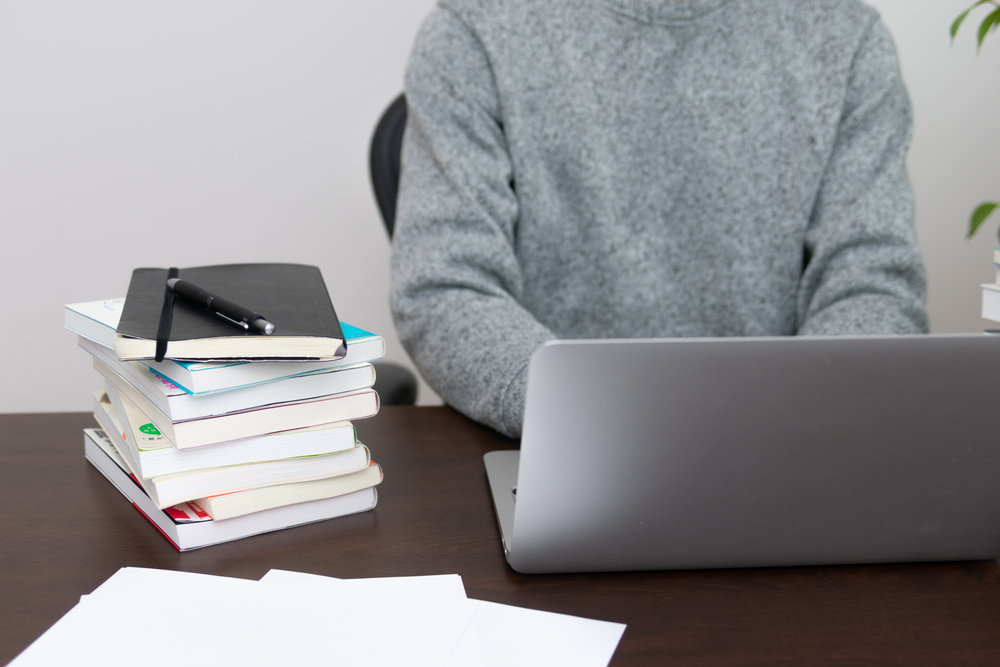
業務委託で働けばさまざまなメリットがあります。ただし、デメリットといえる部分もあるため、注意も必要です。
ここでは、業務委託で働く際のメリット・デメリットをそれぞれみてみましょう。
業務委託で働くメリット
業務委託で働くと、自分のペースで働き方を調整しやすくなります。具体的なメリットは、以下のとおりです。
得意分野を選んで仕事ができる
業務委託契約では、1つ1つの案件ごとに受注が可能です。自分の得意分野に特化して案件を受注すれば効率的に仕事をこなせ、スムーズに高いクオリティを提供できる可能性が高いと考えられます。また、苦手な作業に取り組む必要がないため、ストレスなく働けるでしょう。
働く時間や場所の自由度が高い
案件にもよりますが、業務委託契約で受注できる仕事は、働く時間や場所の制限がない場合が一般的です。仕事の成果を提供して報酬を受け取る契約であるため、求められている成果物を期限までに納品すれば問題ありません。
そのため、自分の都合に合わせて働く時間や場所を自由に決められます。例えば、早朝や深夜に仕事をしたり、自宅やカフェで作業したりすることも可能です。子育てや介護をしながら働きたい場合も、業務委託契約なら実現しやすいでしょう。
高収入が期待できる
業務委託契約の場合、どのような案件をどれくらい受注するかによって収入は大きく変化します。スキルや経験があれば、高単価な案件の受注も可能です。そのため、業務委託契約で働けば、雇用契約を結んで毎月一定の給与を受け取るよりも高収入を得られる可能性があります。
平均的な単価の案件を受注するとしても、たくさんの仕事をこなせば雇用契約以上の収入を目指すことが可能です。自分自身の努力次第で収入が変わるため、高収入を目指したい人に業務委託契約は適しています。
業務委託で働くデメリット
業務委託で仕事をする場合、不安定な部分も多くなります。業務委託で働くデメリットについても確認しておきましょう。
労働法が適用されない
業務委託契約は労働力ではなくあくまでも成果物を提供するだけであり、労働法の対象にはなりません。業務委託で働いているフリーランスの労働環境が悪化していても、労働法による保護は受けられないことになっています。例えば、労働時間が長くなっていたり時給換算した場合に報酬が最低賃金を下回っていたりしても、企業に対して改善を求められません。
そのため、フリーランスは自分自身で働き方や健康状態を管理する必要があります。業務委託で働くなら自己管理を徹底することが大切です。
自分で仕事を探す必要がある
業務委託契約の案件を受注するには、自分で仕事を探して契約する必要があります。業務委託の仕事を募集している企業はたくさんありますが、全ての企業が常に募集を出しているわけではありません。また、自分が仕事を探している時に、自分の得意分野にマッチする案件が必ず出ているとは限らないでしょう。
そのため、仕事を探してもすぐに受注できない可能性もあります。スムーズに仕事を獲得するには、実績を積んだりさまざまな相手と人脈を築いたりする必要があります。
収入が途絶える可能性がある
業務委託は案件ごとに契約を結ぶため、一度契約しても永遠に仕事をもらえるわけではありません。継続的な依頼を前提としている案件もありますが、プロジェクトが終了すれば契約が終了する可能性があります。
契約が終了してほかの仕事を受注できなければ、収入が途絶えるリスクがあるため注意が必要です。業務委託で働くフリーランスは収入が不安定になりやすいため、万一収入が途絶えた時に備えて、ある程度の貯金を確保しておいたほうがよいでしょう。
事務作業を自分で行う必要がある
業務委託で働く場合は、メインの業務以外の事務作業も自分で対応しなければなりません。例えば、請求書の発行や確定申告など、さまざまな事務作業が発生します。事務作業には意外に手間や時間がかかるため、業務委託の仕事を進める時間を削らなければならない恐れもあるでしょう。
特に、税金に関する事務作業を進めるうえでは、税金についての知識も必要です。正しく処理できないと不正な申告や脱税につながる恐れもあるため、しっかりと対応してください。
業務委託で働くことが向いている人

業務委託で働く人には、労働法が適用されません。労働法で守られない分、仕事の獲得から自己管理まで上手く立ち回る必要があります。ここでは、業務委託で働くことが向いている人の特徴を解説します。
実績やスキルがある人
業務委託契約は仕事を自分で見つけなくてはいけないため、委託元にアピールするための実力やスキルが求められます。ただ、「自分にはこれができる」というだけではなく、具体的に提示できる制作物が必要です。委託元が納得するレベルの専門性やクオリティの制作物を用意して、仕事を獲得しましょう。
自己管理を徹底できる人
業務委託で働くと労働法が適用されないため、自分で仕事のペースや健康を管理する必要があります。雇用契約で働く人は「法定労働時間」が労働時間の上限で、法定労働時間を超えて残業する際は「36協定」を守らなくてはいけません。
一方、業務委託の場合は、働き方を管理するのは自分自身です。働けば働くほど収入が増えるとはいえ、健康や仕事のクオリティをキープするためには自己管理を徹底しましょう。
また、請負契約の場合は、納期に間に合わせるためにも、スケジュール立てて仕事を進めるスキルが問われます。
変化に柔軟に対応できる人
業務委託には、変化が付きものです。業務委託契約書の内容にもよりますが、委託元の都合で、急に仕事がなくなる場合もあるでしょう。突然の出来事に対し、営業をかけよう、スキルアップのためインプットの時間を増やそうなどと、前向きに行動できる人は業務委託で働くことに向いています。
また、柔軟な対応を取るには、貯蓄する、ライフプラン・キャリアプランを立てておく、など日頃からの計画性も重要です。
企業側が業務委託で採用するメリット・デメリット

仕事を依頼する企業側にとって、業務委託にはメリットとデメリットの両方があります。委託側の事情を知っておくと、仕事を円滑に進められるでしょう。
企業側が業務委託で採用するメリット
業務委託を採用する側のメリットは以下のとおりです。
- 自社従業員がコア業務に集中できる
- ノウハウや知見がない業務を任せられる
ノンコア業務を委託する企業は、従業員をコア業務に集中させ、業務効率化やコスト削減を図りたいと考えています。
また、フリーランスのなかには専門性に長けた人が少なくありません。社内にノウハウや知見が乏しい分野を業務委託したい、と考えている企業も見られます。
企業側が業務委託で採用するデメリット
業務委託を採用する側のデメリットは以下のとおりです。
- 委託側が指示を出せない
- 高額な報酬が必要な場合もある
- 社内にノウハウがたまらない
業務委託契約には指揮命令権がないため、依頼した相手に指示が出せません。また、専門性が高い内容について業務委託すれば、支払う報酬も高くなります。
業務を任せきりにすると自社にノウハウがたまりません。そのため、定期的な報告会を設ける、レポートを提出してもらうなどして、ノウハウを取得しようと試みる委託元も見られます。
業務委託契約書の目的や種類・書き方

業務委託契約を結ぶ時は業務委託契約書を作成します。ここでは、業務委託契約書の目的とともに、種類や書き方について確認しましょう。
業務委託契約書を作成する目的
業務委託契約にあたって業務委託契約書を作成すれば、さまざまなトラブルの防止につながります。「いった」「いわない」といった認識のズレが生じなくなり、多少の問題が起きてもスムーズに解決しやすくなるでしょう。
業務委託契約書の目的を果たすためには、契約や業務内容に関するさまざまな項目について具体的に記載する必要があります。
業務委託契約書の種類
業務委託契約書は、契約のタイプに応じて以下の3種類に分かれています。
- 毎月定額型
- 成果報酬型
- 単発業務型
毎月定額型は、月ごとに一定額の報酬が発生する契約に使用します。成果報酬型は、実際の成果によって報酬額が変化する契約の際に作成する契約書です。単発業務型は、案件ごとに報酬が決まっている契約において使用します。
業務委託契約書を作成する際は、契約のタイプに適した種類を選択しましょう。
記載すべき項目例
すでに触れたとおり、業務委託契約書ではさまざまな項目をまとめる必要があります。記載すべき項目例をあげると、以下のとおりです。
- 業務内容
- 契約期間
- 受発注手続き
- 成果物の納品・検収方法
- 報酬の計算方法・支払方法・支払時期
- 秘密保持契約
- 禁止事項
- 損害賠償
- 契約解除の手続き
仕事の範囲や報酬が発生する条件などを業務委託契約書で定めておくと、実際に業務を始めてからも安心して取り組めます。秘密保持契約とは、業務委託する際に開示した機密情報を、第三者に漏らさないための取り決めです。秘密保持契約の内容次第では、業務を再委託できません。また、契約終了の際に、秘密情報の返還・破棄するよう求めるケースもあります。
禁止事項には、反社会的勢力の排除、再委託の禁止などがあります。問題が発生した場合に備え、損害賠償の金額や契約解除の手続きについても定めておきましょう。
業務委託契約書には収入印紙は必要?

請負契約では、業務委託契約書に契約金額に応じた収入印紙を貼り付けます。契約ごとに、収入印紙の必要性や使い方を見ていきましょう。
収入印紙とは?
そもそも収入印紙は、課税文書に添付し印紙税を納付する証票です。課税文書は発行時に印紙税が課される文書で、契約書以外にも約束手形または為替手形、保険証券などが挙げられます。
収入印紙は法務局や郵便局、金券ショップ、コンビニエンスストアなどで購入可能です。ただし、コンビニエンスストアでは取り扱う印紙の種類が少なめ。需要が高い「200円」以外の収入印紙を購入したい時は、ほかの購入場所でなければ手に入らない場合があります。
請負契約の場合
請負契約の業務委託契約書を作成する際は、契約金額に応じて収入印紙の貼り付けが必要です。課税文書の第2号文書は請負の契約書を表しており、物品加工注文請書や広告契約書などが含まれています。「国税庁」のサイトに公開されている、契約金額に対する収入印紙の税額を以下に示しました。
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 1万円未満のもの | 非課税 |
| 1万以上 100万円以下のもの | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 |
| 200万円を超え 300万円以のもの | 1,000円 |
| 300万円を超え 500万円以下のもの | 2,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下のもの | 1万円 |
| 1,000万を超え 5,000万円以下のもの | 2万円 |
| 5,000万を超え 1億円以下のもの | 6万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
継続的取引(請負)の場合
継続的に取引する場合の業務委託契約書は、第7号文書に該当します。第7号文書の収入印紙の金額は一律4,000円です。また、契約書に報酬の記載がある場合は第2号文書で、記載がない場合は第7号文書となります。
委任契約の場合
委任契約・準委任契約で交わされる契約書は非課税文書です。そのため、原則として収入印紙を貼る必要はありません。
電子契約書の場合
電子契約書の場合は、収入印紙が不要となります。印紙税は「紙の契約書を作成した時」に課せられるためです。また、コスト削減を目的に、紙の契約書から電子契約書に切り替える事例が増えています。
業務委託契約を結ぶ際の手順

業務委託契約を結ぶ時は、取引する企業と話し合いながら契約内容の詳細を決定する必要があります。業務委託契約を結ぶ際の具体的な手順は以下のとおりです。
- 業務内容のすり合わせ
- 条件の決定
- 業務委託契約書の作成
- 業務委託契約の締結
業務内容についてきちんとすり合わせておかないと、業務を開始してから認識のズレに気づく可能性があるため注意が必要です。双方が納得できる条件が定まったら業務委託契約書を作成します。業務委託契約書の内容を改めて確認し、問題がないかチェックしましょう。双方が業務委託契約書の内容に合意すると、正式に業務委託契約を締結できます。
業務委託契約を結ぶ際の注意点

業務委託契約は法律による規制を直接受けません。基本的には契約内容を自由に決められるため、使い勝手がよいといえるでしょう。
ただし、何らかの問題が起きた場合、契約内容や法律に対する理解が浅いせいで不利になっていることを把握できないケースもあるため、注意が必要です。ほかの法律に抵触していることに気づかず、違法な状態で働かされてしまう場合もあります。
業務委託契約を締結する際には、その内容が請負なのか、委任なのかなどをしっかりと確認し、条件内容を吟味して締結することが大切です。
業務委託契約を結んでいるつもりでも、実際は派遣に該当するケースもあります。このような状態は「偽装請負」とよばれており、注意が必要です。業務委託には労働法が適用されませんが、実質的に派遣として働いている場合は労働法の対象となります。
派遣であれば、労働法に基づいた労働条件を守らなければなりません。偽装請負に陥ると、労働法の対象であるにもかかわらず過酷な労働条件を強いられる恐れもあるため、気をつけましょう。
業務委託契約の内容変更・解除したい場合の手順

業務委託契約を結んだ後も、内容の変更や契約の解除が可能です。ここでは、業務委託契約の内容の変更や契約の解除の手順について、それぞれ説明します。
業務委託契約の内容を変更する手順
業務委託契約の内容を変更する場合、ゼロから業務委託契約書を作り直す必要はありません。変更する内容をまとめた変更契約書または覚書を作成して契約を締結し直せば、内容の変更が可能です。なお、変更契約書または覚書が課税文書に該当するなら、文書の種類や契約金額に応じた金額の収入印紙を貼り付ける必要があります。
契約を締結し直した後は、最初に作成した業務委託契約書とともに変更契約書または覚書を保管しましょう。
業務委託契約の解除の手順
業務委託契約を解除する際は、契約内容の確認や双方の合意が必要です。具体的な解除の手順は以下のとおりとなっています。
- 業務委託契約書を確認する
- 話し合う
- 解除合意書を作成する
なお、業務委託契約を途中で解除するケースについては、民法でも言及されています。委任契約を途中で解除する場合、損害賠償が請求される恐れがあるため注意が必要です。
また、請負契約を途中で解除する場合、報酬が支払われない可能性があります。
業務委託案件の探し方
業務委託案件の探し方について、以下の4つを紹介します。
- フリーランスエージェント
- マッチングサービス
- 求人サイト
- 人脈の活用
フリーランスエージェント
実績やスキルがあれば、フリーランスエージェントがおすすめです。フリーランスエージェントに登録すると、専門のスタッフにキャリアを相談でき、仕事を紹介してもらえます。

弊社「ITプロパートナーズ」は、IT系のフリーランスを対象としたエージェントです。エンド直案件が約9割で、高収入が期待できます。自社開発案件も多く、案件を通じてスキルアップも可能。リモート案件が7割で、週2~3日などフルタイム以外の案件も取り扱っているので、都合に合わせて仕事のペースを調整できます。
マッチングサービス
マッチングサービスは、クライアントとワーカーを結びつけるプラットフォームです。マッチングサービスには、クラウドソーシングも含まれます。クラウドソーシングの特徴は、案件のレベルが幅広いところです。未経験者でも受けられる案件も掲載されているので、実績づくりの場として利用するとよいでしょう。
求人サイト
求人サイトでも業務委託案件を探せます。検索機能で「業務委託」に絞って探しましょう。求人サイトでは多様な職種を探せます。また、エリア別でも案件を検索できるので、特に地方で仕事を探している人には求人サイトの利用がおすすめです。
人脈の活用
過去のクライアントから仕事をもらう、前職の勤め先から仕事を回してもらうなど、業務委託で働く人の多くは人脈から仕事を得ています。仕事を途切れさせないためには、1つひとつの仕事を丁寧にこなし、また依頼したいと思わせることが重要です。
新しい出会いが仕事につながる場合もあるため、日頃から交流会やコミュニティに参加しておくとよいでしょう。
業務委託契約に関するよくある質問
業務委託契約で受注した仕事に取り組むうえでは、税金にも注意しなければなりません。ここでは、業務委託契約の税金面について多くの人が疑問に思うポイントについて解説します。業務委託契約書作成に使えるテンプレートや、2023年10月から開始されたインボイス制度の業務委託への影響も見ていきましょう。
業務委託契約で源泉徴収はされる?
個人が業務委託契約により報酬を受け取る場合、源泉徴収が行われます。源泉徴収の対象になるのは、原稿料や講演料などです。納めるべき所得税以上に源泉徴収が行われていれば、確定申告により還付の申請ができます。払いすぎた税金が戻ってくるため、忘れずに確定申告の手続きをしましょう。
業務委託契約で確定申告は必要?
フリーランスとして業務委託契約の仕事をしていて一定以上の所得がある人は、確定申告や納税が必要です。具体的には、年間の所得金額が48万円を超えている場合に確定申告する必要があります。
なお、所得とは、業務委託契約の報酬として受け取った収入から経費を差し引いた残りの金額です。収入が48万円を超えていても、経費を差し引いた所得が48万円以下なら確定申告は必要ありません。
業務委託契約書のテンプレートはどこで入手できる?
業務委託契約書のテンプレートは、オンラインで入手できます。テンプレートや記載すべき項目については、こちらの記事も参考にしてください。
インボイス制度による業務委託の影響は?
インボイス制度は、適格請求書(インボイス)にもとづいて消費税の仕入税額控除額を計算する制度です。
業務委託で働く人は、クライアントから適格請求書の発行を求められる場合がありますが、適格請求書を発行できる人は消費税の納税義務がある課税事業者のみ。免税事業者のままでは適格請求書を発行できないため、取引に影響する恐れがあります。
まとめ
業務委託で仕事を受ければ自由度が高く、努力次第で高収入も目指せます。ただし、自己責任となる部分も多いため、スキルや実績を積んでしっかり準備したうえで取り組んだほうが安心です。
業務委託契約を結ぶ際は、トラブルを避けるためにさまざまな項目を盛り込む必要があります。万が一の場合に備え、適切な業務委託契約書を作成しましょう。また、業務委託の契約締結や内容の変更は、いずれも取引する相手とよく話し合って進める必要があります。
今回説明したポイントや注意点を押さえ、エージェントなどを活用して業務委託の案件を探しましょう。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)