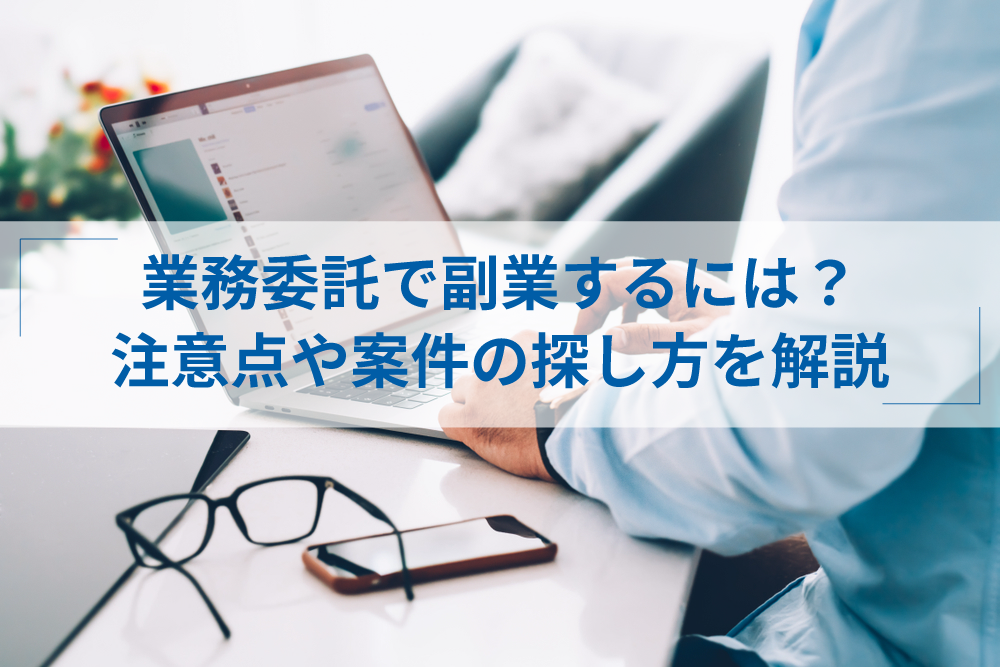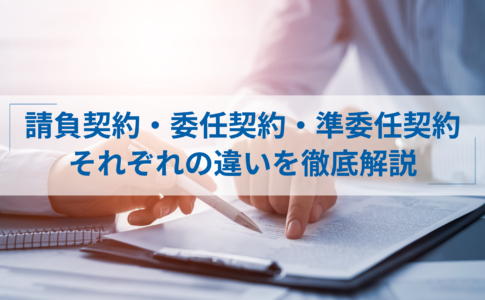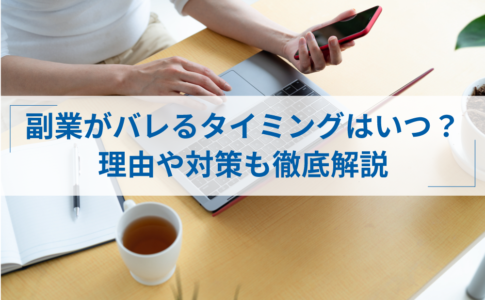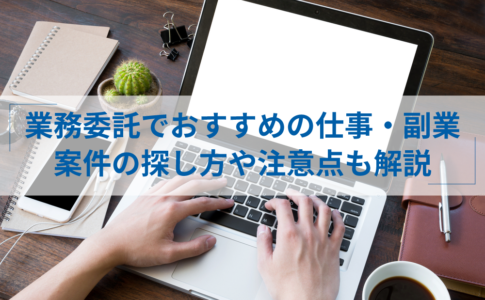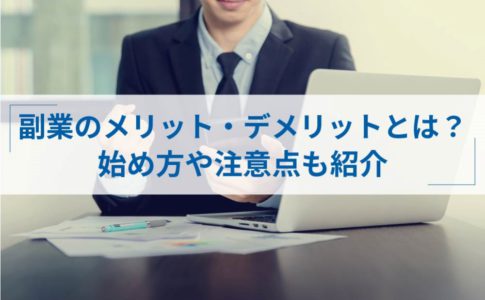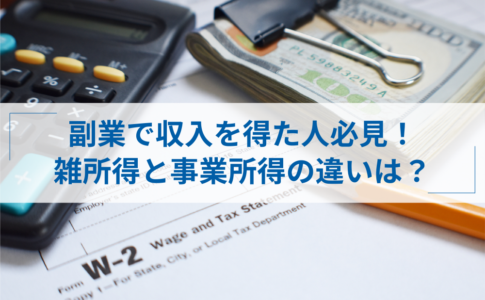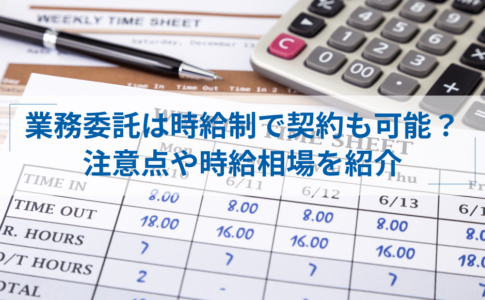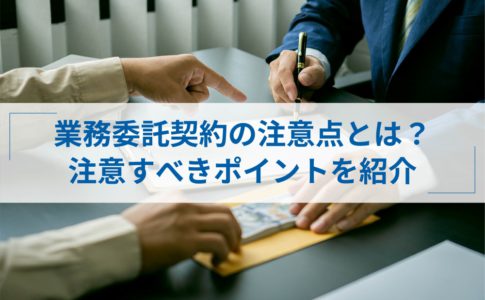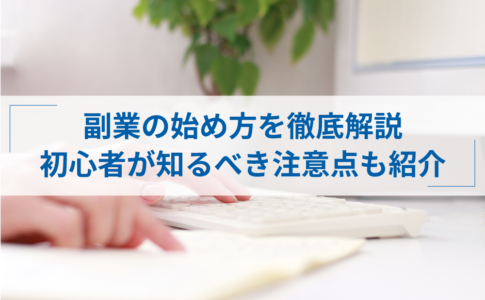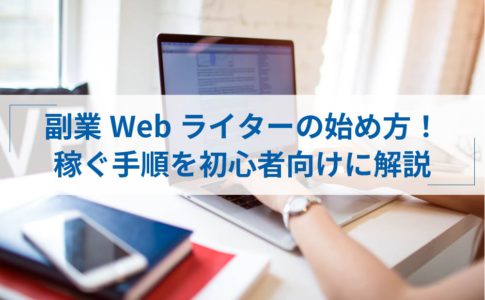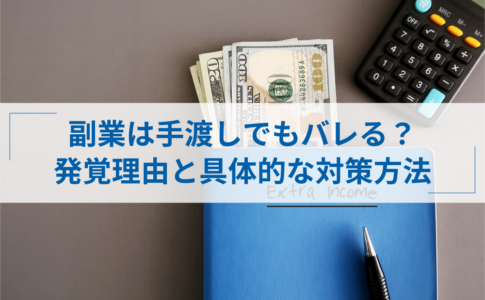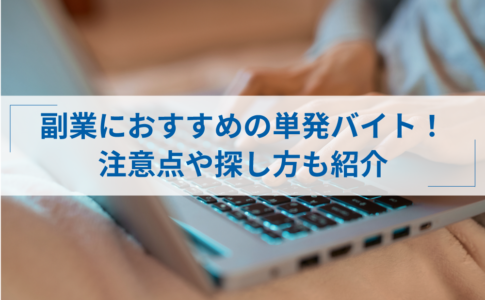こんにちは、ITプロマガジンです。
「業務委託契約で働けば、本業の会社に副業がバレないだろう」と思っている人もいるかもしれません。しかし、業務委託でも副業が会社にバレる可能性は十分にあるので注意が必要です。
本記事では、業務委託契約の副業が本業の会社にバレる理由や、副業と見なされずに収入を得る方法などを解説します。業務委託契約で副業するメリットやデメリット、必要な準備や注意点も紹介するので参考にしてください。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
そもそも業務委託契約とは

「業務委託契約」とは、特定の団体や企業に属することなく、成果物や役務と引き換えに報酬を得る契約方法です。そのため、特定の団体や企業に属し、雇用契約を結ぶ正社員やアルバイト・パートとは立場が大きく異なります。
例えば請負型の業務委託契約の場合、納期までに成果物を納品すればよいので、仕事の方法に関して指示されることはありません。ただし、雇用契約を結ぶ正社員などとは異なり、労災保険などの社会保険が適用されないので注意が必要です。
業務委託の契約方法は、請負契約、委任契約、準委任契約に分かれています。請負契約は、仕事の完成を条件とし、仕事の結果に対して報酬を支払うという契約です。例えば、デザイナーやエンジニアに成果物の納品を依頼する場合、請負契約が結ばれます。成果物を制作して期日までに納品し、クライアントが内容を確認して問題なければ報酬が支払われます。
委任契約は、法律行為の遂行を相手に委託し、相手が承諾すると効力が発生したとみなす契約です。例えば、弁護士に法律行為の代理を依頼する場合は委任契約が締結されます。契約内容は法律行為に限定されるため、業務委託で委任契約を結ぶのは主に弁護士、行政書士、公認会計士などです。
また、準委任契約は、法律行為以外の業務を相手に委託するための契約です。例えば、商品の宣伝、セミナーでの講演、調査などさまざまな業務を委託するために準委任契約が行われています。法律行為以外の全ての業務が対象になるので、幅広い業務について準委任契約が行われています。
業務委託契約で副業する際の働き方
近年は、業務委託契約で副業をしている人も増えています。例えば、普段は会社員のSEとして働いている人が自分のスキルを生かし、「副業としてプログラミングの案件」を業務委託契約で受注するケースがあります。また、収入を安定させる目的により、フリーランスのWebデザイナーが委託ドライバーの仕事の業務委託契約を結ぶパターンもあるでしょう。
いずれにせよ、副業は本業のサブとして取り組む仕事です。会社員、パート、アルバイト、派遣社員、フリーランス、自営業の人が2つの仕事を持つ場合、どちらが本業でどちらが副業かは、本人の意思や業務時間、収入によって決まるのが一般的です。
業務委託での副業をする人が増えている理由
副業をする人と副業人材を活用する企業の両方が増えており、業務委託契約で副業に取り組む人が増えています。「パーソルキャリア プロフェッショナル人材の活用総合サービス「HiPro」調べ」によると、2022年度に副業人材の活用を始めた企業は前年度と比べて123%も増加しました。そのうち62.8%の企業で活用する人数が増加傾向にあります。
また、株式会社リクルートが2022年に実施した「兼業・副業に関する動向調査データ集2022」によると、正社員で兼業・副業に取り組んでいる人の割合は9.9%でした。また、過去に兼業・副業の経験があって今後再開する意向がある人の割合は5.3%、過去に兼業・副業の経験がなく、これから始める意向がある人の割合は41.1%です。副業への取り組みを前向きに捉えている人は半数以上となっており、多くの人が興味をもっていると分かります。
副業が広がる背景には、案件獲得のためのプラットフォームの増加によって副業に取り組みやすい環境が整っていることもあげられます。また、終身雇用の終焉や副業解禁により、業務委託の活用が今後ますます加速するという意見も多い状況です。業務委託での副業をする人は、さらに増えると考えられるでしょう。
業務委託なら副業は可能?
業務委託で副業ができるか否かは、本業として働いている企業の就業規則によります。
法律上、雇用主である企業は従業員の副業を禁止できません。よって、業務委託などの契約方法を問わず、原則として従業員は副業を自由に行えます。
しかし、本業に大きな支障が出る場合や長時間労働を防ぐ場合など合理的な理由があると、雇用主が従業員の副業を禁止することも可能です。「競合他社での副業禁止」など、限定的に副業を禁止している会社もあります。
副業が会社にバレると、会社から減給や降格などの処分をいい渡されかねません。副業する前に就業規則をよく確認してください。具体的な処分については、会社ごとに異なります。
ちなみに、公務員は国家公務員法や地方公務員法によって副業が原則禁止されているため、一部例外地域を除き、業務委託契約でも副業はできません。
業務委託の副業は会社にバレる?バレない?

たとえ隠れて業務委託で副業しても、バレる可能性は十分にあります。バレる理由は主に、「住民税金額の相違」「関係者からの通報」の2つです。
住民税金額の相違
業務委託の副業がバレる理由のひとつが、住民税金額の相違です。副業で収入が増えれば支払う住民税が増えるため、給与以外にも収入があることが企業側に伝わる可能性があります。
副業収入に課される住民税の徴収方法は、普通徴収と特別徴収の2つ。特別徴収を選択すると、増加した住民税は会社経由で支払われるため、会社に副業の存在が推測される可能性があります。一方、普通徴収を選択すれば住民税の納付書が自宅に送られてくるので、住民税が理由で副業がバレる可能性は減ります。
関係者からの通報
関係者からの通報によって、副業がバレることもあります。
会社の飲み会や何気ない雑談のなかで、うっかり副業について触れてしまう人は少なくありません。「最近忙しい」「休日も働いている」といった何気ない発言が、周囲の好奇心を刺激することもあるでしょう。その結果、副業をしている事実が発覚し、人伝いに企業側へ伝わるかもしれません。
本業と同じ業界で副業を行う際は、クライアントが偶然漏らした内容がきっかけで、副業をしていると本業の会社にバレてしまう可能性もあります。
結局どんな人が業務委託で副業できる?
ここまでの話をまとめると、業務委託で副業できるのは以下のパターンです。
- 就業規則で副業が禁止されていない企業に属している
- フリーランスや自営業で働いている
就業規則で副業が禁止されていない企業に属している
公務員は、原則として国家公務員法第103条・104条、地方公務員法第38条にて副業が禁止されています。
また、民間企業に務める会社員の場合は、各社の就業規則によって対応が異なるため注意しましょう。民間企業で副業を行うには、就業規則で副業が禁止されておらず、本業に支障が出ないことが条件です。
近年では、就業規則を守ることを前提として、「副業フリーランス」を始める人も増えています。
フリーランスや自営業で働いている
自営業やフリーランスとして働いている人は、既存のクライアントとほかの仕事について取り決めがない限り、自由に副業ができます。むしろ、複数の仕事を掛け持ちした方が収入が途絶えるリスクを防げるでしょう。
ただし、掛け持ちする仕事が増えるほど、仕事の管理が煩雑になり、メインの仕事と副業の繁忙期が重なると激務になる恐れがあります。タスク管理ツールやスケジューリングアプリを活用しつつ、無理のない働き方を検討するとよいでしょう。
業務委託以外の副業で会社にバレない方法はある?

一時的な収入であれば、副業とみなさない企業は多いものです。一時的な収入には、株式投資などの資産運用の成果や、フリマアプリを利用した不用品の売却益、ポイントサイトで得た収入などがあります。バレるかどうかなどを気にせず安心して副収入を得たい場合は、参考までに覚えておくとよいでしょう。
会社の就業規則によって解釈が異なる可能性もあるため、心配であれば就業規則を確認してみてください。
業務委託契約で副業するメリット
業務委託契約は、会社と雇用契約を結ぶわけではないため、ストレスフリーな人間関係などさまざまなメリットがあります。ここでは、業務委託契約で副業をするメリットを、3つのトピックに分けて解説します。
在宅での勤務も可能
働き方の自由度の高さは、業務委託契約で副業をする大きなメリットです。業務委託契約には、大きく分けて「委任契約/準委任契約」と「請負契約」の2種類があります。
請負契約の場合、労働時間や働く場所は自由なので、オンラインで完結する仕事であればリモート・在宅勤務も可能です。委任契約や準委任契約であっても、クライアントとの交渉次第では自由に働けます。
仕事を選びやすい
仕事を選びやすいのも重要です。雇用契約を結ぶ場合、会社の指揮下に入るため、与えられた仕事を与えられた条件でこなさなければなりません。しかし業務委託契約の副業は、ある程度仕事を自分で選択できます。
そのため、自分が得意な分野に注力でき、「割に合わない仕事・無理な仕事を受けない」という選択もできます。
人間関係のストレスが少ない
雇用契約を結ぶ場合、その企業の一員として働くため、濃密な人間関係が発生しやすいものです。同僚や上司とのコミュニケーションなど、人間関係のストレスを抱える方も多いでしょう。
業務委託契約で副業する場合、あくまでクライアントと対等の立場で業務を進めるため、人間関係のストレスがほとんどありません。業務内容によっては、クライアントとほとんど会話をしない案件もあります。
業務委託契約で副業するデメリット

業務委託契約は、雇用契約とは異なり、労働基準法で守られることはありません。また雇用保険や労災保険などの社会保険も適用されないため、万が一事故やケガなどのトラブルが起こったとしても、必要な手当が受けられません。
業務委託契約による副業は、本業とは異なる収入なので、自分で納税申告・納税をする必要もあります。ここでは、業務委託契約で副業するデメリットを解説します。
労働者基準法で守られない
業務委託契約で副業をする場合、労働基準法で守られないため注意しましょう。労働基準法が適用されるのは、雇用関係にある労働者(正社員やパート・アルバイト、派遣など)です。業務委託契約で副業する際は、「実質的な労働者」と認められるのは難しいでしょう。
例えば「1万円の案件を何十時間もかけてこなした」という場合でも、時間外労働の割増賃金は発生しません。労働時間の上限も存在しないため、「自分で自分の身を守る意識」が重要になります。
社会保険が適用されない
記事の序盤でも少し触れましたが、社会保険が適用されないデメリットもあります。業務委託契約の場合、「厚生年金」「雇用保険」「労災保険」のような社会保険は、適用対象外となります。
厚生年金が天引きされないため、メリットと考える人も多いですが、保険料の支払いが少なければ「将来もらえる年金額」も当然少なくなります。また労災保険が適用されないため、業務中に万が一のことが起こっても、保険が支払われないので注意しましょう。
税務申告・納税を自身で行う必要がある
本業以外で副業を行う場合、税務申告や納税を自身で行う必要があります。雇用契約を結んでいる場合、会社側が源泉徴収をし、納税をしてくれます。しかし業務委託契約で仕事をした際は、確定申告や納税を自分で済ませなければなりません。
確定申告は、自分の所得を申告し、支払う税額を確定させる作業です。副業によって得た所得は、本業の勤務先とは一切関係ないため、自分で処理をする必要があります。確定申告などの手続きは、後に詳しく解説します。
業務委託契約の副業案件の探し方
業務委託契約の副業案件は、いくつかの方法で検索できます。ここでは、「求人サイト」「クラウドソーシング」「スキルシェア」「エージェント」の4つを紹介します。
求人情報サイト
求人情報サイトは、「Indeed」や「Googleしごと検索」など、求人の情報が並べられているサイトです。自分で求人を選択し、そこに応募します。求人サイトのメリットは、自分のペースで求職活動ができ、なおかつ企業選びの自由度が高い点です。
ただしエージェントとは異なり、応募先を自分で選ばなければならないというデメリットもあります。求人情報サイトに向いている人は、以下の通りです。
- 本業が忙しく自分のペースで案件を探したい人
- さまざまな業界や企業を見てみたい人
クラウドソーシング
クラウドソーシングは、インターネット上で企業が不特定多数のワーカーに仕事を発注できるサービスです。企業側は人材の採用コストが抑えられ、受注側も自分の好きなタイミングで働けるため、両者にとってWin-Winな業務形態となっています。
クラウドソーシングを利用するメリットは、何といっても気軽に案件を探せる点です。ただし、報酬を支払わずに行方をくらますなど、一定数の悪徳クライアントが存在するデメリットもあります。クラウドソーシングに向いている人は、以下の通りです。
- とりあえず手軽に案件を受けてみたい人
- スキマ時間に働きたい人
おすすめのクラウドソーシングサイトは以下の記事で紹介しています。
スキルシェアサイト
スキルシェアサイトとは、自分のスキルを商品として提供するサービスです。クラウドソーシングや求人サイトは基本的には依頼先を探すクライアント側が募集を掲載します。一方で、スキルシェアサイトでは、仕事が欲しい人側が自分のスキルや経歴、実績を公開して、応募を待ちます。
プログラミングやWebライティング、Webマーケティング、動画編集、各種コンサルはもちろん、講師や家事代行といった個人・企業のニーズを満たす幅広いスキルが出品できます。自分の価格を自分で設定できる点も魅力といえるでしょう。
下記のような人は、スキルシェアサイトの利用が向いています。
- アピールとなる特定分野の知識やスキル、実績がある人
- 介護や看護・家事などそのほかのサイトで案件が少ない分野で副業したい人
人気のスキルシェアサイトは下記の記事で紹介しています。
副業エージェント
エージェントは、応募先の選択などを代行し、面談を通じてサポートをしてくれます。求人サイトに比べて応募先企業の情報が詳しく、通常では公開されていない求人を紹介してもらえる可能性もあります。
スタッフとの相性などいくつかの注意点はありますが、最近ではエージェントの種類も増えており、自分に合ったサービスを選択できる環境が整っています。エージェントに向いている人は、以下の通りです。
- 自分のスキルや経験を最大限に活かしたい
- 質の高い案件を受けたい
「ITプロパートナーズ」は、エンド直の高単価な案件が全体の9割を占めるフリーランスエージェント。週2~3の案件など副業向けの案件も豊富に取り扱っています。掲載中の案件には自社開発のものも多く、仕事を通じたスキルアップが可能です。案件の7割がリモート案件な点も、副業案件獲得におすすめといえます。
業務委託契約で副業する際に必要な準備と確定申告について

業務委託契約で副業する際は、収入によって確定申告が必要になります。会社で年末調整をしてもらっている人でも、一定の副業収入があれば自分で確定申告しなければいけません。以下を参考に、確定申告の必要性と準備・手続きについて確認しましょう。
確定申告が必要になるケースとは
本業以外で年間20万円を超える所得がある場合、所得税の確定申告が求められます。確定申告とは、1年間の所得に応じて、納めるべき税額を確定させる手続きのことです。
副業に関連する経費がある際は、総収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。経費を漏れなく計上するほど、節税できる仕組みです。業務関連の経費になり得るものは、細かくレシートや領収書などを保存しておきましょう。
白色申告と青色申告の違い
確定申告には、白色申告と青色申告の2つの方式があります。白色申告は、青色申告の申請をしていない個人事業主が行う基本的な申告方式です。白色申告のメリットは、手続きが比較的シンプルなところです。
一方、青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得がある個人事業主が対象となる申告方式です。青色申告制度を活用するためには、適用年の3月15日までに、開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出することが必須条件となります。
青色申告のメリットは、最大65万円の特別控除や、赤字を3年間繰り越せる制度などに見られるように、節税効果が高いところです。
確定申告・税額調整を行う
確定申告書の提出は、基本的に申告する分の翌年の、2月16日から3月15日までの間に行います。
確定申告で提出が必要な書類や情報は以下のとおりです。
- 確定申告書:国税庁の公式サイトや税務署などで入手可能
- 本人確認書類:マイナンバーカードなど
- 所得金額が分かる書類
- 各種控除申請に必要な書類
- 還付金の振り込みなどに使われる銀行口座の番号
確定申告をしないと、ペナルティが発生します。期限後に申告すると、加算税や延滞税を支払わねばなりません。意図的に所得を隠そうとしたと見なされると、重加算税が課される場合もあります。
業務委託契約で副業する際のそのほかの注意点
最後は業務委託契約を結んで副業をする時の注意点をまとめて確認しておきましょう。
稼働時間や稼働方法などを細かく確認する
業務委託には、成果物を納品して報酬が発生する契約(請負契約)と指定の稼働時間業務を遂行すること報酬が発生する委任契約・準委任契約と2種類あります。委任契約・準委任契約の場合、稼働時間や稼働方法が決められているため、細かく確認が必要です。
また、担当すべき業務範囲や報告のタイミング・方法、必要経費の清算方法についても把握しておかなければなりません。
適正な単価・条件かどうかチェックする
業務委託で仕事をする時によくあるトラブルが、報酬と仕事内容が合わないというケースです。そのため、単価や条件が適正であるかも確認が必要です。
特に、成果物を納品する請負契約の場合、成果物の完成基準や修正時のルールなどを細かく確認しておかなければ、たとえ案件単価は高くても金額に見合わない仕事量になってしまうことがあります。単価を確認する時は、そのほかの条件と照らし合わせて、適正かどうかを判断しましょう。
業務委託契約書を取り交わす
万が一にもトラブルが発生した場合、いった・いわないで揉めることが多いため、業務委託契約書を取り交わしておきましょう。法律上、口頭やチャット、メールでも契約は成立しますが、後から契約内容が確認できなければ、立場が不利になる可能性があります。正式に委託者と受託者が契約内容に合意していることが証明できるよう、業務委託契約書を作成してください。
契約書には業務範囲や契約の条件をできるだけ細かく記載し、トラブル時に確認できるようにしておくと安心です。
スケジュール管理・体調管理を徹底する
本業とは別の副業に取り組むうえでは、スケジュールや体調をしっかり管理する必要があります。案件を詰め込みすぎるとスケジュールに余裕がなくなり、心身を休める時間が取れなくなる場合もあるでしょう。十分な休息を取れないと、体調を崩す原因になります。体調を崩せば本業のパフォーマンスにも影響する恐れがあるため、注意が必要です。副業の期日を守れなければクライアントからの信用を失う原因にもなるので、余裕をもって予定を立てることが大切です。
インボイス制度への理解を深めておく
業務委託契約で副業に取り組む人は、インボイス制度にも注意する必要があります。インボイス制度とは、消費税を適切に計算して納税するために導入された新しい制度です。
消費税の仕入税額控除を受けるためには、要件を備えたインボイス(適格請求書)が必要です。仕入税額控除とは、売上の消費税額から自社の仕入れの際にかかった消費税額を差し引いて消費税を計算する方法を表しています。
インボイス制度施行後の現在、副業するにあたって以下の状況を理解しておきましょう。
- 免税事業者は案件の受注が困難になる可能性がある
- 課税事業者になると、税金や事務の負担が増える
免税事業者は適格請求書を発行できないため、クライアントが仕入税額控除を利用したい場合、契約されにくくなる可能性があります。副業者には免税事業者が多いかもしれませんが、今後も副業を続けるなら、免税事業者のままでいるか課税事業者になるか検討すべきです。
なお、課税事業者になれば適格請求書は発行できますが、消費税の申告・納税義務が生じ、税務や事務作業の負担が増加します。
課税事業者になるかどうかについてはさまざまな負担を考慮し、総合的に判断する必要があるでしょう。
まとめ
ここまで業務委託の副業について見てきました。業務委託契約で働く場合、特定の企業や団体に属さないため、雇用契約とは多くの違いがあります。今回の記事で解説した、メリット・デメリットを理解したうえで、業務委託契約の副業を探すとよいでしょう。
業務委託契約の副業案件を探す方法としては、求人サイトやクラウドソーシング、エージェントなどがあります。高単価で働きやすい案件を探している方は、「ITプロパートナーズ」をぜひご利用ください。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)