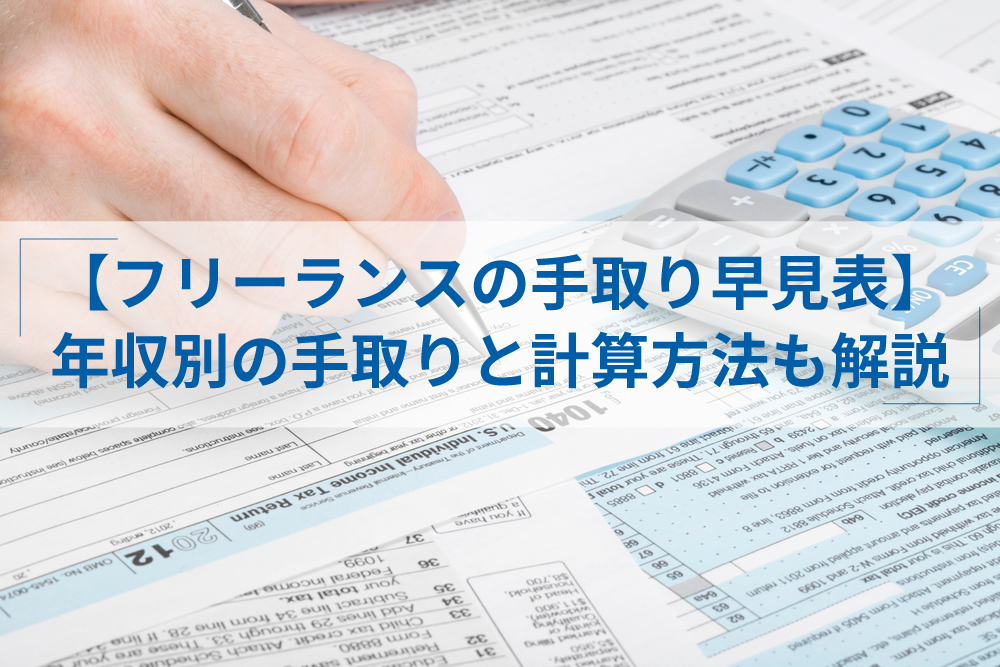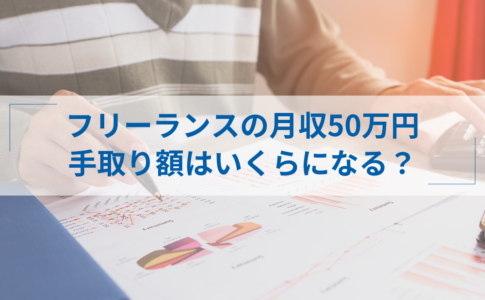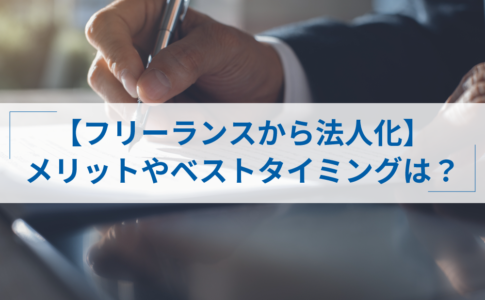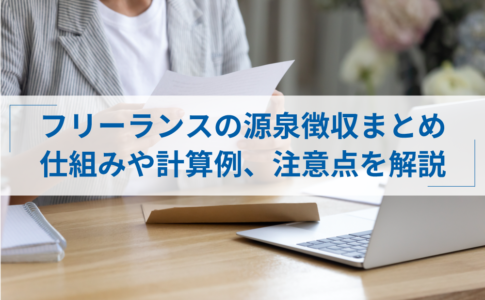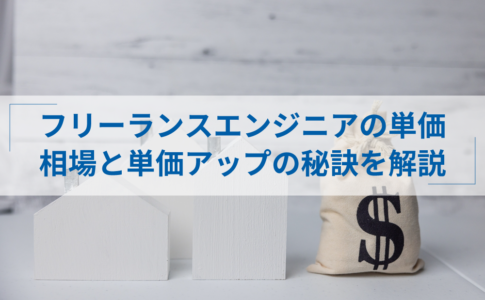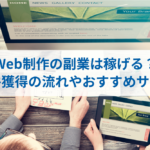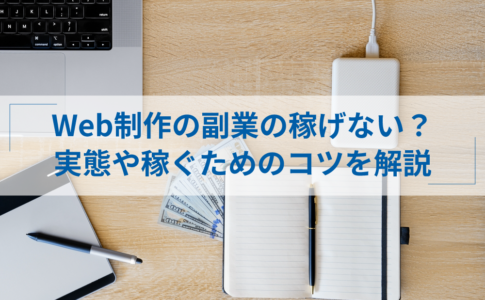こんにちは、ITプロマガジンです。
フリーランス(個人事業)として独立を検討している人にとって、「年収に対して手取りがいくらになるのか?」は気になるポイントかと思います。フリーランスと会社員では税金や保険料の計算方法、経費の考え方も違うので、手取り額にも差が出ます。
実際、フリーランスは年収に対して手元に残るお金はおよそ6〜7割程度になることが多い傾向です。しかし、これも人によってまちまちなので、一概には言えません。
そこでこの記事では、フリーランス(個人事業)の手取り額シュミレーションを年収・月収ごとに早見表形式で紹介します。税金の計算方法やできる限り手取り額を増やす方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
フリーランスの手取り早見表
フリーランスの手取りを年収別に示した早見表は、次の通りです。
| 年収 | 手取り |
|---|---|
| 300万円 | 約180万円 |
| 400万円 | 約240万円 |
| 500万円 | 約300万円 |
| 600万円 | 約360万円 |
| 700万円 | 約420万円 |
| 800万円 | 約480万円 |
| 900万円 | 約540万円 |
| 1,000万円 | 約600万円 |
手取り早見表を見ると、収入に対する手取り金額の割合は、だいたい60%になっていることが分かるでしょう。
上記の内容はこのあと紹介する「フリーランスの手取り金額の計算例・内訳」で設定した条件に基づいて計算したものです。経費や年齢、扶養人数などが違う場合は上記よりも手取りが多くなったり少なくなったりするので、あくまでも目安程度として考えてください。
フリーランスの手取り計算方法と税金・保険料
上で挙げた表を見ても分かる通り、手取り金額の基本的な計算方法は「売上-経費-(社会保険料+税金)」です。
手取り金額を計算する際に売上から差し引く経費、社会保険料、税金の種類は主に以下の通りです。
| 所得税 | 所得に対して課される税金 |
|---|---|
| 経費 | 事業を運営するために必要だった費用 |
| 所得税 | 所得に対して課される税金 |
| 復興特別所得税 | 所得税額に対する付加税 |
| 個人事業税 | 法定業種に該当する個人事業主に課される税金 |
| 消費税 | 課税事業者に対して課される税金 |
| 住民税 | 市町村民税と道府県民税(都民税)を合わせたもの |
| 国民健康保険料 | 会社に属さず働く自営業者などを対象とした健康保険料 |
| 国民健康保険料 | 厚生年金に入らず国民年金に加入する人が支払う年金保険料 |
各税金や保険料の金額は年収や年齢など個人的要素によって決まることが多いです。また、支払い方や支払い時期は費目によって異なるため、手取り金額を知るためだけでなく各費目の支払いを着実に行うためにも確認しておく必要があります。
各項目について詳しく解説していきましょう。
経費
経費は、事業を運営するために必要になった金額のことです。
設備や備品に投資した金額、業務上必要になった交通費、取引先への接待費、事業所の家賃などさまざまなものが含まれます。自宅で仕事をする場合は、自宅の家賃や電気代のうち仕事のために使った分を「家事按分」として経費に計上することも可能です。
国民健康保険料や国民年金保険料のような個人の保険料、健康診断の費用などは経費に入れることはできませんが、公的保険料・生命保険料は控除対象となります。
所得税
所得税とは、所得金額に対して課される税金です。
所得金額が上がるほど税率が高くなる累進制が採用されており、最低5%、最高45%となっています。
なお所得税額を計算する際は、税率ごとに定められた税金の控除額を活用すると便利です。例えば所得金額が700万円の場合、所得税率は23%、控除額は63万6,000円です。よって所得税は「700万円×23%-63万6,000円」で97万4,000円と簡単に計算できます。
復興特別所得税
復興特別所得税とは所得税に付加される税金で、2013年1月1日~2037年12月31日まで課されます。税率は2.1%で、所得税額に対して2.1%を乗じた金額が納付すべき税額となります。この税金は東日本大震災の復興のために使われます。
通常の所得税と一緒に納付することになっており、源泉徴収のない個人事業主の場合は確定申告後に所得税と合わせて納めます。
個人事業税
個人事業税は、法定業種に該当する個人事業主に課される税金です。
法定業種には次のものが含まれます。
- 物品販売業・製造業など37業種
- 畜産業・水産業・薪炭製造業
- 医業・弁護士業など30業種
税率は業種によって違い、3%、4%、5%のいずれかとなります。なお、農業・林業・鉱物採掘事業は個人事業税の対象外です。
消費税
消費税は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税事業者に課される税金です。課税売上高が1,000万円を超えた年ではなく、その翌々年に課されます。
課税売上が1,000万円以下の場合は免税事業者となるので消費税はかかりません。2023年10月からはインボイス制度が導入され、適格請求書の発行有無に応じて、クライアント側が仕入税額控除を適用できるかどうかが変わります。
住民税
住民税は、市町村民税と道府県民税(都民税)を合わせた税金です。
税額は所得に対して税率をかける所得割と所得に関係なく設定されている均等割からなります。
所得割の税率は自治体によって違うこともありますが基本的には10%です。均等割の金額は自治体によって異なり、数千円程度に設定されていることが一般的でしょう。
個人事業主の場合は自治体から届く納付書を使い、コンビニエンスストアの窓口やインターネットバンキングなどで納付します。フリーランスが支払う税金については、以下の記事で更に詳しく解説しています。
国民健康保険料
国民健康保険料は、国民健康保険に加入する人が支払う保険料です。
個人事業主は会社員のように会社の健康保険組合には加入していないため、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険料の金額は前年の所得などをもとに決められますが、具体的な算出方法は都道府県によって違います。所得は変わっていなくても、住む都道府県が変わることで国民健康保険料が変わることもあるので注意しましょう。
国民年金保険料
国民年金保険料は、厚生年金に加入していない個人事業主などが支払う保険料です。国民年金保険料を適切に支払うことで、将来老齢基礎年金を受け取れます。
国民年金保険料の金額は所得金額に関係なく一律ですが、定期的に金額が見直されます。前年とは違う金額が国民年金保険料として請求されることもあるので、よく確認しましょう。
【年収/月収別】フリーランスの手取りシミュレーション
ここからは、年収300万~1,000万円それぞれのケースごとに、フリーランスの手取り金額の計算例・内訳を見ていきましょう。
- 年収300万円/月収25万円のフリーランスの手取り
- 年収400万円/月収33万円のフリーランスの手取り
- 年収500万円/月収41万円のフリーランスの手取り
- 年収600万円/月収50万円のフリーランスの手取り
- 年収700万円/月収58万円のフリーランスの手取り
- 年収800万円/月収66万円のフリーランスの手取り
- 年収900万円/月収75万円のフリーランスの手取り
- 年収1000万円/月収83万円のフリーランスの手取り
なお、国民健康保険料は年齢や世帯加入者の人数によって変わります。経費の金額も個人差がありますが、ここでは(39歳未満の1人世帯、経費は収入の10%)で計算しています。また、ここで示す金額は100円以下の四捨五入したものです。
年収300万円/月収25万円のフリーランスの手取り
| 項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 収入 | 25万円 | 300万円 |
| △経費 | 2万5,000円 | 30万円 |
| △国民年金 | 1万6,000円 | 19万2,000円 |
| △国民健康保険 | 3万6,000円 | 43万5,000円 |
| 控除後の所得金額 | 17万3,000円 | 207万3,000円 |
| △所得税 | 9,000円 | 11万円 |
| △住民税 | 1万7,000円 | 20万7,000円 |
| 差し引かれる金額の合計 | 10万3,000円 | 124万4,000円 |
| 手取り金額 | 14万7,000円 | 175万6,000円 |
年収300万円・月収25万円の手取り金額は、年175万6,000円、月14万7,000円です。各種保険料や税金で収入の約4割が差し引かれることが分かります。
なお、収入から各種保険料や経費を差し引き、基礎控除、青色申告控除を適用した所得金額は207万3,000円です。よって、所得税は税率10%をかけた金額から控除額である9万7,500円を引いた金額となります。
ここでは青色申告をしたケースを想定していますが、白色申告した場合は控除額が減るため所得金額が多くなり、所得税額が増えることになります。
年収400万円/月収33万円のフリーランスの手取り
| 項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 収入 | 33万3,000円 | 400万円 |
| △経費 | 3万3,000円 | 40万円 |
| △国民年金 | 1万6,000円 | 19万2,000円 |
| △国民健康保険 | 4万2,000円 | 50万円 |
| 控除後の所得金額 | 24万2,000円 | 290万8,000円 |
| △所得税 | 1万6,000円 | 19万3,000円 |
| △住民税 | 2万4,000円 | 29万1,000円 |
| 差し引かれる金額の合計 | 13万1,000円 | 157万6,000円 |
| 手取り金額 | 20万2,000円 | 242万4,000円 |
年収400万円・月収33万3,000円の手取り金額は、年242万4,000円、月20万2,000円です。所得税の課税対象となる所得金額は290万8,000円なので、年収300万円の場合と同様に所得税率は10%になります。
所得金額に対する手取り金額の割合は約60%です。年収300万円の場合は約59%だったので、手元に残る割合は若干増えることが分かります。
なお、国民年金保険料は収入に関係なく一律なので、年収400万円でも年収300万円の時と変わりません。
年収500万円/月収41万円のフリーランスの手取り
| 項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 収入 | 41万7,000円 | 500万円 |
| △経費 | 4万2,000円 | 50万円 |
| △国民年金 | 1万6,000円 | 19万2,000円 |
| △国民健康保険 | 4万7,000円 | 56万4,000円 |
| 控除後の所得金額 | 31万2,000円 | 374万4,000円 |
| △所得税 | 2万7,000円 | 32万1,000円 |
| △住民税 | 3万1,000円 | 37万4,000円 |
| 差し引かれる金額の合計 | 16万3,000円 | 195万1,000円 |
| 手取り金額 | 25万4,000円 | 304万9,000円 |
年収500万円・月収41万7,000円の手取り金額は、年304万9,000円、月25万4,000円です。
所得税率は330万円から20%になります。よって、各種控除後の所得金額が374万4,000円であるこの場合は、所得に20%をかけ、そこから控除額である42万7,500円を差し引いた金額を所得税として納付しなければなりません。
収入に対する手取り金額の割合は約61%と、年収300万円、400万円の場合より多くなっています。しかし、白色申告だと控除が減り手取り金額が少なくなってしまうため、青色申告で青色申告特別控除を適用したいところです。
年収600万円/月収50万円のフリーランスの手取り
| 項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 収入 | 50万円 | 600万円 |
| △経費 | 5万円 | 60万円 |
| △国民年金 | 1万6,000円 | 19万2,000円 |
| △国民健康保険 | 5万2,000円 | 62万9,000円 |
| 控除後の所得金額 | 38万2,000円 | 457万9,000円 |
| △所得税 | 4万円 | 48万8,000円 |
| △住民税 | 3万8,000円 | 45万8,000円 |
| 差し引かれる金額の合計 | 19万6,000円 | 236万7,000円 |
| 手取り金額 | 30万4,000円 | 363万3,000円 |
年収600万円・月収50万円の手取り金額は、年363万3,000円、月30万4,000円です。
所得税率が20%となるのは所得金額が330万~約690万円までの場合です。よって、所得金額が457万9,000円であるこのケースは所得の20%から42万7,500を差し引いた金額が所得税となります。
収入に占める手取り金額の割合は約60%です。しかし、経費の金額や確定申告の方法によっては手元に残る金額の割合は減るでしょう。
年収700万円/月収58万円のフリーランスの手取り
| 項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 収入 | 58万3,000円 | 700万円 |
| △経費 | 5万8,000円 | 70万円 |
| △国民年金 | 1万6,000円 | 19万2,000円 |
| △国民健康保険 | 5万8,000円 | 69万3,000円 |
| 控除後の所得金額 | 45万1,000円 | 541万5,000円 |
| △所得税 | 5万5,000円 | 65万6,000円 |
| △住民税 | 4万5,000円 | 54万1,000円 |
| 差し引かれる金額の合計 | 23万2,000円 | 278万2,000円 |
| 手取り金額 | 35万1,000円 | 421万8,000円 |
年収700万円・月収58万3,000円の手取り金額は、年421万8,000円、月35万1,000円です。
各種控除後の所得金額は541万5,000円で約690万円より少ないため、所得税率はまだ20%のままとなります。
収入に対する手取り金額の割合は約60%と年収600万円の時と変わりませんが、500万円の時とやや比べると低くなっています。
年収800万円/月収66万円のフリーランスの手取り
| 項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 収入 | 66万7,000円 | 800万円 |
| △経費 | 6万7,000円 | 80万円 |
| △国民年金 | 1万6,000円 | 19万2,000円 |
| △国民健康保険 | 6万3,000円 | 75万8,000円 |
| 控除後の所得金額 | 52万1,000円 | 625万円 |
| △所得税 | 6万9,000円 | 82万3,000円 |
| △住民税 | 5万2,000円 | 62万5,000円 |
| 差し引かれる金額の合計 | 26万7,000円 | 319万8,000円 |
| 手取り金額 | 40万円 | 480万2,000円 |
年収800万円・月収66万7,000円の手取り金額は、年480万2,000円、月40万円です。
各種控除後の所得金額は625万円で約690万円以下なので、所得税率は20%のままです。ただし、所得税率が上がるまであと約65万円なので、この条件よりも経費が減ったり白色申告をして控除額が減ったりすると、税率が変わる可能性はあるでしょう。
収入に対する手取り金額の割合は約60%と年収600万円や700万円の時と同水準になっています。
年収900万円/月収75万円のフリーランスの手取り
| 項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 収入 | 75万円 | 900万円 |
| △経費 | 7万5,000円 | 90万円 |
| △国民年金 | 1万6,000円 | 19万2,000円 |
| △国民健康保険 | 6万9,000円 | 82万2,000円 |
| 控除後の所得金額 | 59万円 | 708万6,000円 |
| △所得税 | 8万3,000円 | 99万4,000円 |
| △住民税 | 5万9,000円 | 70万9,000円 |
| 差し引かれる金額の合計 | 30万2,000円 | 361万7,000円 |
| 手取り金額 | 44万8,000円 | 538万3,000円 |
年収900万円・月収75万円の手取り金額は、年538万3,000円、月44万8,000円です。
各種控除後の所得金額は708万6,000円と約690万円を超えているので、所得税率は23%に上がります。所得の23%から63万6,000円を控除した金額が所得税です。
なお、課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年から新たに消費税が課税されます。売上をさらに伸ばすことでかえって収入に対する手取り金額の割合が下がってしまうおそれがあるため、場合によっては売上高の調整が必要になってくるでしょう。
年収1000万円/月収83万円のフリーランスの手取り
| 項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 収入 | 83万3,000円 | 1,000万円 |
| △経費 | 8万3,000円 | 100万円 |
| △国民年金 | 1万6,000円 | 19万2,000円 |
| △国民健康保険 | 7万1,000円 | 85万円 |
| 控除後の所得金額 | 66万3,000円 | 795万8,000円 |
| △所得税 | 10万円 | 119万4,000円 |
| △住民税 | 6万6,000円 | 79万6,000円 |
| 差し引かれる金額の合計 | 33万6,000円 | 403万2,000円 |
| 手取り金額 | 49万7,000円 | 596万8,000円 |
年収1,000万円・月収83万3,000円の手取り金額は、年596万8,000円、月49万7,000円です。
各種控除後の所得金額は795万8,000円なので、所得税率は23%です。なお、次に所得税率が上がるのは所得が900万円以上になった時で、税率は33%になります。
先述の通り、課税売上高が1,000万円を超えると翌々年から消費税の対象となる点は意識しておきましょう。課税売上高は、売上高からその取引の売上返品、売上値引、売上割戻金額などを差し引いた金額です。
年収1,000万円の手取り金額や税金について、より詳しく知りたい方は以下の記事を確認してみましょう。
フリーランスが手取りを増やす方法

ここまでフリーランスの収入と手取り金額を見て、思ったよりも手取りが残らないと思った人もいるでしょう。しかし、手取り金額は工夫によって増やすこともできます。具体的にどのようにすればよいのか、方法を解説していきます。
経費の見直しをする
まず1つ目のポイントは、経費の見直しをすることです。
現在支払っている家賃や光熱費のなかで、新たに経費に計上できるものはないか確認してみましょう。
例えば自宅で仕事をしているなら家賃や電気代の一部は経費に計上できますし、書籍購入費など細々した支出もきちんと経費に計上すれば、ある程度大きな金額になるかもしれません。
経費を増やすとその分計算上の手取りは減りますが、課税所得も少なくなるため所得税や住民税を減らすことができます。
一方で、余計な経費を減らすことも重要です。事業のため、あるいは課税所得を減らすためであっても必要のないものを購入するのは単なる無駄遣いでしょう。削れる部分は削って手取りを増やすことがポイントです。
e-Taxで青色申告する
確定申告の際には、青色申告することで白色申告よりも課税所得の控除額を増やせます。所得税や住民税を減らす税金対策になり、手取りが増えるでしょう。さらに、青色申告のなかでもe-Taxを使った申告方法を選択すると、課税所得の控除額が65万円になります。これは、青色申告による最大控除額です。
e-Taxで確定申告を行うと、課税所得が減り手取り金額が増えるだけでなく、「自宅から確定申告書を提出できる」「書類で確定申告するよりも早く還付を受けられる」などのメリットを得られます。
マイナンバーカードから情報を読み取るための環境設定、利用者番号の取得など事前準備が必要ではありますが、メリットが大きいため積極的に活用しましょう。
収入によっては法人化を検討する
売上高や所得金額によっては、個人事業主として事業を続けるよりも法人化した方が税金を抑えられ、手取り金額を増やせることがあります。
法人化を検討する場合は、所得800万円以上、売上高1,000万円以上を目安にするとよいでしょう。例えば個人事業主として所得が900万円を超える部分について、所得税率は33%になります。しかし、法人化すると所得税ではなく法人税が適用されるようになり、所得金額によらず税率は最大23.2%に抑えられるのです。
また、個人事業主として売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税がかかります。しかし、消費税がかかるタイミングで法人化すると1~2年の間消費税の支払いが免除されるのです。
法人化のメリットやデメリット、手続きについては以下の記事で詳しく解説しているのでご確認ください。
売上自体をアップさせる
当然ですが、案件の単価を上げたり案件数を増やしたりして、そもそもの収入をアップさせることも、手取り金額を増やす方法として有効です。特に、新たに計上できる経費がない場合や、まだ法人化のタイミングとはいえない場合は、収入増加が最も現実的な手取り金額アップの方法となるでしょう。
もちろん収入が増えると、所得税や住民税、国民健康保険料なども増えてしまいます。しかし、本記事で年収別に手取り金額を見てきたことからも分かる通り、差し引かれる金額が増えたとしても、収入が多い方が手取り金額は高くなります。
ただ案件数が多すぎると、それぞれの仕事にかけるリソースも少なくなり、却って収入が下がる要因にもなりかねないので、高単価案件を多く紹介しているフリーランスエージェントの利用がおすすめと言えるでしょう。
ITプロパートナーズでは、仲介業者を挟まない「直案件」が9割なので、高単価な案件獲得ができる可能性が高いです。ぜひお気軽にご相談下さい。
なお、おすすめのフリーランスエージェントをもっと知りたいという方は、以下の記事も参考にしてください。
投資で資産形成を行う
フリーランスとして手取り金額を増やしたければ、投資を行い効果的な資産形成を行うのもいいでしょう。
フリーランスのような福利厚生の恩恵を受けられない働き方の場合、自身で資産形成を行う必要があります。例えばiDecoやNISAのような投資がおすすめです。一般的に投資によって得た利益には約20%の利益が発生しますが、iDecoやNISAであれば、非課税なので、節税しながら資産形成が可能です。
もちろん案件を獲得し収入を増やすことがフリーランスとして働く上で必須ですが、資産形成をうまく行い、資産を守ることも視野に入れておきましょう。
フリーランスと会社員の手取りを早見表で比較
フリーランスと会社員の手取りは、以下のとおりです。(あくまで目安になります)
| 年収 | フリーランスの手取り | 会社員手取り |
|---|---|---|
| 300万円 | 約180万円 | 225〜255万円 |
| 400万円 | 約240万円 | 300〜340万円 |
| 500万円 | 約300万円 | 375〜425万円 |
| 600万円 | 約360万円 | 450〜510万円 |
| 700万円 | 約420万円 | 525〜595万円 |
| 800万円 | 約480万円 | 600〜680万円 |
| 900万円 | 約540万円 | 675〜765万円 |
| 1,000万円 | 約600万円 | 750〜850万円 |
上記のように会社員とフリーランスの手取り金額には差があるものの、フリーランスは仕事で発生した費用を経費として計上できるため、課税所得を減少させ、節税効果を得ることができます。これにより、結果的に上記の表よりも手取り金額の差を埋められる可能性も高いです。
経費として計上できるものが気になる方は、以下の記事を参考にしてみるといいでしょう。
フリーランスの手取りについてよくある疑問
ここではフリーランスの手取りに関する、よくある疑問とその回答を紹介します。
手取り額は会社員とフリーランスどっちが多い?
一般的な目安でいうと、手取り金額はフリーランスよりも会社員の方が多いです。基本的に会社員は収入の75~85%が手取り金額になるのに対し、フリーランスの手取り金額は収入の60~70%が目安となります。
ただし、フリーランスの場合は家賃や光熱費の一部など、会社員が手取りから支払わなければならないものを経費に計上できます。会社員が手取りから支払っているものを経費から外してフリーランスの手取り金額を計算すると、必ずしもフリーランスの手取り金額の方が少ないとはいえないでしょう。また、成果が収入に直結しやすいフリーランスの方が収入を上げやすく、法人化して所得税から法人税に切り替えれば税率が下がります。
このように、フリーランスは工夫次第で自由になるお金を増やしやすいので、手取り金額の伸びしろという点で考えれば、フリーランスの方が利点があるともいえるでしょう。
フリーランスのメリットは以下の記事でも解説しているので、確認してみてください。
経費として計上できる金額が少ない場合でも、フリーランスであれば高単価案件を契約することで、会社員よりも手取り金額を増やすことができます。ITプロパートナーズでは、60〜100万円/月の高単価案件も数多く掲載しているので、まずは登録だけでもしてみることをおすすめします。
フリーランスの報酬からも源泉徴収される?
フリーランスの報酬であっても、源泉徴収されることがありす。
ここで注意すべきなのは、源泉徴収される金額と本来徴収されるべき金額が違う場合があるということです。例えば本来の所得税率は5%なのに、復興特別所得税も含めて税率10.21%で所得税が源泉徴収されるケースがあります。この場合、毎月の手取り金額は本記事で紹介したものより少なくなってしまうでしょう。
ただし、こうした現象は会社員でも同様に起こることです。会社員の場合は年末調整で過剰に徴収された分が返ってきますが、フリーランスの場合は確定申告をすることで払いすぎた金額が還付されます。
フリーランスの源泉徴収については以下の記事でさらに詳しく解説しています。
フリーランス月収100万円の手取りは?
経費を計上しない場合、フリーランス月収100万円の手取りは約77万円程度と言われており、税金と保険の支払額は以下のとおりです。
| 税金・保険 | 支払額 |
|---|---|
| 所得税 | 約69,700円 |
| 復興特別所得税 | 約1,800円 |
| 住民税 | 約53,500円 |
| 個人事業税 | 約23,000円 |
| 国民健康保険 | 約62,500円 |
| 国民年金保険 | 約16,600円 |
| 合計 | 約227,100円 |
このようにフリーランスとして月収100万円稼ぐ場合、約23万円の支払い額が発生します。税金の知識を押さえることも大切ですが、まずはひと月に100万円を稼ぐことを目標に、フリーランスとして業務に注力しましょう。100万円の稼ぎ方について気になる方は、以下の記事を確認するといいでしょう。
まとめ
フリーランスの収入は経費や年齢によって異なりますが、実際の手取りは収入の約60〜70%です。
手取りの割合を高めるには、経費の最適化が重要となります。例えば、不要な出費を削減し、必要経費だけを残すことで効率を上げることができます。
また、法人化することで税金の負担を減らすことも一つの手段です。加えて、収入の増加も重要です。新規クライアントの獲得やサービスの価値向上を図ることで、収入の向上が見込めるでしょう。このような戦略を通じて、フリーランスとしての手取り金額を最大化することが可能です。
収入アップにあたっては、弊社ITプロパートナーズのご利用がおすすめです。スタッフが希望に合った案件をご紹介するため、スキルアップに集中しながら効率よく条件の良い案件に出会えます。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)