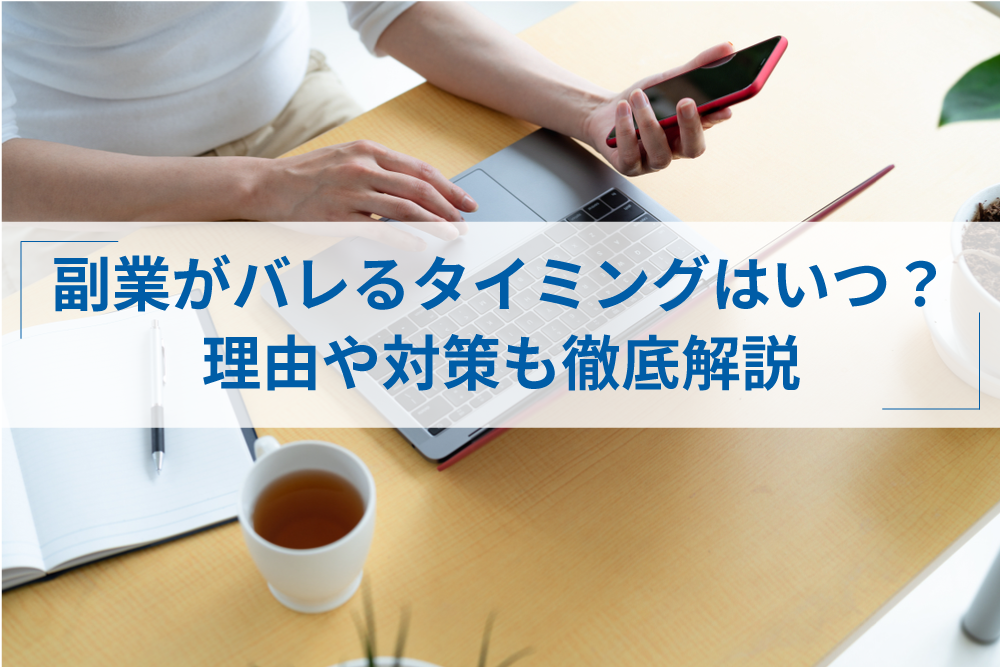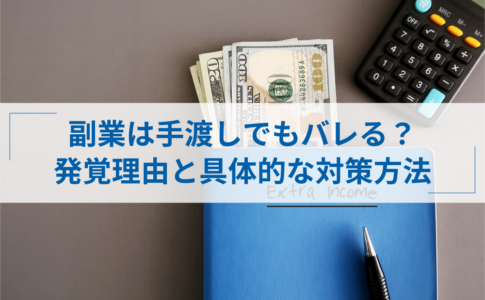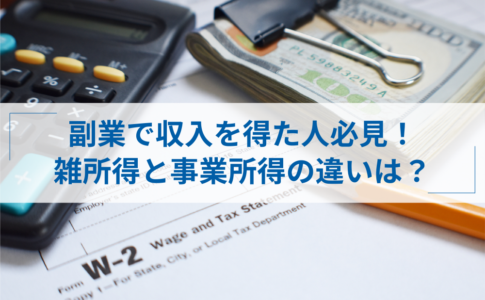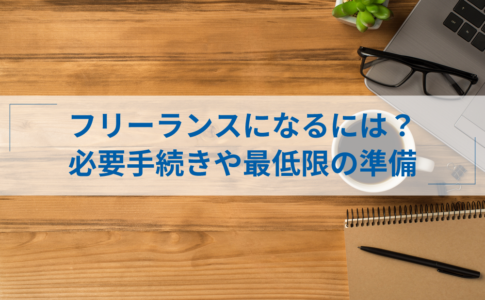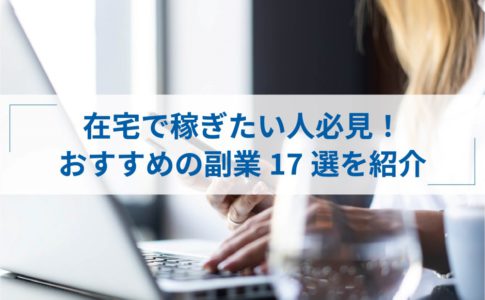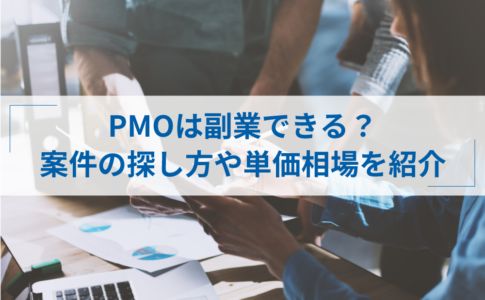こんにちは、ITプロマガジンです。
昨今、ダブルワークや副業が注目されています。「副業がバレるタイミングは?」「副業をしてみたいけど、会社にバレずに副業をする方法はあるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、会社に副業がバレる主なタイミング・理由や、バレた場合のリスク、よく挙げられるバレない対策とその実際の効果などを解説します。会社員として働いており、副業を考えている方は、ぜひ今回の内容を参考にしてください。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
副業がバレることの多い時期は6月

先に結論をお伝えすると、最も副業が発覚しやすいタイミングは6月と言われています。
例えば住民税は、前年度の所得に応じて計算されます。そしてその納付確定書が勤務先に届くのは6月頃です。納付確定書の情報と照らし合わせながら作業を行うため、ここでバレてしまうことになります。
このように税金関係でバレる場合は、6月が多いので覚えておきましょう。もちろん副業がバレるケースは多様なので、6月以外も気を抜けません。
副業がバレるタイミングと理由5選
副業は、さまざまな経路でバレることがあるため注意しましょう。ここでは副業がバレるタイミングと理由を解説します。
1.住民税の金額で副業がバレる
よく見られるのが、住民税の金額で副業がバレるケースです。
会社員の場合、住民税は給料から天引きされる形になります。給料から引かれた住民税は最終的に会社によって納税されるため、会社側がおおまかな納税額を把握している状態です。
住民税は前年度の所得から算出されるため、副業で所得が上昇すると、その分支払う住民税も高くなります。住民税の金額に相違が生じるため、その情報によって副業をしているのがバレてしまいます。
2.社会保険の手続きで副業がバレる
社会保険の手続きで副業がバレるのもよくあるケースです。企業に勤めており、一定の労働時間や賃金を超えて勤務する場合は、社会保険に加入しなければなりません。入社した際に社会保険関係の書類が渡されるのは、会社側が社会保険の手続きを行うためです。
社会保険の手続きが済むと、それぞれの企業の給与を合わせて、支払うべき保険料が算出されます。「1つの企業で働いている場合」と「複数の企業で働いている場合」の保険料が異なるため、それによって副業がバレてしまいます。
3.関係者からの通報でバレる
関係者からの通報でバレるケースも少なくありません。例えば副業をしている事実を、飲み会のような席で同僚に話し、同僚からの通報で副業がバレるケースがあります。
また会社関係者に話さなかったとしても、家族がその事実をうっかり話してしまい、人づてにバレてしまうケースもあります。
特に副業の影響で、本業に身が入らないような状態であれば、通報されるリスクも高まるので注意しましょう。
4.年末調整でバレる
年末調整でも副業がバレてしまいます。所得を得ている場合は、原則として1年に1度、納める所得税を申告しなければなりません。いわゆる確定申告と呼ばれるものです。
また会社で給与を得ている場合は、会社側が「年末調整」を行い、納めるべき税額を本人に代わって計算します。年末調整をする際、会社員は「給与所得者の基礎控除申告書」を会社に提出しなければなりません。別途収入がある場合は、その金額を記載しなければならないため、その情報で副業がバレてしまいます。
5.事故・ケガによる労災保険給付でバレる
事故・ケガが発生して労災保険給付を受ける場合、勤め先に副業していることがバレることがあります。これは、労災保険給付の金額は全ての勤務先の合計賃金額をもとに計算するためです。
仮に副業で給与を受けている場合、勤め先の給与よりも多い金額で手続きをする必要があり、副業していることが発覚します。
また、副業で事故に遭ってケガをしてしまうと、当然ながら勤め先から理由を尋ねられることになり、隠し切れずに副業がバレる可能性もあるでしょう。
ここまで見てきたように、副業がバレるタイミングは多いので注意が必要です。
副業がバレたらどうなるの?

現在副業をしており、「副業がバレたらどうなってしまうの?」と悩んでいる方も多いかもしれません。ここでは副業がバレたらどうなってしまうのか、さまざまなケースを想定しながら解説します。
就業規則によって処遇が変わる
副業がバレると、就業規則によって処遇が変わります。まず前提として知っておきたいのは、「副業は法律上禁止されているわけではなく、法的に裁かれることない」という点です。しかし会社には就業規則が存在するため、その内容によっては何らかの処分を受けるケースもあります。
就業規則とは、その会社にまつわる基本的なルールが記されているものです。就業規則に副業禁止または許可制の記載がある場合、それに反して副業をすれば、会社によって処分を下されます。
軽度なものであれば始末書を書かされるケースが多いでしょう。しかし副業の影響によって、本業に支障が出てしまえば、より重い処分になる可能性もあります。最悪の場合、懲戒処分を受け、退職につながる可能性もあるでしょう。
就業規則によって副業が禁止されているのであれば、処分されるリスクは高いと考えておくべきでしょう。また副業を認めている会社であっても、許可制になっている可能性もあるため、事前に確認しておくのが重要です。
公務員ならより重い処分が下される可能性も
公務員で副業がバレてしまった場合は、より重い処分が下される可能性もあります。公務員の処分としてよく知られているのは、国家公務員法第82条で定められている懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)と、組織内の処分(訓告など)です。
公務員として国または地方自治体に勤めており、副業が発覚した場合、減給はまず避けられないと考えた方がよいでしょう。また停職や免職になるケースも多いため、通常の会社員に比べてリスクが高いと言えます。
副業がバレないようにすることは可能か
副業をしていることを勤め先に隠し通すことは難しいのが実情です。住民税の仕組みや所得の種類によってリスクを減らすことは可能ですが、思わぬ形で発覚することもあります。ここでは、副業をバレにくくするためによく挙げられる対策と、その実際のリスクを紹介します。
現金手渡しでもバレることがある
現金手渡しの副業であっても、本業の勤務先にはバレてしまいます。最近は数が減っていますが、現在でも仕事や勤務先によっては、給与を手渡しで受け取るケースがあります。一見、本業の勤務先にはバレなさそうに見えますが、それは大きな間違いです。
そもそも会社は、給与の支払い形式にかかわらず、「誰にどれくらい給与を払ったのか」を役所に届け出なければなりません。どちらにせよ「給与を支払った(受け取った)」という情報は残ってしまうため、結果的に副業がバレてしまうことになります。
もちろん「庭の芝刈りを全部やって1万円もらった」のような、単発的な個人間のやり取りであれば、会社にバレることはないでしょう。ただし一般的な企業から給与をもらっているのであれば、現金手渡しであっても副業がバレてしまうので注意が必要です。
住民税を普通徴収に切り替えてもバレることがある
住民税を自分で納付する「普通徴収」にすれば、副業の収入が本業の会社に通知されないと考える人もいます。しかし、これは完全な対策にはなりません。
会社が従業員の給与に基づいて住民税を天引きする「特別徴収」では、副業収入が加算されることで不審に思われるケースがあります。そのため、「普通徴収に切り替えれば大丈夫」と言われることもありますが、実際には前半で挙げたように、住民税以外にもさまざまな理由でバレる可能性があるため、リスクはゼロにはならないのです。
事業所得・雑所得でもバレることがある
副業収入を給与所得ではなく、事業所得や雑所得として申告すればバレにくいと言われることがあります。これは、事業所得や雑所得の場合は給与所得とは別枠で計算され、勤め先には情報が共有されないためです。
これも一部では正しいですが、同僚や取引先が「副業しているらしい」という情報を本業の会社に伝えてしまったり、副業の事故・ケガで不審がられたりといったリスクは依然残ります。そのため、やはりバレるリスクをゼロにすることはできません。
秘密にしても情報が漏れる可能性はある
どれだけ副業の情報を隠しても、完全にバレない保証はありません。特にSNSや口コミを通じた情報発信をすれば、本人が意図せずとも会社に伝わってしまうリスクが増えます。
例えば、副業の成果や仕事のことをSNSに投稿した場合、匿名であっても偶然目にした同僚や上司が勘づいてしまうこともあります。また、家族や友人など限られた人だけに副業の話をしていても、それが間接的に会社に伝わるケースも少なくありません。
副業がバレることによるトラブルを防ぐ方法

ここまで副業がバレないようにするために意識するポイントを解説しました。それと同時に、副業がバレることによるトラブルを防ぐ方法も確認しておくとよいでしょう。ここではその方法を3つのトピックに分けて解説します。
会社に事前相談する
まずは会社に事前相談をしましょう。事前相談をするうえで確認しておきたいのが就業規則です。勤務先の就業規則を見て、副業についての記述を確認しましょう。例えば「副業は全面的に禁止」としている会社もありますが、「条件を満たせばOK」と定めているところもあります。
また先ほども少し触れたように、事前相談制になっている会社もあります。副業は会社の就業規則に則ってするようにし、事前相談の必要があれば必ず会社に報告しましょう。
もちろん副業の相談をしても、さまざまな事情によって認めてもらえないケースもあります。相談しても副業ができなさそうであれば、「副業ができる会社」への転職を検討してみるのもよいでしょう。
臨時的副業や資産運用を検討する
副業禁止の会社や公務員でも許可されている可能性が高い方法として、臨時的な副業や資産運用を活用するのも有効です。例えば、フリマアプリやネットオークションでの売却は、「自宅の不用品を売る」という名目で行われるため、副業とみなされることはほとんどありません。これなら就業規則に抵触するリスクを最小限に抑えながら、副業的に収入を得られます。
また、株式投資やFX、不動産投資などの資産運用も、副業としては扱われません。実際、公務員でも資産運用を行うことは認められており、会社員であればより自由に投資ができます。ただし株式やFXのようなものは、当然失敗するリスクもあるため、「確実に収入を得られるもの」とは考えないようにしましょう。
フリーランスとして独立する
「会社にバレるリスクを完全になくしたい」のであれば、フリーランスとして独立する方法もあります。独立すれば、就業規則に縛られることなく、自由に仕事を選べるようになります。例えば、エンジニアやデザイナー、ライターなどの職種であれば、これまでのスキル・人脈を活かしてクライアントを増やし、安定した収入を得ることも可能です。
ただし、フリーランスは会社員のように毎月決まった給与が保証されるわけではなく、仕事を継続的に獲得しなければ収入が不安定になる可能性があります。もちろんフリーランスとして独立するためには、実務経験を含めある程度のスキルが必要で、継続的なアップデート・リスキリングも欠かせません。
フリーランスとして独立する際は、メリット・デメリットを事前によく考えるのがおすすめです。
まとめ
副業がバレるタイミングとして最も多いのは6月の住民税通知時ですが、それ以外にも社会保険の手続き、年末調整、関係者の通報、事故・ケガによる労災申請など、さまざまな要因で発覚するリスクがあります。特に、就業規則で副業が禁止されている場合は、会社にバレると懲戒処分を受ける可能性もあり、慎重に行動することが重要です。
副業がバレるリスクを最小限に抑える方法として、臨時的な副業や資産運用が挙げられます。また、会社にバレる心配を完全になくしたいのであれば、フリーランスとして独立することも1つの選択肢となるでしょう。
副業・フリーランス案件を探す際は「ITプロパートナーズ」がおすすめです。IT/Web分野専門のフリーランスエージェントで、エンジニア、デザイナー、マーケター、コンサルタント向けの案件が多く、「高単価」「フルリモート」案件も豊富です。案件をお探しの方はぜひご活用ください。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)