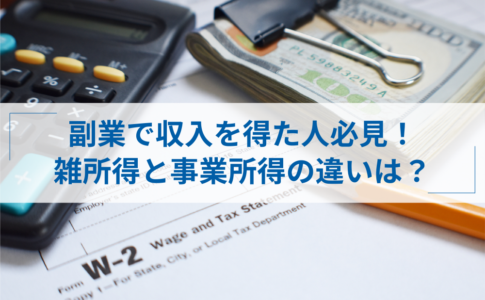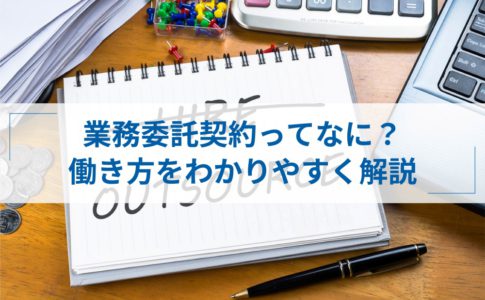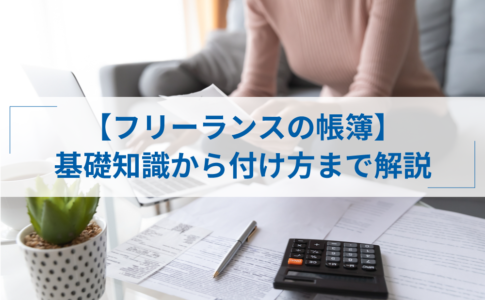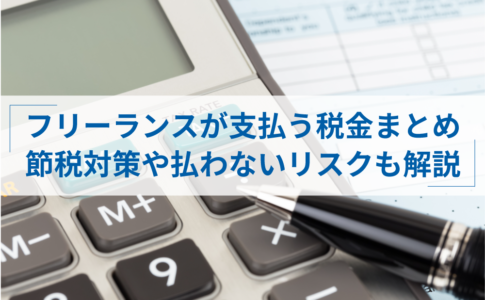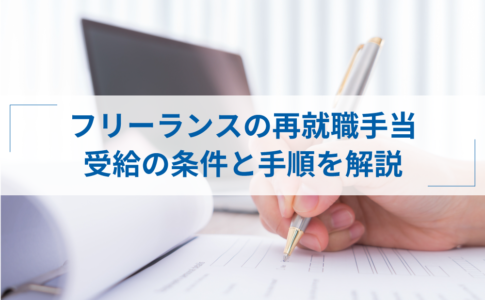こんにちは、ITプロマガジンです。
フリーランスとして活動を始めると直面する人が多いのが「自分の所得は給与所得なのか、事業所得なのか」という疑問です。所得区分を誤ると確定申告の内容が不正確になり、過大・過小納付につながる恐れもあるため、正しい理解が欠かせません。
一方で、フリーランスの所得は案件や契約形態によって分類が変わり、さらに副収入がある場合には雑所得として申告する必要も出てきます。こうした複雑さから、確定申告に不安を抱える人も少なくありません。
本記事では、「給与所得と事業所得の違い」「パターン別の所得区分」「確定申告の流れ」「よくある疑問点」などを解説します。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
フリーランスの所得は給与所得?事業所得?

フリーランスが得る収入は、基本的に事業所得として扱われます。ただし、状況によっては給与所得や雑所得に区分される場合もあるため注意が必要です。
例えば、副業としてアルバイトをしている場合は給与所得となり、単発の小規模な仕事は雑所得とされることがあります。所得の種類を正しく理解しておくことで、確定申告といった税務手続きをスムーズに進められます。以下では、それぞれの所得区分について解説します。
事業所得に該当する所得
事業所得とは、継続的に事業として行う活動から得られる所得を指し、収入から必要経費・各種控除項目を差し引いた後の金額が課税対象となります。
フリーランスがクライアントから受け取る報酬は、基本的にこの事業所得に該当します。特にITエンジニアやWebデザイナー、ライターなど、継続して案件を請け負う働き方の場合は事業所得に当たるでしょう。
確定申告の際は、事業所得として申告することで、家賃や通信費、ソフトウェア利用料といった業務に必要な経費を損金計上でき、節税効果を得られる点も特徴です。
給与所得に該当する所得
給与所得とは、雇用契約に基づき勤務先から支給される給与や賞与などの収入を指します。
フリーランスとは特定の組織に所属しない働き方ですが、一時的に企業と雇用契約を結んで働くケースもゼロではありません。また、フリーランスの活動に加えて、パート・アルバイトを並行して行う場合、その収入は給与所得に区分されます。さらに会社員が副業としてフリーランス案件を請け負う場合、本業の給与は給与所得、フリーランスの報酬は事業所得として別々に考える必要があります。
雑所得に該当する所得
雑所得とは、事業所得や給与所得など他の所得区分に当てはまらない収入を指します。具体的には、公的年金や講演料、シェアリングエコノミーによる収入、単発の原稿料などが代表的です。フリーランスの場合でも、継続性が乏しい単発の副業収入は雑所得に分類されることがあります。
事業所得と異なり、青色申告特別控除などの適用は受けられません。そのため、フリーランスとして活動するうえではどの所得に該当するかを正しく判断することが重要です。詳しくは国税庁の解説をご覧ください。
その他の所得
フリーランスの収入は多くの場合、事業所得や給与所得、雑所得のいずれかに分類されます。しかし、所得税法では全部で10種類の所得区分が定められており、これらに含まれない所得も以下のように存在します。
| 所得区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 利子所得 | 預貯金や公社債の利子 |
| 配当所得 | 株式や投資信託の配当 |
| 不動産所得 | 不動産や土地の賃貸収入 |
| 退職所得 | 退職金や一時金 |
| 山林所得 | 山林の伐採・譲渡収入 |
| 譲渡所得 | 山林の伐採・譲渡収入土地・建物・株式などの売却益 |
| 一時所得 | 懸賞金、保険の満期金など |
フリーランスの本業とは直接関係がなくても、副収入として得た場合には確定申告に記載する必要があります。
フリーランスが知っておきたい給与所得・事業所得の違い
以下の表は、給与所得と事業所得の代表的な違いをまとめたものです。
| 項目 | 給与所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 契約の種類 | 雇用契約 | 業務委託契約・売買契約など |
| 収入から差し引く金額 | 給与所得控除 | 必要経費・青色申告特別控除など |
| 必要な手続き | 年末調整または確定申告 | 確定申告 |
| 帳簿の作成 | 任意 | 必要 |
このように、契約形態や差し引ける金額、手続き・帳簿要件などには違いがあります。以下でそれぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
契約の種類の違い
給与所得は「雇用契約による収入」であり、事業所得は「業務委託契約などによる収入」に該当します。
雇用契約とは、従業員として会社と雇用関係を結び、勤務場所・時間の指定や指揮・命令を受ける形態です。給与や賞与などが支払われ、これらは給与所得として扱われます。
一方、事業所得では、「売買契約」のほか、「請負契約」や「委任・準委任契約」といった業務委託契約が多く、クライアントから仕事を受け、成果物や役務提供を対価として報酬を得る形です。業務委託報酬は給与所得にならず、事業所得またはスポットの場合は雑所得として扱われます。なお請負契約は成果物の納品に対して、委任・準委任契約は業務遂行・役務の提供に対して対価を受け取る契約形態です。
収入から差し引く金額の違い
給与所得では「給与所得控除」が自動的に適用されますが、事業所得では「必要経費」や「青色申告特別控除」などを個別に差し引くことが可能です。
給与所得者は仕事にかかった支出を経費として個別に申告しない場合でも、いわば「みなし経費」として所得額に応じて定められた給与所得控除が適用されます。
一方で、事業所得では、事務所家賃・通信費・機材購入費用・外注費など、実際に業務に関連する経費を収入から差し引けます。さらに、青色申告を選択している場合には「青色申告特別控除」(最大65万円)が受けられ、節税効果が生じます。
必要な手続きの違い
雇用契約で給与所得者として働いている場合、本業の所得については勤め先が源泉徴収や年末調整を行います。ただし、給与以外の所得がある場合、所得が一定額を超えれば自身で確定申告する必要があります。
一方で、事業所得として働くフリーランス・個人事業主は、自ら確定申告を行わなければなりません。年間所得が一定額を超えると申告・納税義務が生じる仕組みで、所得が少額である場合には確定申告が不要となるケースもあります。
帳簿作成の必要性の違い
事業所得には帳簿の作成が求められ、収支の記録や証拠資料の保存が義務になりますが、給与所得にはそのような帳簿作成は不要です。
事業所得の場合、収入と支出を記録した帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)を作成し、請求書・領収書などの証拠書類を一定期間保存することが求められます。電子帳簿等保存制度も整備されており、要件を満たせば電子データでの保存も可能です。
一方で、給与所得者は勤め先が源泉徴収票や給与明細を発行するため、自身で帳簿を用意する必要はありません。
【パターン別】フリーランスの所得区分と必要な手続きの違い

フリーランスは働き方の形態によって所得の区分が変わり、それに伴って必要な手続きも異なります。特に給与所得と事業所得の扱いは税務上大きな違いがあるため、どのケースに該当するかを正しく把握しておくことが重要です。ここでは代表的なパターンを整理します。
フリーランスの収入だけの場合
フリーランスとしての収入のみを得ている場合、その報酬は原則として「事業所得」に区分されます。会社員のように年末調整で勤め先が税金を計算・調整するわけではなく、自ら帳簿を作成し、確定申告を行う必要があります。
事業所得として申告する場合、売上から業務に必要な経費を差し引けるため、節税効果が得られるのが特徴です。例えば、パソコンの購入費やソフトウェアの利用料、作業スペースの家賃、通信費などは必要経費として計上できます。
結論として、フリーランスの収入しかない場合は「年末調整は受けられない」「確定申告が必須」という2点を押さえておくことが重要です。青色申告を選べば、記帳や帳簿保存の手間はあるものの、最大65万円の控除が適用されます。
フリーランスの収入+会社員・パート・アルバイト収入がある場合
フリーランスの事業所得に加えて、雇用契約に基づく給与収入がある場合は、それぞれを「事業所得」と「給与所得」に分けて考える必要があります。給与所得は勤務先が源泉徴収や年末調整を行いますが、事業所得は自身で確定申告を行わなければなりません。
給与以外の所得の合計が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、超える場合は申告が必要になります。例えば、会社員として本業で年収400万円を得ながら、副業としてWeb制作案件で年間30万円を受け取り経費を引いて25万円だった場合、その25万円は事業所得として確定申告を行います。
年の途中でフリーランスになった場合
年の途中で会社を退職し、フリーランスとして独立開業した場合は、必ず確定申告を行う必要があります。
会社員は通常、年末調整によって勤め先が納税手続きを代行してくれます。しかし、年の途中で退職すると、その年の年末調整は行われません。そのため、自身で1年間の所得を全て合算し、納税額を計算・申告する必要があります。
具体的には、以下の2つの所得を申告書に記載することになります。
- 給与所得:会社員時代に得た給与・賞与
- 事業所得:独立後にフリーランスとして得た報酬
申告をスムーズに進めるためにも、退職時に勤め先から交付される「源泉徴収票」と、事業用の「帳簿」をあらかじめ準備しておくことが肝要です。
フリーランスの収入+その他の副収入がある場合
フリーランスの事業収入に加えて家賃収入や講演料などの副収入がある場合は、収入の性質ごとに区分を分けて確定申告する必要があります。前述の通り、所得税法では所得が10種類に分類され、それぞれ計算方法や経費の扱いが異なるため注意しましょう。
例えば、ライターとして年間300万円の事業所得があり、副収入としてアパート経営から100万円の家賃収入を得ている場合には、確定申告書に「事業所得300万円」「不動産所得100万円」と分けて記載します。さらに、単発の講演料や原稿料で得た収入は「雑所得」に該当します。
フリーランスの給与所得・事業所得の確定申告のやり方
フリーランスは、自身の所得区分に応じて確定申告を行う必要があります。フリーランスとして給与所得を得ることは比較的珍しいものの、会社員が副業的に活動する「副業フリーランス」や一時的に組織に雇用されるケースで事業所得もあるケースなど、給与所得・事業所得をまとめて確定申告するケースもあるため注意が必要です。ここでは、青色申告・白色申告の違いや必要書類の準備について整理します。
青色申告・白色申告を選択する
フリーランスが確定申告を行う際は、まず「青色申告」と「白色申告」のどちらを選ぶかを決めます。白色申告は手続きが比較的簡単ですが、控除額や節税のメリットは限定的です。一方、青色申告は複式簿記による帳簿付けなどが必要になる代わりに、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、赤字を翌年以降に繰り越せるといったメリットがあります。
青色申告を選ぶ場合には、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければならず、申告を始めたい年の3月15日まで(または事業開始等の日から2ヶ月以内)に手続きが必要です。節税効果を重視するなら青色申告、事務作業の負担を軽くしたいなら白色申告を選ぶとよいでしょう。
必要書類を作成する
確定申告には、収入や経費を正しく申告するための書類を準備します。主なものは以下の通りです。
- 確定申告書
- 決算書(青色申告の場合)または収支内訳書(白色申告の場合)
- 源泉徴収票(給与所得がある場合)
- 領収書や請求書などの経費証憑
- 控除証明書(生命保険料控除や医療費控除などを受ける場合)
これらの書類は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すればオンラインで作成可能です。経費関連の証憑は日頃から整理しておくと、確定申告時にスムーズに集計できます。
確定申告書を提出する
必要書類を作成したら、最後に確定申告書を提出します。提出方法は大きく分けて3つあります。
1つ目は「税務署に直接持参する方法」で、窓口に提出すればその場で受領印が押され、控えを受け取れます。
2つ目は「郵送による提出」で、提出期限内の消印があれば有効です。控えを返送してもらう場合は、返信用封筒を同封する必要があります。
3つ目がe-Taxで、マイナンバーカードとICカードリーダー、もしくはスマートフォンを使ってオンラインで申告できます。
e-Taxを使うと、24時間いつでも申告可能で、還付金の振込が早いという利点があります。一方で、初めて利用する際には環境設定や利用者識別番号の取得などの準備が必要です。
自身の状況や利便性を踏まえて提出方法を選びましょう。
フリーランスの所得についてよくある疑問
フリーランスとして活動を始めると、税金や所得の区分について疑問を抱く人は少なくありません。ここでは特に多い質問について、区分の違いや注意点を整理します。
雑所得と事業所得の違いは?
雑所得と事業所得は似ているように見えても、税務の扱いが大きく異なります。事業所得は継続性や営利性がある活動から得られる収入で、必要経費の幅が広く、青色申告を選べば65万円の控除など節税メリットを享受できます。一方、雑所得は一時的・断続的に発生する収入が対象で、経費として認められる範囲が限られる点が違いです。
例えば、継続的にライティング案件を受けている場合は事業所得に該当しますが、単発で受けた講演料や原稿料は雑所得に当たります。収入をどちらに区分するかは、活動の継続性や規模によって判断されるため、判断に迷う場合は税務署や税理士に確認すると安心です。
フリーランスが経費にできる項目は?
フリーランスは、業務に必要な支出を経費として計上できます。代表的な項目としては、自宅を仕事場にしている場合の家賃や光熱費の按分、業務に利用する通信費やパソコン・ソフトウェアの購入費、取引先との打ち合わせにかかる交通費や交際費などがあります。
ただし、生活費や私的な支出は経費にできません。例えば、自宅の家賃を全額経費にするのではなく、「家事按分」という考え方に沿って仕事で使用している面積割合に応じて計算する必要があります。経費の線引きは曖昧になりやすいため、領収書や請求書を必ず保存し、合理的に説明できる形で処理することが重要です。
フリーランスが払う税金の種類は?
フリーランスは、会社員のように給与天引きで自動的に所得が申告・納税されるわけではなく、自ら計算・納税を行う必要があります。代表的な税金は「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」の4種類です。所得税と住民税は収入から経費を差し引いた課税所得に応じて課され、確定申告で算出します。
個人事業税は、事業所得が年間290万円を超える場合に対象となり、業種によって税率が異なります。さらに、課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務も発生するケースもあります。
こういった仕組みを正しく理解していないと、思わぬ支出が生じることがあります。フリーランスとして活動する際は、事前にシミュレーションを行い、納付分の現金を確保しておくことが重要です。
まとめ
フリーランスの所得は、契約方法や収入の性質によって「給与所得」「事業所得」「雑所得」「その他の所得」に区分されます。それぞれ必要な手続きや控除の扱いが異なるため、正しい区分を把握して確定申告に臨むことが重要です。事業所得であれば、経費の対象が広く、青色申告による特別控除が適用できます。
また、副収入がある場合や年の途中で働き方が変わる場合は、所得区分を分けて記載する必要があり、申告漏れを防ぐためにも丁寧な整理が欠かせません。
IT/Web分野で副業やフリーランス案件を探すなら、ITプロパートナーズがおすすめです。週2〜3日から稼働可能な案件やフルリモート案件が豊富にあり、エンジニア・デザイナー・マーケターなど多様な職種に対応しています。スキルや経験に合った案件を効率的に探したい方はぜひご利用ください。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)