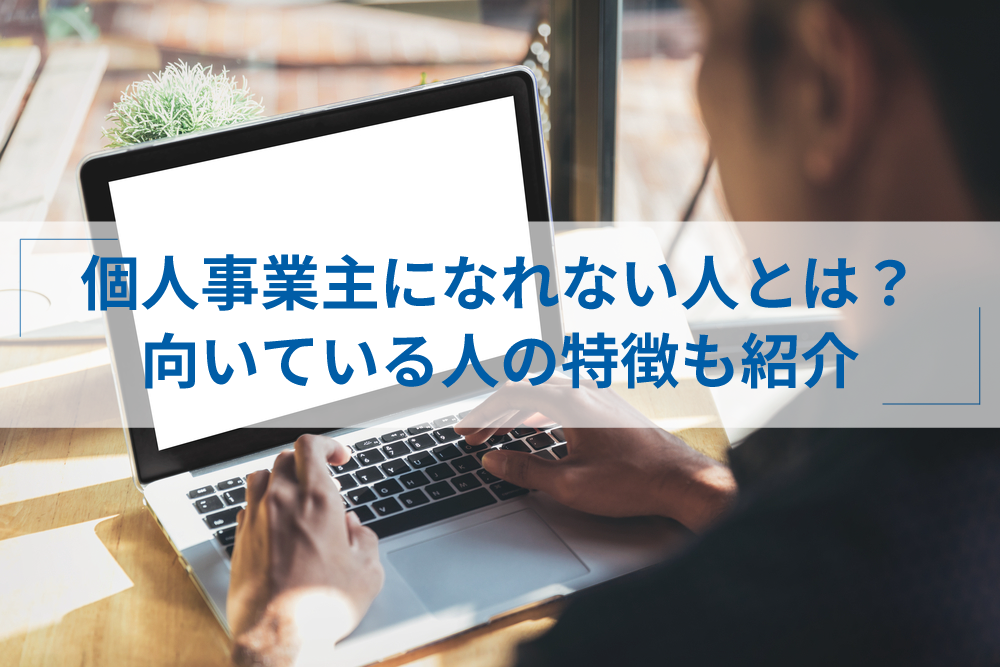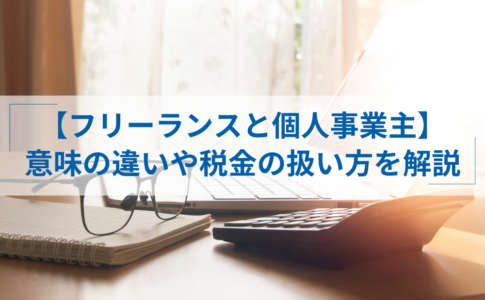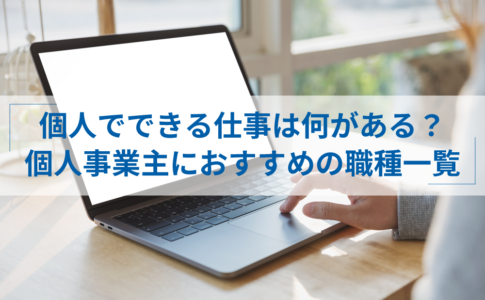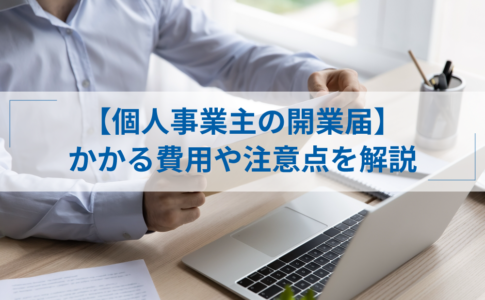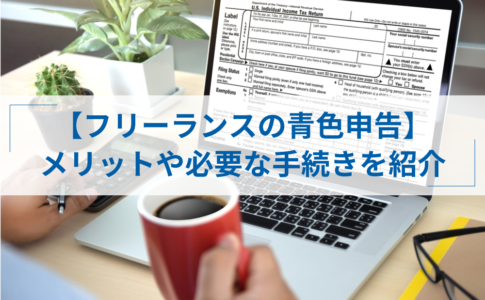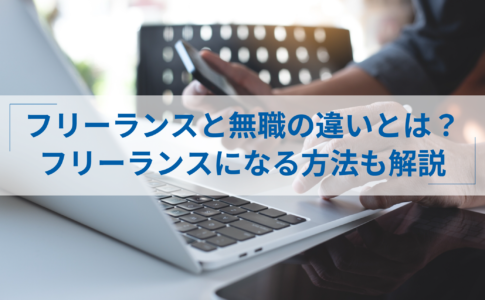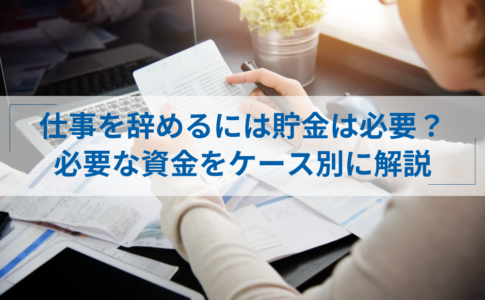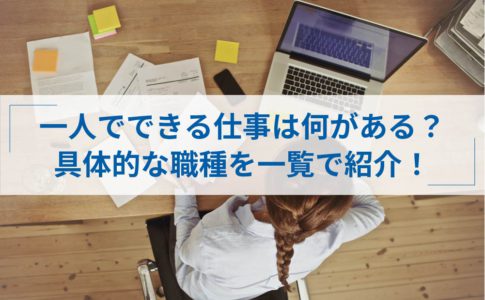こんにちは、ITプロマガジンです。
「個人事業主に興味はあるけれど、自分でもなれるのか心配」という方もいるのではないでしょうか。結論からいえば、法律上はほとんどの人が個人事業主になれますが、一部、なれない人もいます。また、法律上は問題がなくとも、個人事業主に向かないという人もいます。
そこで本記事では、個人事業主を検討している人向けに、個人事業主になれない人や、向かない人・活躍しやすい人の特徴、独立におすすめな職種、なり方などについて紹介します。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
個人事業主とは?
個人事業主とは法人を設立せず、個人で事業をおこなっている人や事業形態を指します。
個人事業主として事業を開始する際には、税務署に「開業届」を提出する必要があります。開業届を出さずとも個人事業主として活動はできますが、税法上「個人事業主」と呼ばれるのは、開業届を提出した人になります。
個人事業主は、自営業やフリーランスと混同されやすいため、それぞれの違いについて確認していきましょう。
個人事業主と自営業の違い
自営業は他の会社に属さず働くといった働き方を指し、そのような人を自営業者と呼びます。
自営業者の中には個人事業主が含まれますが、個人事業主は自営業者の一部に過ぎません。また個人事業主と比較すると、自営業者は飲食店などの実店舗を構えて事業を行っている人を指すのが一般的です。
個人事業主とフリーランスの違い
フリーランスは個人事業主と比べると、業務や働き方において大差はありません。個人事業主も広義ではフリーランスとなります。
しかし税務上で明確な違いがあります。個人事業主とは、税務署に個人事業主として開業届けを提出した人を指す名称です。一方でフリーランスは単に「働き方」を指す言葉であり、開業届けを提出してないフリーランスは、税務上、個人事業主ではありません。
フリーランスと個人事業主の具体的な違いについて知りたい方は、以下の記事を確認してみましょう。
個人事業主になれない人

個人事業主には、誰もがなれるわけではありません。以下のような人は、基本的に個人事業主にはなれないので注意しましょう。
公務員をしている人
公務員は、国家公務員法や地方公務員法による副業禁止規定により、個人事業主になることができません。公務員は職務専念義務を負い、本業に支障をきたす可能性があるため、営利目的の事業を行うことが認められていないのです。また、公務員の信用を損なう行為や業務上の秘密保持義務も、副業禁止の理由です。
ただし、投資による資産運用や、講演・執筆活動などの非営利活動は、可能なケースもあります。
副業が禁止されている企業に務めている人
就業規則によって副業が禁止されている会社に勤務している場合は、原則として個人事業主になれません。もし会社の許可なしに個人事業主として活動してしまうと、懲戒処分の対象になる可能性があります。
近年、副業に関しては許容する会社も増えていますが、機密情報の漏洩や本業への影響を防ぐために、副業を禁止している会社も一定数存在します。個人事業主になろうと考えている場合は、就業規則をしっかり確認するようにしましょう。はっきりしない時は、自己判断せず、上司に相談すべきです。
法律によって個人事業主になれない人
公務員以外にも、法律によって個人事業主になれない人がいます。主に、以下のような人たちです。
- 18歳以下
- 破産者
- 成年被後見人・被保佐人・被補助人
ただし、上記に該当する場合も、個人事業主になることが不可能なわけではありません。例えば、18歳以下の未成年でも、親などが法定代理人になれば契約行為を行うことができます。とはいえ、契約のたびに法定代理人をはさまなければならないというのは煩雑であり、個人事業主として活動するには大きな足かせとなってしまうでしょう。
破産者や成年被後見人なども、場合によっては個人事業主になれますが、「制限がある」「資金調達が難しい」などの問題があるため、個人事業主として活動するのは現実的に難しいと言えます。
個人事業主になるメリット
個人事業主になるメリットは、以下のとおりです。
- 働き方が比較的自由になる
- 能力に応じて収入を得られる
それぞれについて確認しましょう。
働き方が比較的自由になる
個人事業主になれば、比較的に自由度高く働くことができます。
個人事業主は会社員のように勤務時間や勤務地に縛られず、自分のライフスタイルに合わせて働くことができるからです。例えば、朝早くから仕事を始めて午後は自由な時間を確保したり、休日を柔軟に調整したりすることも可能です。
また、仕事の内容や取引先を自分で選べるため、得意分野を活かして自由に働くこともできます。
このように個人事業主は、比較的ストレスなく自分らしい働き方を実現できます。
能力に応じて収入を得られる
個人事業主は仕事の成果や結果が直接収入に反映されるため、自分の能力次第で、収入を上げることができます。
会社員の場合、どれだけ努力しても給与は基本的に一定で、昇給には時間がかかることが一般的です。しかし、個人事業主であれば、スキルや実績を高めることで、より高単価の仕事を受けられるようになり、収入を増やすことが可能です。
また、顧客の満足度を上げることでリピートや紹介が増え、安定的な収入につなげることもできます。
このように、個人事業主は努力と工夫次第で収入を大きく伸ばせる可能性があるため、やりがいのある働き方ができるのが特徴です。
個人事業主になるデメリット
メリットのある個人事業主ですが、一方で独立するデメリットもあります。
- 収入が不安定
- 社会的信用が低い
リスクを最小限に押さえるためにも、それぞれのデメリットについて確認しましょう。
収入が不安定
個人事業主は、収入が不安定になりやすい働き方とも言えます。
会社員の場合、毎月決まった給料が支払われ、有給休暇やボーナス、社会保険といった福利厚生も充実しているため、安定した生活を送りやすいです。一方、個人事業主は、案件の獲得状況や市場の変化、能力などに大きく影響を受け、収入が変動することがあります。
特にクライアントが減ったり、需要が下がったりすると、一気に収入が落ち込むリスクが高いです。また、病気やケガで働けなくなった場合、収入が途絶えてしまう可能性もあります。
社会的信用が低い
個人事業主は、会社員と比較して社会的信用が低いというデメリットがあります。
会社員であれば、毎月安定した給与が支払われ、雇用契約のもとで働いているため、金融機関や賃貸契約の審査などで信用を得やすいです。特に住宅ローンやクレジットカードの審査では、勤務先の安定性や勤続年数が重視されるため、会社員は有利な立場にあります。
一方、個人事業主は収入が変動しやすく、雇用の保証もないため、審査に通りにくいことがあります。
そのため、個人事業主として働く場合は、確定申告を正しく行い、継続的な収入を証明することが大切です。
個人事業主に向いている人の特徴

個人事業主に向いていない人の特徴を見てきましたが、反対に個人事業主として向いている人・活躍しやすい人には次のような特徴があります。
- 主体的に物事に取り組める
- 責任感や覚悟を持っている
- 自分自身を客観視できる
- 向上心がある
上記4点について、詳しく解説していきます。
主体的に物事に取り組める
主体的に物事に取り組める人は、個人事業主として活躍しやすいです。個人事業主は自分自身で事業を動かしていかなければならないため、会社員よりもさらに主体性が求められます。
例えば収入が不安定だったり仕事が少なかったりする場合は、自分自身で営業をして仕事を増やしていかなければなりません。
このように仕事上の問題は全て自分の判断と行動で解決していくという主体性があれば、個人事業主として長く働きやすくなります。
責任感や覚悟を持っている
責任感や覚悟を持っていることも、個人事業主として活躍しやすい人の特徴です。
個人事業主は自分で事業を回していくため、良いことも悪いことも全て自己責任となります。例えば「クライアントが報酬を上げてくれない」「クライアント側の納期設定に無理がある」など他責思考で考えていても何も変わりません。
「なぜ収入が上がらないのか」「納期が短いなかでどのような工夫あるいは交渉をすべきか」などを自己責任ベースで考えて行動していく覚悟があれば、状況を好転させながら活躍していけるでしょう。
自分自身を客観視できる
自分自身を客観視できる人も、個人事業主として活躍しやすいです。
個人事業主には上司や同僚がいないため、自分の強みや弱みを客観的に指摘してくれる人が少ないです。よって、自分自身を客観視し、強みを伸ばして弱みを克服していかなければ、成長できなかったり努力の方向を間違えたりしてしまうでしょう。
自分を客観視することは、体調管理やスケジュール管理など自分自身をコントロールするためにも重要です。
向上心がある
向上心の有無も、個人事業主に向いているかどうかを測る指標になります。個人事業主は、会社員とは違い、需要がなくなれば仕事がなくなってしまいます。そのため、周囲から求め続けられるように、「更なるスキルアップを図りたい」「より多くの知識を得たい」という向上心を持ち、常に成長を続けなければいけません。
向上心があり、日々成長している人は、自然と仕事が増えていくでしょう。
個人事業主に向いていない人の特徴
個人事業主になれない人は基本的にいないと説明しましたが、向いていない人はいます。個人事業主に向いていない人の特徴として以下4点が挙げられます。
- そもそもどうやって稼ぐかわからない
- 自己管理できない
- 現状に満足している
- 決断力が低い
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
そもそもどうやって稼ぐかわからない
個人事業主は、稼ぐために自ら考えて動く必要があります。会社員のように、どう行動すればいいかについて指示をしてくれる上司や先輩はいません。したがって、「どうやって稼いでいいかわからない」と考えている人は、個人事業主にならない方がよいです。稼ぎ方がわからないまま、勢いだけで個人事業主になっても、すぐに貯金が尽きてしまうでしょう。
個人事業主になるのならば、稼ぐためのノウハウを学んだり、アイデアが浮かんだりしてからにすべきです。
自己管理ができない
売上の目標管理や仕事のスケジュール管理、体調管理といった自己管理ができない人は、個人事業主に向きません。
例えば不摂生が続き体調を崩したりスケジュール管理が甘かったりしても、個人事業主だと仕事を手伝ってくれる人がいないため、納期に遅れる可能性があります。納期に遅れることが続けば、個人事業主として仕事を得にくくなるでしょう。
よって、自分で自分を律して体調やスケジュールなどを管理できない人は、個人事業主には向かないのです。
現状に満足している
現状に満足している人も、個人事業主として活躍していくのは厳しいでしょう。
例えば現在の会社員としての収入に満足しているのに個人事業主になると、「ボーナスがない」「収入が不安定になる」といったことで不満や不安を感じ後悔するかもしれません。個人事業主になるとたとえ収入が安定しても、突然仕事が切れて再び不安定になることは十分ありえます。よって、常に現状を疑い、リスクに備えたり目標を持ち続けたりできることが重要なのです。
また、向上心や上昇志向がない人も、個人事業主として活躍していくのは厳しいでしょう。
個人事業主は、会社員のように他人からフィードバックを受ける機会は多くありません。現状維持を続けていると、「業界の新たな流れについていけない」「個人事業主歴にスキルが見合わない」といった理由から仕事を得にくくなり廃業に追い込まれるおそれがあるのです。
決断力が低い
決断力も、個人事業主として仕事をしていくために欠かせない要素です。個人事業主になると、時にはリスクを冒してチャレンジすることも必要です。事業存続にかかわる重大な決断が必要になることもあります。
「どういう方向性で事業を進めていけばよいか分からない」「さらなる事業拡大につながるチャレンジをしたいが踏み出せない」などと迷っていると、タイミングを逃してしまうおそれがあるのです。
こうしたことから、個人事業主には大きな決断をする力も必要です。
個人事業主になるまでの流れ

会社員が個人事業主になるまでの流れは、次の通りです。
- 事前準備をする
- 開業届を提出する
- 青色申告承認申請書を提出する
- 国民健康保険や国民年金に加入する
これから個人事業主を目指すためにも、それぞれの手順について確認しましょう。
事前準備をする
事前準備とは、貯金やクレジットカードの作成などを指します。個人事業主になるとしばらくは収入が安定しないことが予想されます。クレジットカードの審査も厳しくなる可能性があるため事前に準備しておきましょう。
その後、自分のスキルの棚卸しや事業環境のリサーチをし、職種や事業内容について考えましょう。
開業届を提出する
その後、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を出せば個人事業主になることができます。開業届の提出方法は3つあります。
- 税務署の窓口へ持参する方法
- 郵送する方法
- e-Taxを使う方法
e-Taxとは国税電子申告・納税システムのことを指し、このシステムを利用することで、インターネット経由で開業届の提出が可能です。Freee開業などのサービスを利用すれば、より効率的に手続きを進められるので、利用を検討してみるといいでしょう。
青色申告承認申請書を提出する
確定申告で青色申告をする場合は、開業届を提出した年の3月15日までに、管轄の税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告承認申請書を提出することで、最大で65万円の青色申告特別控除などのメリットを受けることができます。
国民健康保険や国民年金に加入する
個人事業主は、健康保険や厚生年金に加入することができません。そのため、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
加入手続きはお住まいの市区町村役場で行います。加入に必要な書類は以下のとおりです。
| 国民健康保険に必要な書類 | 国民年金に必要な書類 |
|---|---|
| ・健康保険の資格喪失日が分かる証明書 ・マイナンバーが確認できるもの ・身分証明書 ・印鑑 | ・退職日がわかる証明書 ・年金手帳 ・身分証明書 ・印鑑 |
手続きは退職翌日から14日以内に済ませる必要があるので注意しましょう。
個人事業主に関するよくある質問
独立したいと考えている方にとって、個人事業主という働き方にはさまざまな疑問があります。
- 個人事業主に適した職業は?
- 会社員をしながら個人事業になれる?
- 個人事業主と法人どちらがおすすめ?
- 個人事業主を辞める方法は?
それぞれの疑問について、回答していきます。
個人事業主に適した職業は?
個人事業主になりたいなら、ITエンジニアやライター、デザイナーなどの職業がおすすめです。パソコンとインターネット環境があれば場所を選ばずに働けるため、個人事業主としての自由度が高いです。
リモートワークが可能な案件も多い事務やカスタマーサポート、働く時間を自由に選べるデリバリースタッフもおすすめと言えるでしょう。
会社員をしながら個人事業主になれる?
会社員をしながら個人事業主になることは可能です。
しかし、勤務先の就業規則によっては、副業が制限されている場合があります。特に公務員や一部の企業では副業が禁止されており、違反すると懲戒処分の対象になる可能性もあるので、事前に確認しておくのがいいでしょう。
個人事業主と法人どちらがおすすめ?
個人事業主と法人のどちらが適しているかは、事業の規模や目的などによって異なります。
個人事業主は開業手続きが簡単で、税務や会計の負担も比較的少ないため、低リスクで始められるのがメリットです。一方、法人は信用力が高く、大きな取引がしやすいほか、利益が増えれば法人税のメリットを活かせます。
個人事業主か法人のどちらで始めるべきか悩んでいる方は、以下の記事がおすすめです。
個人事業主を辞める方法は?
個人事業主は、廃業に関する以下の書類を所管の機関に提出することで辞めることができます。
- 個人事業の開業・廃業等届出書の提出
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出
- 事業廃止届出書の提出
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書の提出
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書の提出
特に廃業届を提出しなければ、事務所は事業が続いていると判断し、税金を課す可能性があるため注意してください。
まとめ
個人事業主になること自体は誰でも可能です。しかし、個人事業主として長く働くことを考えると、自己研鑽の習慣化や事業を自分で回す責任感・主体性などが必要です。
また、自分のスキルや希望条件に合った案件を獲得することも、個人事業主として働くために欠かせません。弊社ITプロパートナーズなら、エージェントが厳選した案件を紹介します。
「案件探しの時間をスキルアップや仕事に費やしたい」「スキル・経験はあるが案件を探すのが苦手」という方はぜひご利用ください。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)