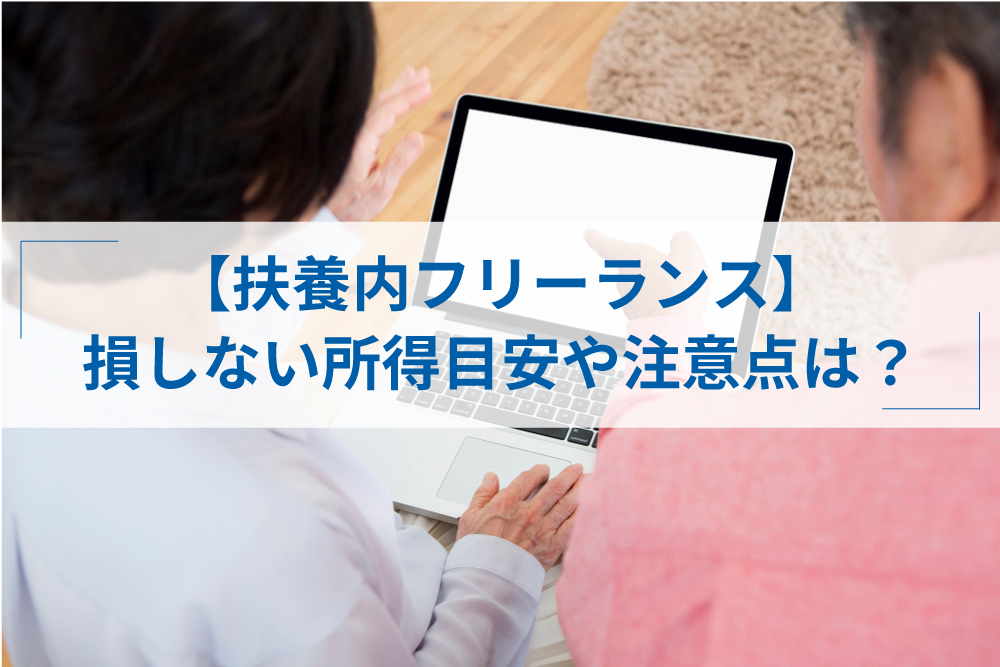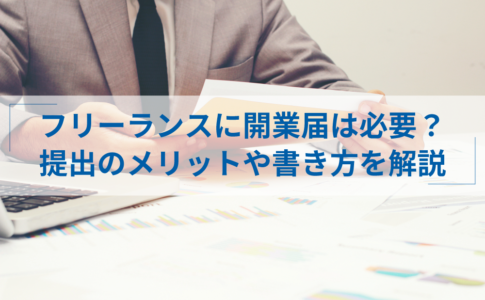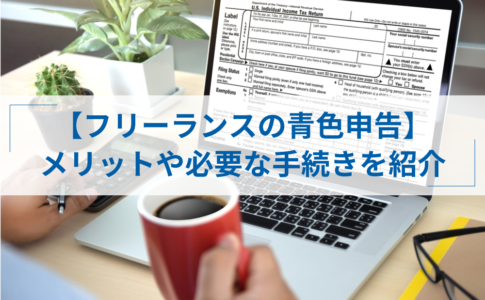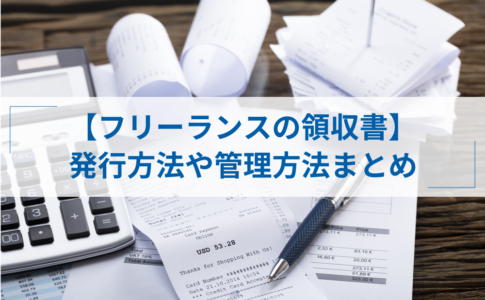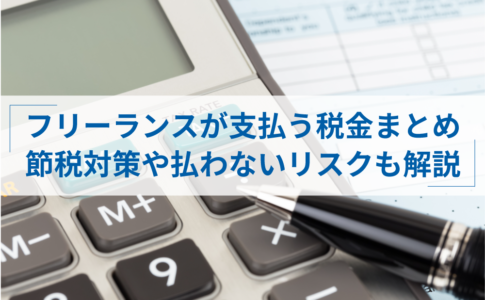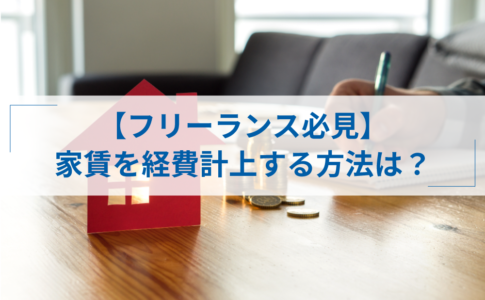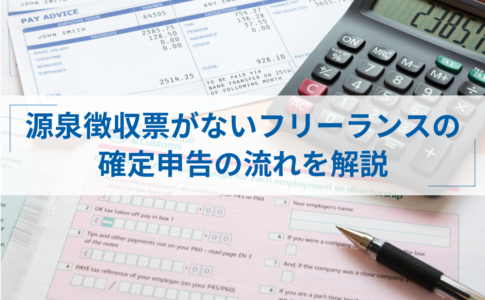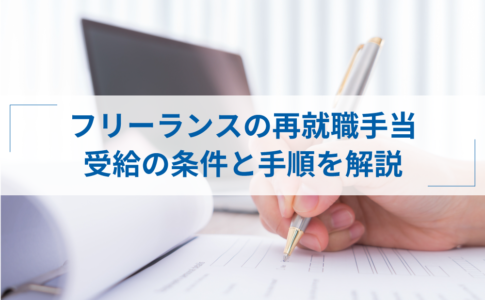こんにちは、ITプロマガジンです。
家計を主に担っている配偶者がいる人で、これからフリーランスとして働こうとしている際に悩むテーマの1つが「扶養の範囲内で働くかどうか」ではないでしょうか。「扶養内で働いた方がよいと聞いたけれど本当?」「いくら程度稼ぐと扶養から外れるの?」などの疑問を持っている人もいるかもしれません。フリーランスであれば仕事量を調整しやすいので、扶養内がお得であれば、そうしたいところです。
そこでこの記事では、扶養控除の概要と、働きながらも扶養内の立場を維持できる条件や目安の収入金額、フリーランスが扶養内で働くメリット・デメリットなどについて解説します。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
フリーランスが扶養内で働くとはどういうことか

フリーランスとして扶養内で働くことを検討する際は、扶養という概念や社会保険の仕組みを理解することが欠かせません。ここでは、フリーランスが扶養内で働くか検討するうえで知っておきたい仕組みを解説します。
扶養親族として働くこと
フリーランスとして扶養親族の範囲で働く場合、税制上の扶養の仕組みを理解しておく必要があります。扶養親族とは、納税者と生計を共にし、一定の所得以下である親族のことを指します。
例えば、フリーランスが「親」の扶養に入る場合、扶養者である親が扶養控除を受けられ、家計全体の税負担を軽減できます。一方で、「配偶者」の扶養には入ることができず、税制上「扶養親族」にはなりません。
扶養控除を受けるためには、年間所得が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である必要があります。この金額を超えると扶養から外れ、扶養者の税負担が増えるため、フリーランスとして扶養内の立場を維持したい場合は所得の管理が重要になります。
社会保険の扶養内で働くこと
社会保険の扶養に入ると、健康保険料や年金保険料を自己負担せずに済みます。このため、フリーランスとして働きながらも、経済的な負担を抑えることが可能です。
扶養に入るための条件は、親や配偶者といった扶養者が勤務する会社の規模によって異なりますが、基本的には年間給与130万円未満が条件となります。
この年収を超えると、自身で国民健康保険や国民年金に加入しなければならず、保険料負担が発生します。そのため、扶養に入り続けたいなら、収入の見込みを立てたうえで「働く量の調整が必要かどうか」を慎重に検討することが重要です。
配偶者(特別)控除の範囲で働くこと
フリーランスが「配偶者控除」「配偶者特別控除」の範囲で働くことも、「扶養内で働く」と表現されることがあります。これは、フリーランス本人ではなく、その配偶者が税制上の控除を受けられる仕組みです。
配偶者控除を受けるには、フリーランスの年間所得が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である必要があります。一方で、配偶者特別控除は、年間所得が133万円以下であれば段階的に適用されるため、48万円を超えても控除を受けることが可能です。
社会保険の扶養とは別の制度であるため、フリーランスが自分で社会保険に加入しながらも、配偶者特別控除の対象となることができます。
所得はいくらまで?フリーランスが扶養内で働くための基準
フリーランスが配偶者の扶養に入るためには、稼ぐ金額を一定以下にしなければなりません。
「所得金額がいくらまでなら扶養に入れるのか」といういわゆる「所得の壁」「年収の壁」は扶養の種類や受ける控除の種類により異なり、次の通りです。
| 扶養親族 | 所得48万円まで |
| 配偶者控除(税法上の扶養) | 所得48万円まで |
| 配偶者特別控除(税法上の扶養) | 所得133万円まで |
| 社会保険上の扶養 | 年収130万円まで |
壁となる金額の違いだけでなく「所得」と「年収」の考え方も重要です。
事業所得と年収の考え方についても合わせて、詳しく確認していきましょう。
そもそもフリーランスの所得とは
フリーランスや個人事業主の所得とは、基本的には事業所得を指します。事業所得の計算方法は次の通りです。
フリーランスの場合、経費には地代家賃、水道光熱費、通信費、新聞図書費など15項目を計上できます。青色申告特別控除の金額は、最大65万円です。
なお、フリーランスで収入を得ながらアルバイトとしての「給与所得」、不動産運用による「不動産所得」もある場合は、これらも合計したものが所得となります。
給与所得と不動産所得の計算方法は、次の通りです。
- 給与所得=総収入-給与所得控除
- 不動産所得=総収入-必要経費-青色申告特別控除(青色申告する場合)
なお、その他の所得については合算不要な場合もあります。
扶養親族として働くための基準
フリーランスが扶養親族として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 配偶者以外の親族である
- 納税者と生計を共にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でない
なお「親族」とは、6親等内の血族および3親等内の姻族(配偶者の一方と他方の血族)を指します。
参考:No.1180 扶養控除 | 国税庁
配偶者(特別)控除の範囲内で働くための基準
フリーランスとして税法上の配偶者(特別)控除を受けられる範囲で働くためには、上で解説した事業所得を一定の基準以下に抑えなければなりません。事業所得だけを見ると少なく感じるかもしれませんが、収入に計算し直すと思っていたより余裕があると感じる人もいるでしょう。
詳しく解説します。
配偶者控除の適用基準
フリーランスとしての収入のみを得ている場合、配偶者控除の対象となるための基準は「事業所得が48万円以下」です。
収入で基準を考えるなら「事業所得48万円+青色申告特別控除の最大額65万円=113万円」に経費分を足した金額が配偶者控除の適用基準となります。
なお、配偶者控除で扶養者(納税者本人)に適用される控除額は、扶養者の合計所得により異なり次の通りです。
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(※) | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
参考:No.1191 配偶者控除 | 国税庁
配偶者特別控除の適用基準
配偶者特別控除とは、被扶養者の所得が配偶者控除の基準を超えている場合に適用されるものです。適用基準は「事業所得が133万円以下」です。
配偶者特別控除額は扶養される側の所得が増えるほど少なくなります。控除額が最大になるのは被扶養者の事業所得が95万円以下の時で、95万円を超えるとだんだん控除額が減り、133万円を超えると控除を適用できなくなってしまうのです。
ただし、事業所得は収入から青色申告特別控除や経費を引いたものです。
収入で考えるなら、配偶者特別控除額が最大になる収入の上限は「95万円+65万円=160万円」に経費分を加えた金額、配偶者特別控除が適用される収入の上限は「133万円+65万円=198万円」に経費分を加えた金額となります。
| 控除を受ける納税者の合計所得金額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ~900万円 | 900万円超 950万円以下 | 951万円超 1,000万円以下 |
||
| フリーランス本人の合計所得金額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 96万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
参考:No.1195 配偶者特別控除 | 国税庁
社会保険上の扶養内で働くための基準
社会保険上の扶養に入りながら働くためには、被扶養者の年収は130万円未満でなければなりません。ただし、60歳以上または障害者であれば年収の基準は180万円未満です。
上記に加え、扶養者である配偶者と同居しているなら扶養者の収入の半分未満、別居しているなら扶養者からの仕送り額未満という基準も設けられています。
配偶者控除や配偶者特別控除のような税法上の扶養ルールとは異なり、社会保険の扶養ルールは扶養者が加入している健康保険によって違ってきます。
「年収130万円未満」という条件も、経費などを差し引いた後の年収が130万円未満なのか、経費を引く前の金額が適用されるのかについて、扶養者が入っている保険の種類で変わってきます。
扶養内で働くフリーランスが損をしない所得金額の目安とは?
ケースバイケースですが、フリーランスが扶養内で働こうと思ったら、税法上の扶養ルールよりも社会保険上の扶養ルールである130万円未満を目安とするのがおすすめです。
所得税に関わる配偶者控除、配偶者特別控除はともに控除額は最大38万円で、仮に所得税率10%としても3.8万円の違いで、それほど大きな金額ではありません。
一方、社会保険については、扶養から外れれば扶養者の社会保険に入れず、フリーランス本人が国民年金と国民健康保険に加入して支払わなくてはなりません。国民年金保険料は年間最大約20万円、国民健康保険料は20万〜40万円(年齢や自治体によって異なる)程度が相場ですから、結構な負担です。
ちなみに、健康保険の加入条件となる130万円未満とは、加入時点での見込み収入(所得)額を指しますが、だいたい月額10万8,000円程度に抑えると扶養内に収まる計算になります。
フリーランスとして扶養内で働くメリット・デメリット
パートや契約社員として働く人が扶養内を意識するのはよく聞きますが、フリーランスが扶養内で働くには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
フリーランスとして扶養内で働くメリット
メリットとしてはもちろん、生計を共にしている配偶者の所得税や、自身の社会保険料の負担を軽減できるということです。配偶者の所得から扶養控除分を引けるので、翌年の住民税も抑えられます。
フリーランスは収入が不安定になりやすく、最初のうちはなかなか稼げないという人も多くいます。そこで、無理をせずにあえて扶養内になるように収入を抑え、配偶者控除などで家計の負担を減らすのも1つの手です。
フリーランスとして扶養内で働くデメリット
デメリットとしては扶養控除を受けるためには扶養内で働かなくてはならず、チャンスがあっても収入を増やせないという点が挙げられます。
例えば、青色申告で65万円の控除を受けたとしても、扶養内であり続けるには年間の事業所得を抑えなくてはなりません。フリーランスの場合、急に入ってきた仕事を断れない場合も多く、年間の事業所得を抑えるのが難しいケースもあるものです。
扶養内にしようと思うとせっかく魅力的な仕事の話があっても断る必要が出てきます。大きなプロジェクトの仕事が引き受けられず、いつまでたってもスキルアップが図れなくなってしまうかもしれません。
フリーランスとして扶養内で働く場合に必要な手続き

扶養内で働くために、事前に確認しておきたいことや準備すべきことをお伝えします。
配偶者の社会保険の被扶養者として申請する
配偶者の社会保険上の扶養に入る場合は、配偶者が勤める会社を通じて申請をします。
配偶者の会社に申し出れば、以下の書類を提出するよう求められるでしょう。
- 被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届
- 扶養者との続柄が確認できる書類
- 被扶養者の収入を確認できる書類
具体的にどのような書類を提出すればよいのかは状況などによっても異なるため、配偶者の勤務先からの案内に従ってください。
また、入籍を機に扶養に入る場合や配偶者と別居している場合、配偶者と内縁関係にある場合はさらに別の書類の提出が必要です。
これらの書類を配偶者の勤務先に提出すれば、そこから書類が日本年金機構や保険組合などに渡ります。
手続きが済むと配偶者の勤務先に保険証が届くので、受け取ってください。
「開業届」「青色申告承認申請書」の提出
確定申告には白色申告と青色申告がありますが、青色申告の方が控除額が大きく、事業所得を低く抑えられます。
青色申告で確定申告する場合は、税務署に「開業届」を出し「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。開業届は原則として開業後1ヶ月以内に、青色申告承認申請書は開業後2ヶ月以内か、申告したい年の3月15日までに提出する必要があるので注意してください。
確定申告の実施
確定申告は例年2月15日から3月15日に行われ、前年の1月1日から12月31日までの所得を申請します。前年に収入があった人は基本的にはこの期間に、税務署に対して所得額の申請をしましょう。
確定申告の方法としては税務署から書類をもらって記入をするか、税務署のホームページからe-TAXを活用して行います。
「確定申告書」に必要事項を記入のうえ、青色申告決算書、収支内訳書などを添えて提出します。
フリーランスが扶養内で働くためのポイント
扶養内で働きたいフリーランスにとって、案件の選び方や報酬形態の調整は非常に重要です。フリーランスが扶養内で働くためのポイントを紹介します。
案件応募の際に扶養内で働きたいことを伝える
扶養内で働くためには、クライアントに収入の上限を考慮してもらうことが重要です。特にフリーランス向けの案件では、稼働・成果物の量によって想定よりも収入が増えて扶養から外れてしまう可能性があります。
そのため、案件応募時に「扶養内で働きたい」旨を伝え、収入の調整が可能か相談することが大切です。エージェントを利用する場合は、登録時に上限収入をエージェント側に伝えておけば、条件に合った案件を紹介してもらえるため安心して仕事に取りかかれます。
報酬形態について相談する
フリーランスの報酬形態は、「固定報酬制」「時給制」「出来高制・成果報酬」などさまざまです。扶養内で働くためには、自身の収入が基準を超えないように、報酬形態を事前に調整することが重要です。
例えば、出来高制の場合、想定以上の成果を出すと扶養の範囲を超えてしまう可能性があるため、固定報酬型の案件を選ぶ方が安心です。また、時給制の案件では、月ごとの勤務時間を調整しながら働くことで、年収のコントロールがしやすくなります。
上記と同様、エージェントを利用する際は、報酬形態や上限収入についても伝えておきましょう。
状況に応じて報酬や稼動時間を相談する
扶養の条件を維持しながら働くためには、状況に応じて報酬や稼働時間を調整することも必要です。例えば、収入が扶養の上限に近づいた場合、一時的に稼働時間を減らして調整することが考えられます。また、年度ごとに契約内容を見直し、翌年の収入見込みを計算しながら働くことも重要です。
こうした調整をスムーズに行うためには、エージェントを活用して、扶養の範囲内で調整可能な案件を紹介してもらうとスムーズでしょう。
弊社ITプロパートナーズはIT/Web分野に強いフリーランス・副業エージェントです。専属スタッフが希望をヒアリングしたうえで条件に合う案件を紹介するため、安心して上限収入・稼働量のなかで働くことができます。条件があるなかで効率的に案件探しをしたい方はぜひご活用ください。
フリーランスと扶養の関係についてよくある疑問
ここまでフリーランスの扶養について確認してきましたが、扶養の制度は単純ではなく、さまざまな疑問・不安があるものです。ここではフリーランスと扶養の関係について、よくある疑問とその回答を紹介します。
開業届を提出すると扶養ではなくなる?
開業届を提出することで扶養から外れることはありません。扶養に入れるかどうかの基準は、あくまでも所得の金額です。
むしろ、開業届を出すことは扶養内で働くにあたってメリットになります。開業届を出して青色申告をすれば、所得の計算時に青色申告特別控除が適用されます。扶養に入りながら稼げる額が多くなるのです。
所得が扶養に入るための上限を超えにくくなりますし、配偶者特別控除を受ける場合は青色申告特別控除がある分所得が少なくなり、控除額が多くなる場合もあるでしょう。
青色申告と白色申告のどっちがよい?
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、扶養内で働くなら青色申告の方がおすすめです。
青色申告の場合、最大65万円の青色申告特別控除が適用され、その分扶養内で稼げる金額が多くなります。一方、白色申告では48万円しか控除を受けられません。
控除額が大きい方が扶養を外れるかもしれないという不安が少なくなるため、利用できる控除はできるだけ利用しておいた方がよいでしょう。
青色申告は白色申告よりも手間がかかりますが、会計ソフトなどを使えば負担を軽減できます。
パート・アルバイトとフリーランスの掛け持ちの場合の条件は?
フリーランスがパート・アルバイトと掛け持ちする場合、扶養内で働くためには全ての所得を合算したうえで基準を満たす必要があります。先述の通り、具体的には税法上の扶養では所得が48万円以下、社会保険の扶養では基本的に年収130万円未満が条件です。
なお、パート・アルバイトといった雇用契約の場合に一定の勤務条件を満たすと、勤務先の社会保険に加入する必要があります。週20時間以上の勤務、月収8.8万円以上、2ヶ月を超える雇用などの条件を満たすと、会社の健康保険・厚生年金への加入が必要です。この場合は扶養から外れますが、社会保険料の半分を会社が負担するため、手取りの減少を抑えつつ将来の年金受給額が増えるメリットがあります。
まとめ
本記事では、フリーランスが扶養内で働く方法と合わせて、税制上の扶養や社会保険の仕組みを解説しました。扶養内で働くためには、所得の上限を把握したうえで、報酬形態・収入を調整することが重要です。また、配偶者控除・配偶者特別控除、社会保険の扶養など、それぞれの基準を理解し、最適な働き方を選ぶことも欠かせません。
希望の稼働量や収入に合う案件を探す際は、エージェントを活用するとスムーズな可能性があります。ITプロパートナーズは、IT/Web業界に特化したフリーランスエージェントです。「週2〜3日の稼働OK」といった柔軟な働き方ができる案件も多く、専属スタッフが希望をヒアリングのうえでマッチする案件を紹介します。扶養の範囲内で無理なく働きたい方は、ぜひご活用ください。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)