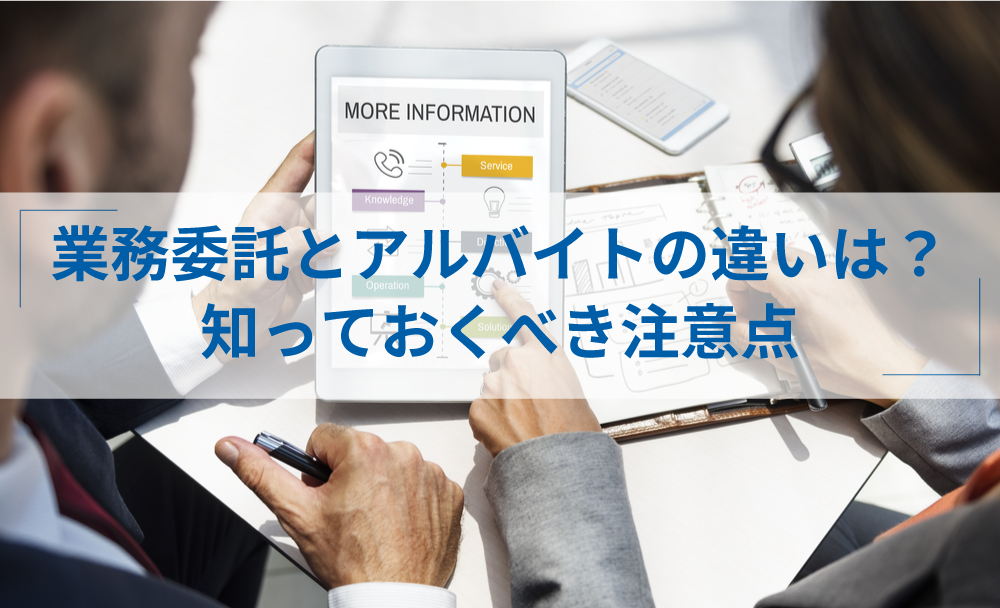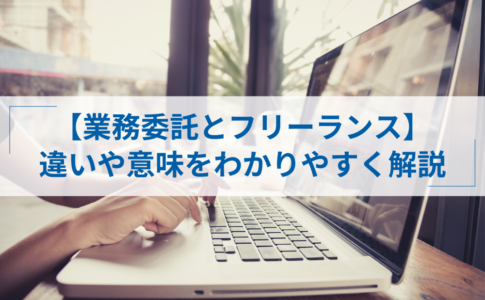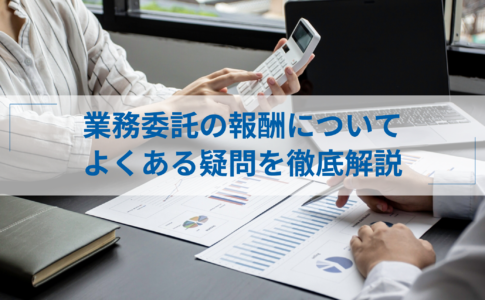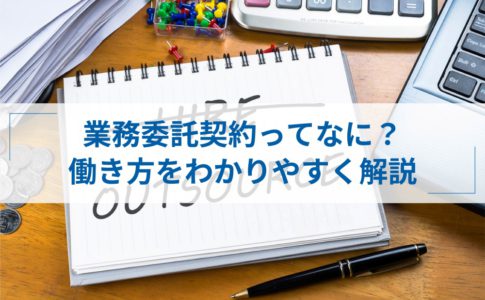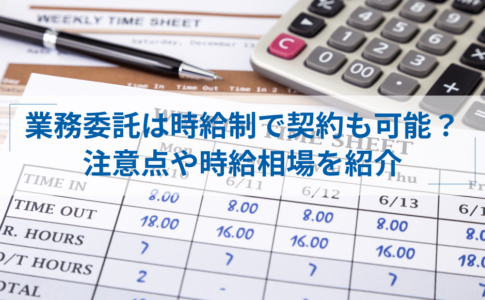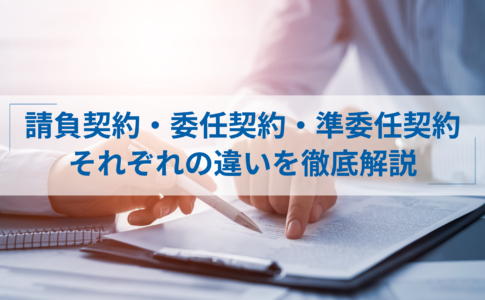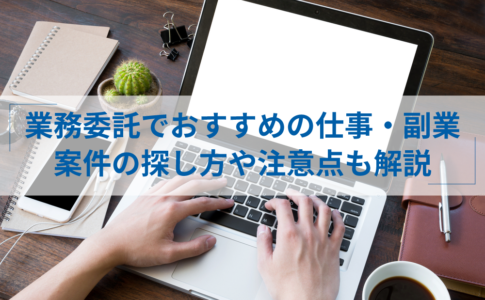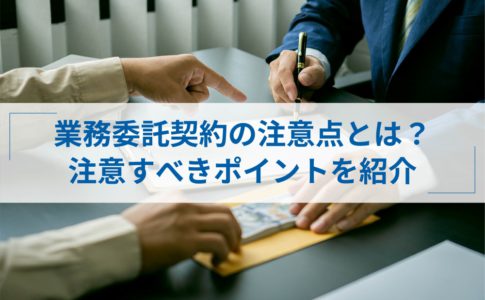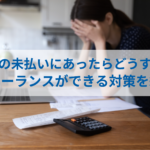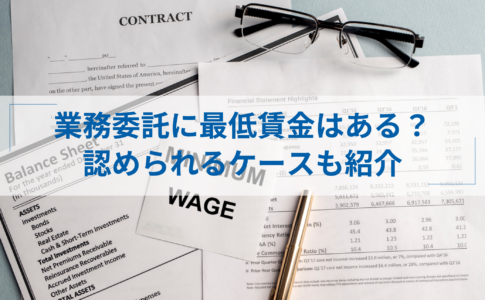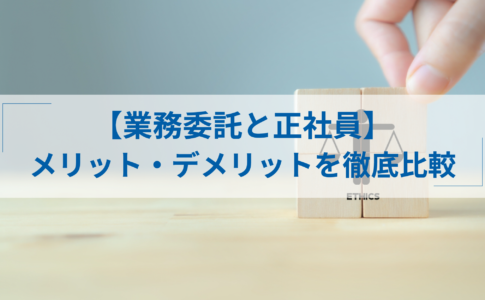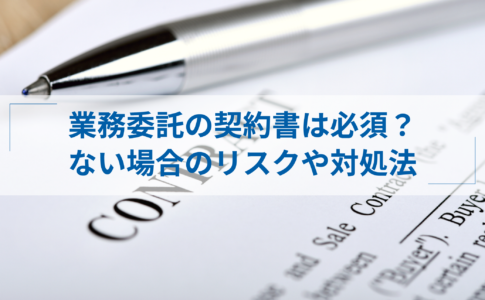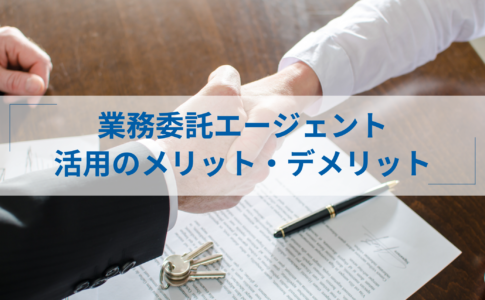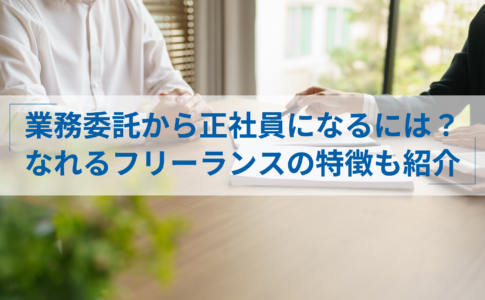こんにちは、ITプロマガジンです。
業務委託とアルバイトは、契約の形態や報酬の仕組み、社会保険や税金の取り扱いなど、基本的なルールが大きく異なります。フリーランスとして働く場合、業務委託とアルバイトの違いを正しく理解できていると、スムーズな手続きやトラブル防止につながります。
本記事では、業務委託とアルバイトの違いや、それぞれの特徴やメリット・デメリット、向いている人のタイプまで詳しく解説します。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
業務委託とアルバイトの違いとは?
業務委託とアルバイトは、労働基準法や社会保険、年末調整などさまざまな部分で違いがあります。両者の違いを簡単にまとめると以下の通りです。
| 業務委託 | アルバイト | |
|---|---|---|
| 労働基準法の対象 | ×対象外 | 〇対象 |
| 会社の社会保険への加入 | ×不可 | 〇可 |
| 年末調整の対象 | ×対象外 | 〇対象 |
| 所得の種類 | 事業所得・雑所得 | 給与所得 |
| 契約の種類 | 請負契約・委任契約・準委任契約 | 雇用契約 |
| 報酬・給与の対価 | 成果物・業務の遂行 | 労働・時間 |
以下、「労働基準法」「社会保険」「年末調整」「所得の種類」「契約の種類」「報酬・給与の対価」の6つの視点で詳しく解説します。
労働基準法の適用対象になるかどうかの違い
まずは、労働基準法の適用対象になるかどうかの違いです。アルバイトは雇用契約に基づいて働くため、労働者として労働基準法の適用対象となります。例えば最低賃金や労働時間、有給休暇などが法的に保障される立場です。
一方、業務委託は「業務委託契約(請負契約や準委任契約)」に基づく働き方です。法律上、アルバイトで働いている人とは異なり、労働者ではなく「個人事業主」という扱いになります。そのため、適用対象にはなりません。
なお、フリーランスと業務委託の違いについては以下の記事で解説しているので、こちらも参考にしてください。
会社の社会保険に加入できるかどうかの違い
会社の社会保険に関しても、業務委託とアルバイトで大きな違いがあります。アルバイトとして働く場合、労働時間や日数などの条件を満たせば、会社の社会保険に加入できます。例えば健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険などです。健康保険料と厚生年金保険料は、会社との折半になります。
一方、業務委託は雇用契約ではないため、会社の社会保険に加入できません。フリーランスや個人事業主として働く人は、自分で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料も全額自己負担です。万が一の備えは自分で行う必要があります。
年末調整の対象になるかどうかの違い
年末調整の対象になるかどうかも、業務委託とアルバイトの大きな違いです。年末調整とは、1年間の所得に応じた所得税の過不足を調整する作業です。アルバイトとして働く場合は、会社が本人の代わりに年末調整を行ってくれます。
業務委託で働く人は、会社に雇用されていないため、年末調整の対象外です。源泉徴収されている場合でも、年間の所得や経費を自分で整理し、確定申告をしなければなりません。つまり、税務処理の負担がアルバイトよりも大きくなる可能性があります。
所得の種類の違い
業務委託とアルバイトは、たとえ同じ仕事をしても、所得の種類(税法上の所得の分類)に違いがあります。アルバイトとして得た収入は、会社から支払われる「給与」であり、税務上は「給与所得」として扱われるのが一般的です。
一方、業務委託で受け取るお金は、「給与」ではなく「報酬」です。本業として継続的に活動している場合は「事業所得」、副業や単発的な業務であれば「雑所得」に分類されます。
契約の種類の違い
業務委託とアルバイトは、契約の種類にも違いがあります。前述のように、アルバイトとして働く場合、企業と個人は「雇用契約」を結びます。雇用契約とは、労働に従事し、報酬を受け取ることを約束する契約です。企業は労働者に対して、業務内容や進め方、勤務時間などを指示する権限を持ちます。つまり、労働者は企業の「指揮命令下」で働く立場です。
一方、業務委託で働く場合、企業と個人は「業務委託契約」を結びます。業務委託契約は、雇用契約とは異なり、「請負契約」や「委任契約(準委任契約)」といった形式が一般的です。企業と個人の間に指揮命令関係がなく、契約にもよりますが業務の進め方や働く時間・場所などは原則として個人の裁量に委ねられます。特に「請負契約」の場合は、社内規則に従う義務もなく、拘束時間がないことも普通です。
報酬・給与の対価の違い
報酬・給与の対価の違いも明確です。アルバイトの場合は、雇用契約に基づき、働いた時間や日数に応じて給与が支払われます。例えば「時給1,200円で1日5時間働いたので6,000円」といった計算です。同じ時間でどれだけ効率良く業務をこなしても、給与は基本的に変わりません。
一方、業務委託では、成果物の納品や業務の遂行そのものに対して報酬が支払われます。例えばITエンジニアの場合は、システムやアプリケーションの開発といった成果物を納品し、その対価として報酬を受け取るという形です。つまり「何を納品したか」「どの業務を完了したか」が報酬の根拠になります。ただし、契約形態の種類によっては、稼働時間に応じた報酬になることもあります。
業務委託契約の種類
業務委託は、大きく分けて「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」の2つの契約形態が存在します。以下、それぞれ契約の性質や報酬発生のタイミングなどを解説します。
請負契約
請負契約とは、業務委託契約のうち、完成された成果物を納品した時点で報酬が発生する契約です。例えばWebサイト制作やアプリケーションの開発、ロゴデザインなどが該当します。
業務を請け負う受注者は、委託された業務を完成させるため、必要な設備や環境を整える必要があります。納期や品質の責任も、受注者に強く求められるのが一般的です。ミスがあれば修正が必要になり、もし重大な欠陥があった場合は損害賠償につながる可能性もあります。
請負契約では、委託された成果物が完成される前であれば、依頼者側から一方的に契約を解除できます。契約を解除されて仕事がなくなっても保証はなく、全てが自己責任です。
委任契約・準委任契約
委任契約(準委任契約)は、業務の遂行自体を目的とした契約です。
- 委任契約:弁護士の代理業務など、法律行為に関する業務
- 準委任契約: IT保守、経理代行、システム運用など、法律行為以外の業務
両者の違いは、法律行為があるかどうかです。フリーランスや外部パートナーとして業務を受託する場合は、基本的に「準委任」に該当することを前提するとよいでしょう。いずれも「請負契約」とは異なり、成果物の完成を目的とはしていません。完成責任がない代わりに、誠実に業務を遂行する義務(善管注意義務)を負います。
業務委託で働くメリット・デメリット

業務委託契約を結んで働く場合、メリットとデメリットの両方があります。ここでは、業務委託契約のメリットとデメリットの両方を確認しましょう。
業務委託で働くメリット
業務委託契約は、融通がききやすい点が大きなメリットです。業務委託契約のメリットについて、具体的に解説します
働き方の自由度が高い
業務委託で働くメリットは、働き方の自由度が高い点です。特に請負契約では、「いつ、どこで、どのように作業を進めるか」は、原則として受託者の自由となります。成果物を納品さえすれば、その過程は問われません。平日昼間だけでなく、夜間や土日など、自分のライフスタイルに合わせて働けます。
業務委託は、雇用契約とは異なり、会社の就業規則に従う義務もありません。服装や勤務場所、ツールの使い方なども自分で選べます。仕事の進め方も自分で決められるため、柔軟性を重視したい人に向いている働き方です。
収入アップしやすい
業務委託は、成果に応じて報酬が支払われる仕組みのため、「アルバイトと比べて収入を増やしやすい」というメリットがあります。アルバイトは時給制が一般的で、収入を増やしたければ働く時間を増やすしかありません。とはいえ、1日の労働時間や週のシフトには限度があります。
一方、業務委託は、納品した成果物や対応した業務の量・質に応じて報酬が増える仕組みです。そのため、短時間で効率的に成果を出せれば、多くの報酬を得られるチャンスもあります。スキルや専門性が高ければ、より単価の高い仕事を受注でき、収入を大きく伸ばせるかもしれません。スキルや専門性が高ければ、単価の高い仕事も受注できます。
人間関係のストレスを避けやすい
業務委託は、アルバイトと比べて人間関係のストレスを感じにくい働き方です。アルバイトの場合、職場の上司や同僚と毎日顔を合わせて働くため、人間関係の悩みを抱えるケースも少なくありません。勤務シフトや仕事内容も、周囲と細かく調整する必要があり、それがストレスに感じる場合もあります。
しかし業務委託は、基本的に業務の成果や遂行内容を重視した関係性です。職場での人間関係にこだわる必要がない点で、アルバイトとは違いがあります。連絡や打ち合わせもオンライン中心で、必要最低限のやり取りになるため、余計なストレスを避けたい人に適した働き方です。
業務委託で働くデメリット
業務委託契約で仕事をする際は会社による保証がなく、全てが自己責任となります。ここでは、業務委託契約のデメリットについて確認しましょう。
労働基準法の適用外になる
業務委託で働く場合、労働基準法の保護を受けられないのが大きなデメリットです。
アルバイトなどの雇用契約では、最低賃金や労働時間、休憩、残業代、有給休暇などが法律によって守られています。しかし業務委託契約は、個人事業主としての契約であり、こうした法的保護の対象外です。例えば作業に時間がかかり、時給換算で最低賃金を下回っても、違法にはなりません。
さらにアルバイトであれば、雇用契約に基づき、十分な理由なく一方的に解雇するのは「不当解雇」として問題になります。しかし業務委託の場合は、契約内容やプロジェクトの状況によって、一方的に契約解除される可能性もあります。働く側が弱い立場になりやすい点には注意が必要です。
自分で仕事を獲得する必要がある
業務委託で働くには、自分で仕事を探して獲得するスキルや行動力が求められます。アルバイトであれば、一度採用されれば契約期間中は基本的に安定して仕事があります。会社の倒産など、よほどの事情がない限り、自分から仕事を取りに行く必要はありません。
しかし業務委託の場合は、自分でクライアントを見つけ、案件を受注しなければ収入はゼロになります。継続案件があっても、契約が終了すれば次の仕事を確保しなければなりません。常に営業活動や仕事を紹介してもらうための人脈作りが求められます。
営業が苦手な人や、仕事探しに不安を感じる人は、業務委託案件を紹介してくれるエージェントを活用するなどの工夫が必要です。
税金・保険関係の手続きは自分で行う必要がある
業務委託契約で仕事をする場合、税金や保険に関する手続きも自分で対応しなければなりません。慣れればそれほど難しい手続きではありませんが、さまざまな取り決めを理解する必要があります。手続きの期限も決まっているため、着実に対応することが大切です。
企業と雇用契約を結んで働いていれば、税金や保険の手続きは基本的に企業が対応してくれます。業務以外の部分にかかる手間は、アルバイトや正社員のほうが少なめです。
自己管理が必要になる
働く時間や場所を細かく指定されない業務委託契約では、自己管理が求められます。業務委託契約で報酬を得るには、成果物や労働時間に対して責任を持たなくてはなりません。体調や業務量のバランスを見て無理なく稼働しないと、契約を守れなくなってしまいます。
必要に応じて、打診された仕事を断る選択肢も持っておかなくてはなりません。自己管理を徹底して、納期や品質を守って働きましょう。
アルバイトとして働くメリット・デメリット
アルバイトをすると、業務委託契約を結んで働く場合と比べてどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。ここでは、それぞれについて説明します。
アルバイトとして働くメリット
アルバイトをするメリットは、主に下記の3点です。
- 収入が安定しやすい
- 就業開始・終了が決まっている
- 単純作業の仕事もある
安定性・規則性は、業務委託に対するアルバイトのメリットといえるでしょう。
収入が安定しやすい
収入が安定しやすいという点は、収入アップを目的にアルバイトしたい人にとっては魅力的でしょう。
業務委託では高収入を稼げるチャンスがある反面、仕事を獲得できなければ収入がゼロになる可能性もあります。そのためどうしても安定性に欠けてしまいます。一方で、アルバイトは出勤して決められた業務をこなしていれば、契約に従って給料を得られます。「何時間働けばいくら稼げるのか」があらかじめ分かっているため、望む収入を得られるように勤務を調整することも可能です。
就業開始・終了が決まっている
アルバイトでは就業開始・終了の時間がはっきり決まっているため、オン・オフが切り替えやすいというメリットもあります。
業務委託では基本的に勤務時間を指定されないため、始業・終業という考え方がありません。適切に自己管理・スケジュール管理していないと、休みや休憩時間など「オフ」がない状態になることが多々あります。場合によっては、納期に間に合うよう長時間連続で仕事をせざるを得ないことも。一方、アルバイトでは、たとえ多少の残業があっても、仕事が終わればオフに入れます。
特に、会社員のかたわら副業としてアルバイトをする人は、本業との切り替えをしやすく心身の健康も保ちやすいでしょう。
実績・スキルなしでもできる仕事が多い
未経験者でも採用されやすい仕事が多いのも、アルバイトとして働くメリットです。例えば接客業や軽作業、飲食店などでは、「未経験歓迎」「学歴・職歴不問」といった求人が数多くあります。必要な知識は、勤務開始後にOJT(現場研修)で教えてもらえる場合がほとんどで、事前に何かを詳しく勉強する必要はありません。
一方、業務委託の場合、未経験からのスタートはハードルが高くなります。クライアント側も成果を前提に契約するため、経験・実績を重視する傾向が強いからです。「まずは働きながら経験を積みたい」「いろいろな仕事を試したい」と考えている人にとっては、アルバイトが向いています。
アルバイトとして働くデメリット
アルバイトをするメリットは、主に下記の3点です。
- 勤務時間・場所の縛りがある
- 給与アップがしにくい
- スキルアップが難しい
アルバイトのメリットである安定性が、マイナスの効果を生む場合もあります。
勤務時間・場所の縛りがある
多くのアルバイトでは勤務時間・勤務場所に縛りがあるため、「短時間だけ働きたい」「スキマ時間に働きたい」などの自由がききにくいといえます。
アルバイトではシフト制が多く、始業・終業と勤務時間が決まっています。また、オフィスや店舗に出勤する必要があり、リモート不可の仕事も多いものです。そのため、人によっては仕事先が見つからなかったり、希望の時間数働けなかったりする可能性があります。
給与アップがしにくい
アルバイトでは、安定収入が得やすい分、給与が上がりにくい傾向があります。
業務委託のメリットでもお伝えした通り、アルバイトでの昇給は少額であることがほとんどで、大幅な収入アップはそうそうあり得ません。昇給がないアルバイトも多く、たとえ昇給があっても、「半年ごと」「1年ごと」など少しずつ上がっていくのが一般的です。一生懸命に働いても収入が上がらないことは、アルバイトのデメリットといえるでしょう。
スキルアップが難しい
アルバイトでは特別なスキルが必要ないものが多く、任される仕事も比較的難易度が低いものが多く見られます。また、仕事に慣れても、アルバイトでは契約の範囲内でしか働けません。そのうえ、時給制で給料が決まるため、スキルを高めるモチベーションを保てない人もいるでしょう。
業務委託とアルバイトの違いについて知っておきたい注意点

業務委託やアルバイトで働くうえでは、気をつけるべきこともあります。トラブルに巻き込まれずスムーズに働くためには、注意点を把握するのが重要です。以下、業務委託とアルバイトの違いについて知っておきたい注意点を解説します。
偽装請負を避ける必要がある
業務委託で働く場合に特に注意したいのが、「偽装請負」と呼ばれる働き方です。偽装請負とは、本来は雇用契約であるべき働き方を、形式上だけ業務委託契約としている状態を指します。
そもそも業務委託契約では、働く時間・場所・方法を受託者が自由に決められるのが原則です。しかし実態が「会社の社員のように働く」ものであれば、雇用契約とみなされる可能性があります。
例えば「会社の社員と同じように勤務時間が指定されている」「作業指示や勤務内容を細かく会社側が管理している」「勤務場所が常に指定され、自由がない」などの場合は、偽装請負に該当する可能性があるため、注意してください。
契約書の内容をよく確認することが重要
業務委託で働く際は、契約書の内容を事前に確認するのが重要です。業務委託契約では、労働基準法の保護を受けられないため、自分の権利・義務を契約書の内容に基づいて守る必要があります。
業務委託契約を結ぶ際は、「契約書を交わすこと」「内容を理解すること」「不明点があれば質問すること」の3点を徹底してください。書面が存在しない場合、証拠が残らないため、トラブルの解決が難しくなるリスクも高まります。
業務委託契約書の書き方については、以下の記事を参考にしてください。
業務委託とアルバイトはそれぞれどんな人に向いている?
業務委託とアルバイトは、それぞれ異なる特徴があります。それぞれに向いているのは、どのような人なのでしょうか。ここでは、業務委託とアルバイトに向いている人の特徴について説明します。
業務委託に向いている人
業務委託に向いている人は、以下の通りです。
- 専門的なスキルを持っている人
- 成長意欲がある人
- 自分のペースで働きたい人
専門的なスキルを持っている人
業務委託を依頼する企業は、自社では対応できない特別なスキルを持つ人を探しています。そのため、一般的なビジネススキルよりも、専門的なスキルを持つ人が重宝されるでしょう。
また、業務委託には、1人で作業を進めるケースも多く、アルバイトのように丁寧にやり方を教えてもらえるとは限りません。つまり、即戦力レベルの専門的なスキルがなければ、業務委託は難しいといえます。
成長意欲がある人
業務委託は、成長意欲がある人にもおすすめです。常にレベルアップを目指している人ならスキルを高めやすく、実績も増やせます。経験が増えるにつれ、条件の良い案件をスムーズに獲得できるでしょう。
また、業務委託を依頼する企業は、レベルの高い人材を求めるもの。成長意欲があって日々勉強や情報収集できる人は、活躍できます。
自分のペースで働きたい人
業務委託は働き方の自由度が高いため、自分のペースで働きたい人にも適しています。自己管理ができれば、自分のライフスタイルや都合に応じた柔軟な働き方を実現可能です。育児や介護をしていて臨機応変にその日の働き方を決めたい人から、仕事量をどんどん増やしたい人まで、業務委託なら融通をきかせて働けます。
アルバイトに向いている人
以下の人は、アルバイトに向いています。
- 時間的に余裕があり決まった時間に働きたい人
- 福利厚生を重視したい人
時間的に余裕があり決まった時間に働きたい人
アルバイトはシフト制で働く時間がきっちり決められている場合が多く、決まった時間に働きたい人に向いています。時給で給料が計算されるため、働く時間を決めれば得られる収入を計算可能です。
なお、本業の合間に副業として働きたい人は、働ける時間を見極めてから応募しましょう。平日の夜や土日のみなど、本業に支障が出ない時間に働くようにしてください。
福利厚生を重視したい人
福利厚生を重視したい人もアルバイト向きです。労働者の確保のため、社会保険などの法定福利厚生とは別に、企業独自の福利厚生を充実させる企業が増えました。食堂やまかない、クーポンや割引、予防接種や健康診断などの健康支援といったように、さまざまな福利厚生が用意されています。
どっちがいい?業務委託とアルバイトで迷ったときの選び方

業務委託とアルバイトのどちらかを選択するか迷った場合は、自分にとっての優先順位を考えてみましょう。稼ぎたい金額・働き方・自分のスキルを活かして働ける可能性、などが仕事選びのポイントです。
稼ぎたい金額で判断する
高収入を目指すなら業務委託が向いています。業務委託はスキルしだいで高単価な案件を受けられるためです。また、自己管理できる範囲であれば、仕事量を増やせば報酬も増えます。業務委託は受ける仕事を自由に選べるため、自分のスキルを活かせる分野で、高単価な案件を探してみましょう。
また、主婦など扶養内で働きたい人には、働く時間から給料を計算できるアルバイトが向いています。
働き方で判断する
働き方を重視して仕事を選ぶ人もいます。例えば、自由度が高い働き方をしたいなら、業務委託がおすすめです。また、メリハリのある働き方を望む人には、決まった時間に働けるアルバイトが向いています。
また、在宅での働き方を希望するなら、アルバイトより業務委託として働くのがよいでしょう。アルバイトは比較的出勤する案件が多いので、在宅案件を探している人は見つけるのが難しいかもしれません。
保有スキルで判断する
専門的なスキルがない場合は、アルバイトが無難です。上述したように、アルバイトには特別なスキルが必要ないものが多く見られます。未経験でも安定した働き方ができる点は、アルバイトの大きなメリットといえるでしょう。
一方で、前職のスキルを活かして働きたい場合は、専門スキルが必要な業務委託の案件を選ぶのがおすすめです。例えば、事務やデスクワークの経験があれば、事務の業務委託案件を選ぶといったような形です。「どんな経験を活かすのか」「仕事で使えるスキルは何か」を明確にしましょう。
業務委託とアルバイトで掛け持ちは可能?
業務委託とアルバイトで掛け持ちは可能です。例えば、業務委託契約で働くフリーランス(個人事業主)をしながら、アルバイトをしている人もいます。
業務委託とアルバイトを掛け持ちする際は、確定申告のやり方に注意が必要です。確定申告の際は、アルバイト先から源泉徴収票を受け取ります。フリーランスとして得た利益は事業所得、アルバイトで得た利益は給与所得として申告しましょう。フリーランスでアルバイトしたい人は、以下の記事も参考にしてください。
まとめ
自由度が高くスキルを活かせる働き方を望む人には、業務委託が向いています。一方で、安定した収入や労働環境を重視したい人にはアルバイトがおすすめです。「自分がどう働きたいのか」「どのような環境を求めるのか」によって最適な選択が変わります。
業務委託で働く際は、契約内容や税務・保険の対応、偽装請負などの注意点を理解するのが重要です。契約書のチェックや、信頼できる取引先選びも、トラブル防止につながります。業務委託とアルバイトの違いを、今一度整理しましょう。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)