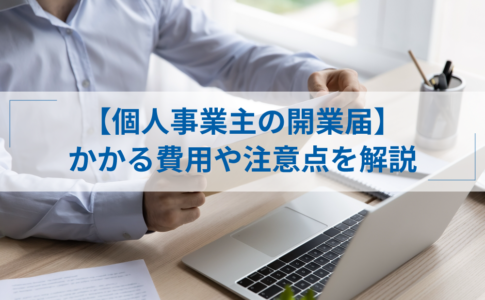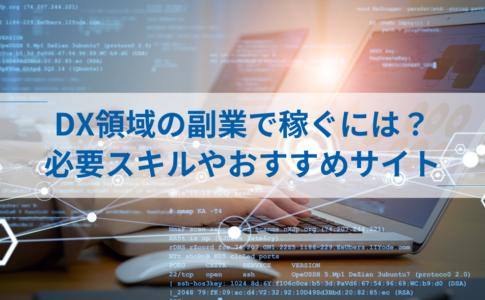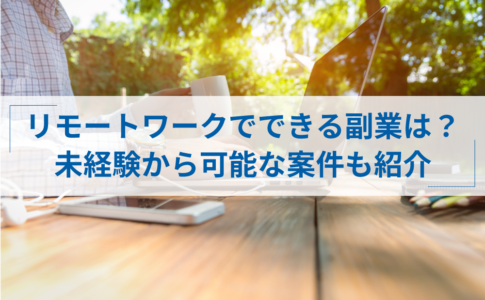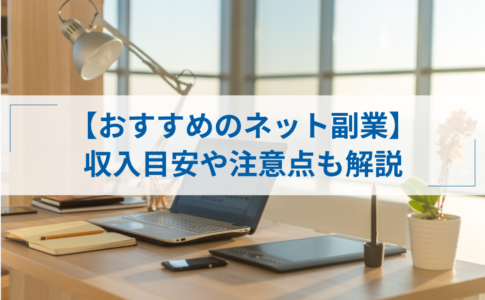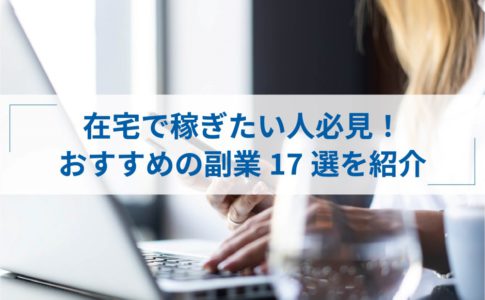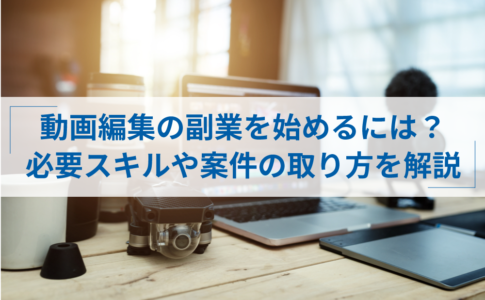こんにちは、ITプロマガジンです。
会社員として働きながら個人事業主としても活動するのはメリットが大きく「最強」と言われることもあります。
「会社員と個人事業主は掛け持ちできるのか?」「具体的にどのようなメリットがあるのか?」「デメリットや注意点はあるのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、会社員と個人事業主を掛け持ちするのが最強と言われる理由や、具体的なメリット・デメリット、手続きまで詳しく解説します。会社員と個人事業主の両立にチャレンジしようか検討している方はぜひご覧ください。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
会社員が兼業・副業で個人事業主になることは可能

結論として、会社員でありながら個人事業主として兼業・副業を行うことは法律上問題ありません。
ただし、企業の就業規則によって副業が禁止されている場合や、勤務先と利益相反になるケースでは制約が生じるため、事前の確認が必要です。
「個人事業主」という言葉にもある「事業」は、国税庁の定義によると、対価を得て行われる資産の譲渡や役務の提供を反復・継続・独立して行うこととされています。そのため、一度限りの単発収入であれば事業には該当しませんが、継続的に仕事を受ける場合は事業として扱われる可能性が高いです。
また、会社員が個人事業主として活動を開始した場合、事業の開始から1ヶ月以内に「開業届」を税務署へ提出する義務があります。開業届を提出することで青色申告が可能になり、特別控除を受けられる点がメリットです。
会社員と個人事業主の掛け持ちは最強?主なメリット
会社員と個人事業主を掛け持ちするのは、収入面・キャリア面の両方で大きなメリットがあります。ここでは、掛け持ちの主な利点を6つ紹介します。
事業に関する支出を経費にできる
個人事業主として活動すれば、通信費、交通費、機材費、広告費といった事業に必要な支出を経費として計上できます。
これは、会社員のみで働いている場合には得られない大きなメリットです。例えば、ライターとして副業をしている場合、取材のための交通費や購入した書籍代も経費になります。
経費を計上できると、所得税や住民税の負担を軽減できます。通常、会社員の給与からは所得税が源泉徴収されますが、個人事業主として経費を適切に計上すれば、課税所得を抑えられ、節税対策としても有効に活用できます。
損益通算・損失繰越ができる
個人事業で赤字が出た場合、給与所得と損益通算できるというメリットがあります。
損益通算とは、ある種類の所得の赤字を、他の所得と相殺する仕組みです。例えば、個人事業で赤字になった場合、その損失を会社員としての給与所得から差し引くことで、所得税や住民税の節税につながります。
さらに、個人事業主として青色申告をする場合、損失が出れば3年間繰り越しが可能です。翌年以降に利益が出た際、「損失の繰越控除」として、その過去の赤字と相殺することで課税所得を減らせます。
開業初期は設備投資などの支出がかさむことが多く、損益通算や損失繰越の仕組みを上手く活用すれば、恩恵を受けやすいのです。
収入源の多様化につながる
会社員の安定収入に加えて、個人事業での収入を得ることで、経済的に安定します。これは単に収入を増やすだけでなくリスク分散の観点でも有効で、会社の業績悪化やリストラなど、会社員のリスクを軽減することが可能です。
また、会社員と個人事業で異なる分野の仕事を選ぶと、さらにリスクヘッジになります。例えば、会社ではエンジニアとして受託開発を行い、個人事業ではWebアプリを開発して課金収入を得るといった形なら、一方の市場が不調でも別の収益源を確保できます。
自身の裁量で働ける
会社員として働く場合、業務方法や勤務時間は基本的に会社の指示に従う必要があります。一方、個人事業主としての仕事は、自分のペースで案件を選び、作業時間を自由に決められる点がメリットです。
特に、会社の組織運営や上司の意向に縛られることにストレスを感じている場合、個人事業の裁量の大きさは魅力でしょう。例えば、副業でライティングやデザイン業務を請け負う場合、案件数が多いため報酬・納期面で条件に合う案件を見つけやすい傾向にあります。
会社の福利厚生・社会保険を活用しながら働ける
会社から独立すると、会社の福利厚生を受けられなくなり、住宅補助・各種手当・健康保険の会社負担分なども受けられなくなります。しかし、会社員のまま個人事業を兼業すれば、こうした恩恵を維持しながら、柔軟に働くことが可能です。
例えば、会社の健康保険に加入していれば、健康保険料や厚生年金保険料の半額を会社が負担するため、フリーランスのみで活動する場合と比べてコストを抑えられます。さらに、福利厚生もそのまま活用でき、会社員と個人事業主の「いいとこ取り」ができる点も魅力です。
独立の準備になる
会社員のうちに個人事業主として活動を開始すれば、スムーズに独立の準備ができます。個人事業主として本格的に独立するには、開業届の提出、青色申告承認申請、確定申告といった手続きが必要です。また、クライアントの開拓や案件の契約交渉、売上管理など、会社員とは異なるスキルも求められます。
副業として個人事業をスタートしておけば、こうした手続きや運営の実務に慣れておき、独立のハードルを大幅に下げることが可能です。さらに、会社員の間に事業を軌道に乗せられれば、退職後すぐに安定した収益を確保しやすくなり、独立時のリスクを最小限に抑えられます。
会社員と個人事業主を掛け持ちするデメリット

会社員と個人事業主を掛け持ちすると、いくつかデメリットもあります。ここでは主なものを紹介します。
経理・税務処理の負担が発生する
個人事業主として活動する場合、確定申告を行う必要があるため、売上や経費の記録、帳簿の作成といった経理業務が発生します。
給与所得のみの場合は年末調整と、必要な場合のみの確定申告で税務処理が完結しますが、個人事業主になると税務の知識を学び、帳簿付けを行う必要があるのです。
会計ソフトを活用すれば負担を軽減できますが、それでも会計知識やソフトの操作方法を理解する必要はあります。特に本業の会社勤めと並行して行う場合はより負担が大きくなる可能性があるでしょう。
退職時に失業給付を受けにくい
会社員として雇用保険に加入していると、退職後に一定の条件を満たせば失業手当(基本手当)を受給できます。しかし、この制度は求職活動を行っているものの就職できていない人を対象としており、個人事業を行っている場合は「失業状態」と見なされず、給付を受けることは難しいとされています。
そのため、会社員としての退職後に失業手当を受けながら個人事業を軌道に乗せるという選択肢は取りにくい点に注意が必要です。万が一、退職を検討している場合は、事前にハローワークや社会保険労務士に相談し、受給できる要件を確認しておくとよいでしょう。
過労になる恐れがある
会社勤めに加えて個人事業を行うと、単純に労働時間が増加するため、適切にスケジュールを管理しなければ過労や睡眠不足につながるリスクがあります。特に、本業の勤務時間が長かったり、個人事業の案件が増えすぎたりすると、十分な休息が取れず、両方の仕事のパフォーマンスが低下しかねません。
本業の業務に支障をきたしたり、体調を崩したりするのは本末転倒です。そのため、掛け持ちをする場合は、働く時間をコントロールし、負担が大きくなりすぎないよう調整することが重要です。
会社員と個人事業主の掛け持ちに向いている人の特徴
会社員として働きながら個人事業主としても活動するには、時間管理や仕事の進め方を工夫するスキルが求められます。ここでは、掛け持ちに適した人の特徴を解説します。
自己管理ができる
まずは、自己管理能力が重要です。
会社員と個人事業を両立するためには、仕事のスケジュール管理やタスク整理を徹底する必要があります。本業の業務に加えて、個人事業の案件探し、クライアントとの交渉、契約手続きなども行うため、適切な時間配分が求められます。
また、個人事業主として活動する以上、税務処理や確定申告も行う必要があります。売上・経費の記録を怠ると、後々の手続きが煩雑になり、税務リスクが発生しかねません。さらに、個人ビジネスでは、マーケティングやブランディング戦略を考え、安定的に収益を得る仕組みを作ることも求められます。
こうした多岐にわたる仕事をこなすためには、自己管理を徹底し、計画的に行動する力が不可欠です。
適応力が高い
適応力が高い人は、会社員と個人事業主の両立も上手くこなせるでしょう。
会社員と個人事業主の仕事は、働き方や求められるスキルが大きく異なります。会社では決められた業務を遂行することが求められる場面が多いですが、個人事業主としては、案件獲得、価格交渉、マーケティング、サービス開発など、ビジネス全般を自身で決める必要があります。特に、未経験の分野に挑戦する場合は、柔軟に新しい知識を吸収し、環境の変化に対応できる能力が不可欠です。
また、個人事業では、仕事の進め方やクライアントへの対応方法が案件ごとに異なるため、柔軟に対応できる人ほど、掛け持ちで成功しやすいと言えます。
会社員が個人事業主との掛け持ちで「最強」の効果を得るポイント

会社員として働きながら個人事業主としても活動することで、収入の多様化やスキル向上のメリットを得られます。しかし、両立を成功させるには、事前の準備や適切な働き方の工夫が不可欠です。ここでは、最大限の効果を得るためのポイントを紹介します。
副業しやすい環境を作る
会社員と個人事業を両立するには、無理のないスケジュールと働きやすい環境を整えることが重要です。本業に支障をきたさない範囲で、「個人事業に割く時間を週何時間までと決める」など、ルールを設けることが考えられます。
また、作業場所の確保も大切です。自宅の一角に専用スペースを設けたり、カフェやコワーキングスペースを活用したりして、集中できる環境を整えましょう。特に家族がいる場合は、事前に相談して理解を得ておくことも大切です。
経理・税務などの手続きを把握する
個人事業主として活動を始めるなら、確定申告や経費計上、青色申告のメリット・要件など、税務処理を理解する必要があります。事前に税務知識を学んでおくことで、手続きの負担を軽減でき、節税対策も可能になります。
特に、青色申告を活用すると最大65万円の控除が受けられるため、利益が見込める場合は早めに準備しましょう。また、経費として認められる支出を把握し、正しく帳簿をつけることも重要です。本格的に活動を始める前に、会計ソフトの使い方を学ぶなどスムーズに処理できるよう準備しておくのもよいでしょう。
相乗効果を発揮しやすい仕事を選ぶ
個人事業の内容を決める際、本業と関連する仕事を選ぶことで、スキルの相乗効果を狙えます。例えば、本業がエンジニアなら、副業でテックブログの執筆をすれば、知識のアウトプットとブランディングにつながるでしょう。
また、マーケティング職なら「副業でSNS運用代行をする」、デザイナーなら「個人でロゴ制作を受注する」など、本業の経験を活かせる仕事を選ぶと、学びながら副業の収入を伸ばせます。異なる分野に挑戦するのも1つの選択肢ですが、負担が増えすぎないよう、本業とのバランスを考えて決めることが大切です。
仕事・案件探しの方法を確立する
個人事業主は、自ら案件を探して営業を行う必要があるため、効率的な仕事探しの方法を確立することが不可欠です。以下のような手段を活用しましょう。
- 人脈・SNS
- クラウドソーシング
- エージェント
- 求人サイト
特に、スキルがあり、クライアントワークを探している場合は、フリーランス・副業エージェントの活用がおすすめです。IT/Web分野専門のフリーランスエージェント「ITプロパートナーズ」なら、週2~3日の柔軟な案件やフルリモート案件も充実しており、会社員と両立できる案件も見つかります。効率よく案件を獲得し、安定した収益を得たい方は、ぜひチェックしてみてください。
会社員が個人事業主を開始する際の手続き・準備
会社員が個人事業主としての活動を始める際には、税務手続きや資金管理、会計処理の準備が必要です。ここでは、具体的な準備内容を解説します。
開業届・青色申告承認申請書の提出
個人事業を開始する際、税務署へ「開業届」を提出する必要があります。これは事業開始の証明となる届出であり、提出して初めて「個人事業主」として正式に認められる仕組みです。開業届は、最寄りの税務署に直接持参するか、e-Taxを利用してオンラインで提出できます。
また、「青色申告承認申請書」を提出することで、最大65万円の特別控除を受けられるほか、赤字の3年間繰越が可能になるなどの恩恵があります。新たに青色申告を利用するには手続きの期限があるため、事業を本格的に始める場合は早めの準備が重要です。
銀行口座・クレジットカードの用意
個人事業を始める際は、事業専用の銀行口座とクレジットカードを用意するのが望ましいです。プライベートと事業の資金を分けると、入出金の管理がしやすく、スムーズに経理処理を進められます。
特に、フリーランス向けのビジネス口座や、会計ソフトと連携可能な銀行を選ぶと、経理の効率が向上します。例えば、ネット銀行は手数料が低く、オンラインでの取引もスムーズなため、個人事業主に人気です。
また、事業専用のクレジットカードを作成すると、事業経費を明確にしやすくなるだけでなく、ポイント還元や経費の自動仕訳機能を活用できるため、経理の手間を減らせます。
会計・税務ソフトの導入
個人事業主になると、売上や経費の管理、確定申告などの税務処理を自身で行う必要があります。これらの手続きを効率化するために、会計ソフトを導入するのがおすすめです。
会計ソフトを利用すると、日々の取引を記録しながら確定申告に必要な帳簿を自動作成できるため、手作業によるミスを防ぎながら時間を節約できます。
特に、「freee」「弥生会計」といったクラウド型の会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードと連携でき、効率的な仕訳が可能です。
さらに、こういった会計ソフトは確定申告の機能・プロダクトとも連携していることが多く、会計から税務申告までをスムーズに行えます。
まとめ
本記事では、会社員が個人事業主を兼業するのが「最強」と言われることも踏まえて、そのメリットやデメリット、成功のポイントについて詳しく解説しました。会社の福利厚生や社会保険を活用しながら自分の裁量で事業を進められる点は大きな魅力である一方で、税務処理の負担や過労のリスクなど、注意点も理解しておく必要があります。
会社員と個人事業主の掛け持ちで成功するには、副業しやすい環境を整え、経理や税務の知識を身につけることが重要です。また、相乗効果を発揮しやすい仕事を選び、案件獲得の方法を確立すれば、安定した収入を得やすいでしょう。
個人事業主として案件探しをする際は、フリーランスエージェントの活用がおすすめです。弊社「ITプロパートナーズ」は、IT/Web分野専門のフリーランスエージェントで、「週2〜3日から稼働OK」「フルリモート可能」といった掛け持ちにも適した案件を扱っています。主にエンジニアやデザイナー、コンサルタントの方で、条件に合う案件を効率的に探したい方は、ぜひご活用ください。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)