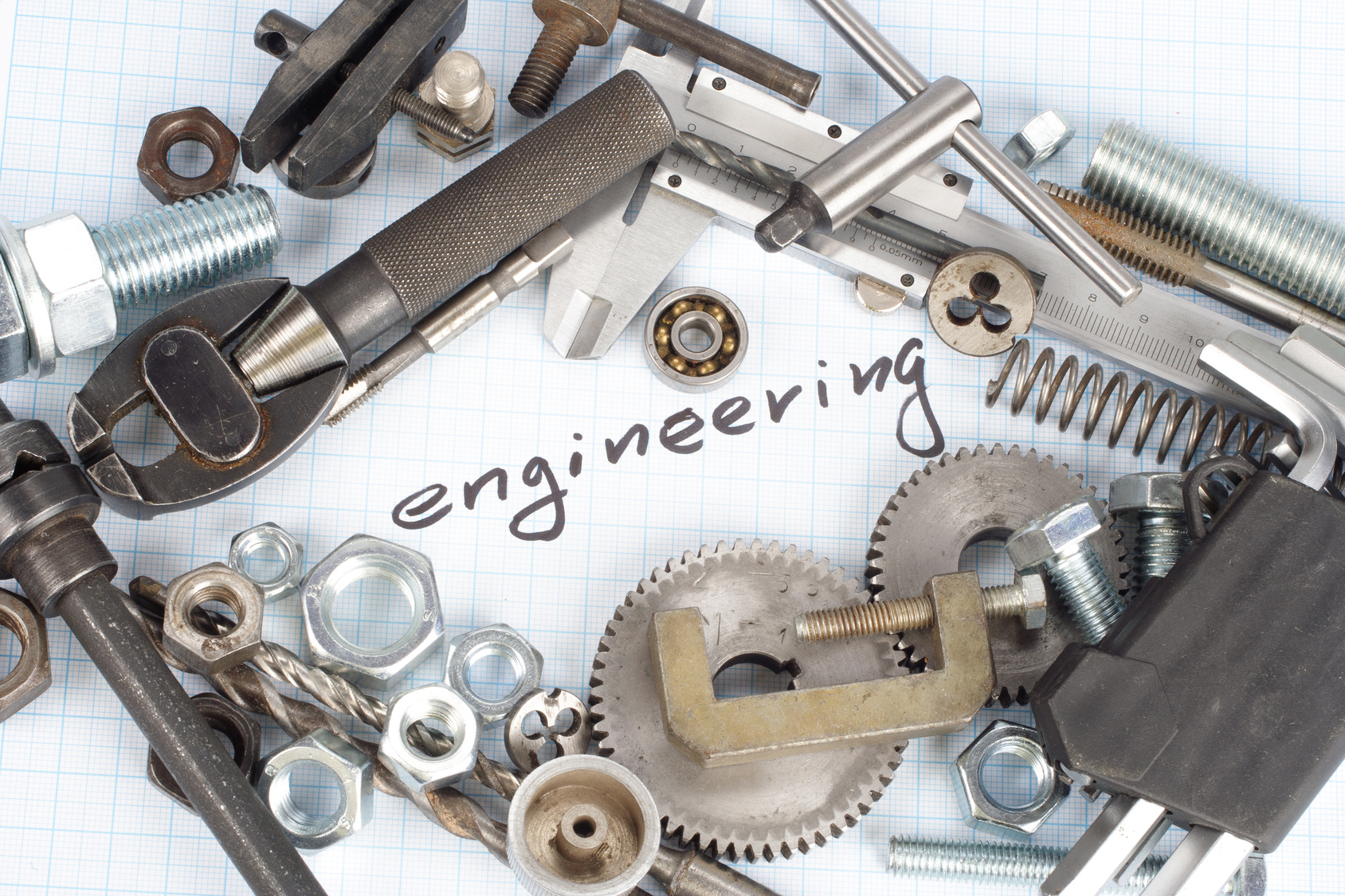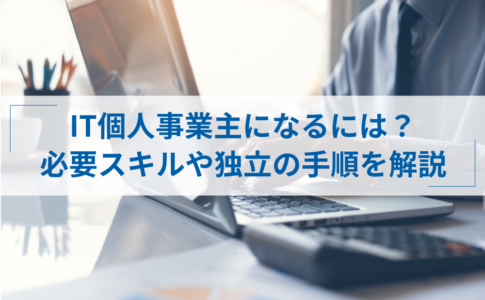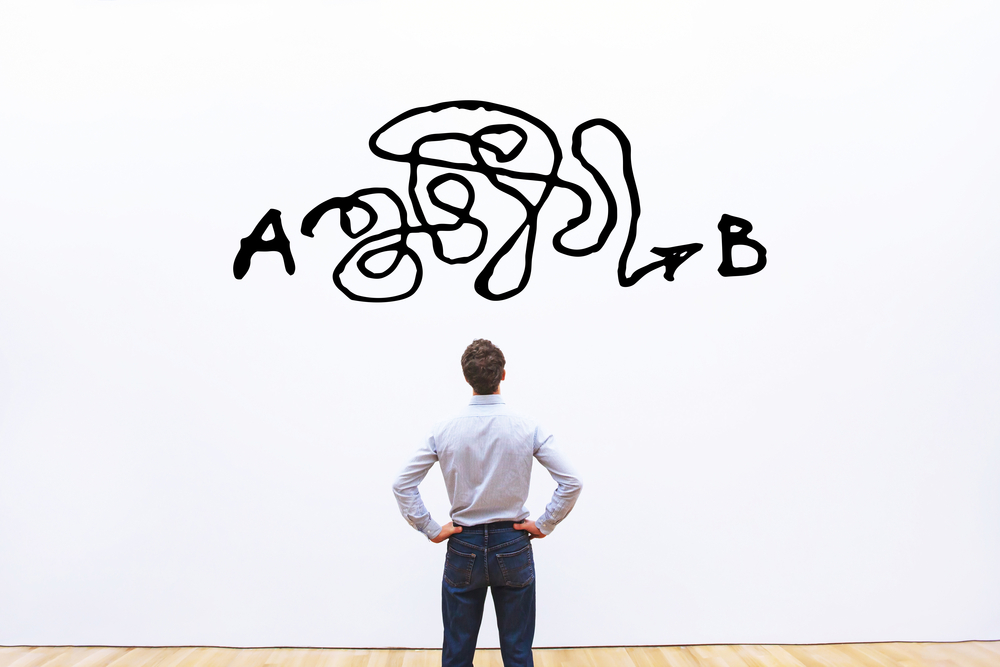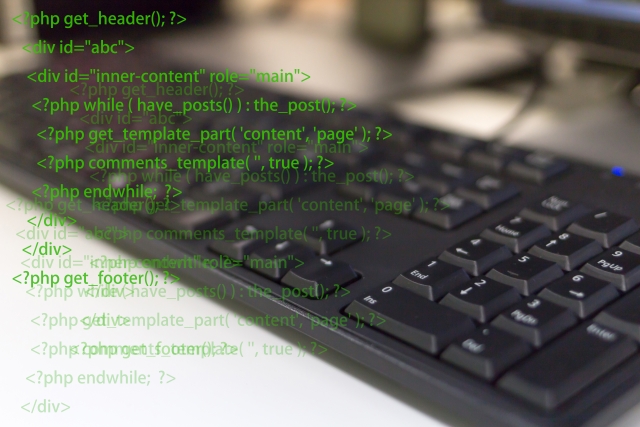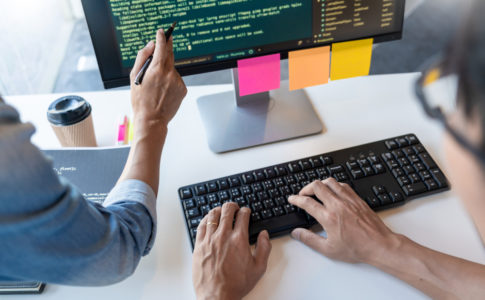こんにちは、ITプロマガジンです。
エンジニアとして技術力を向上させたい、自身の知識を発信してキャリアアップにつなげたい、という人はQiitaを活用しましょう。Qiitaは、エンジニア同士が知識を共有し合い、コミュニケーションを育むプラットフォームです。
本記事では、Qiitaとはどういったプラットフォームかを、基本的な使い方や活用するメリット・デメリットなどに触れつつ解説します。効果的な情報発信のコツも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
ドンピシャ案件の探し方
「案件はたくさんあるはずなのに、なかなか自分の望む案件が見つからない…」
エンジニア市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいマッチングノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・事業会社の自社開発案件が多い
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
Qiita(キータ)とは?

Qiitaは、Increments株式会社が開発したもので、プログラミングに関する知識を記録・共有するためのサービスです。
利用者は自分の得たプログラミングに関する情報を投稿することにより、ほかのエンジニアから投稿に対する適切な評価やコメントをもらえます。また、プログラミングに困った時には、豊富な投稿のなかから、問題解決につながる情報を探すことも可能です。
例えば、コードにミスがあった時やシステムトラブルなどの問題が生じた時に、本やインターネットで調べても知りたい情報が出てこない事は多いでしょう。その点Qiitaには、過去から最新にわたる豊富な事例が蓄積されているため、問題解決の糸口を見つけられる可能性が大いにあります。
プログラミング言語や関連するツールの種類は豊富であるため、自身の専門分野から外れた途端に課題に直面する人は多いでしょう。自分で情報や知識を得るだけでなく、Qiitaを活用して、常に新しいトレンドや新製品の情報を理解しておくことは、キャリアにとってプラスに働きます。
Qiitaでできること
Qiitaでできることは、情報の閲覧・検索と、情報発信の2つに大きく分けられます。
情報の閲覧・検索
Qiitaは、エンジニアリングに関する情報の閲覧・検索をする際に便利です。ホーム画面には、フォロー中のユーザーやタグに基づく投稿、トレンドの記事、新しく公開された記事などが一覧表示されています。画面上で興味深い内容が見つからない場合でも、検索機能を使えば関心のある情報を見つけ出すことが可能です。
あとから読みたい記事に関してはストックでき、備忘録として残しておけます。
情報発信
Qiitaは、個人の知識や経験を発信するプラットフォームとしても活用できます。ほかのエンジニアやクライアント候補となる企業に自身をアピールしつつ、アウトプットを通じて学んだ内容への理解を深めましょう。
また、ほかのユーザーが投稿した記事にコメントを残すことも可能です。コメント機能を通じてエンジニア同士の交流を深めることで、自身の見解を検証したり、専門知識をより広げたりできるでしょう。
エンジニアがQiitaを利用する10のメリット

エンジニアがQiitaを利用するメリットは以下の通りです。
- 気軽に投稿ができる
- 情報検索が容易で技術的なトラブルを解決しやすい
- 編集リクエストがある
- サービスを無料で理世できる
- マークダウン形式で記事を編集できる
- SEO効果が高いと期待されている
- ランキングや表彰プログラムでモチベーション維持しやすい
- フォローやストックで固定読者を増やしやすい
- イベントが活発化している
- ユーザー同士の交流が生まれやすい
10のメリットについて見ていきましょう。
1.気軽に投稿が出来る
Qiitaの最大のメリットは、気軽に投稿が出来る事です。実際にプログラミングで検証してみたことについて、成功したとか、失敗したとかという、ちょっとした話をメモ代わりに投稿して、共有することができます。
2.情報検索が容易で技術的なトラブルを解決しやすい
自身が作業中に遭遇したトラブルについて、同様の問題を経験したほかのエンジニアが、Qiitaに解決方法を投稿しているケースは少なくありません。
Qiitaには数多くの記事が蓄積されているため、業界内の幅広い知見を活用して効率的に課題を解決できるでしょう。
3.編集リクエストがある
「編集リクエスト」ができることもQiitaのメリットです。
編集リクエストは、他人が書いた記事であっても、利用者が見て「時代遅れだ」「間違っている」という書き込みがあった場合、Qiitaの「編集リクエスト」という機能を利用して修正が可能です。
実際にはユーザーが記事を直接編集し、それを変更提案として作者に送信できるので、若干違うかもしれません。ただ、要は個人ではなく、コミュニティのみんなでコンテンツを育てていこうとする発想なのです。ですので、シェアできるものは全てシェアしています。
4.サービスを無料で使用できる
無料で利用できることもメリットです。メールアドレスでアカウントを作成すれば、コンテンツを投稿できます。そのため、無料でほかの人のコンテンツから知識を得られます。
さらに記事へのタグ付けから、コンテンツの分類や整理など、さまざまな機能を無料で使えるため便利です。
5.マークダウン形式で記事を編集できる
Qiitaは、マークダウン形式で記事を編集できます。これにより、コンテンツ制作者はHTMLを学ぶことなく、よりシンプルに記事を作成可能です。マークダウン形式は、HTMLよりも学習・理解しやすく、また、必要に応じて更新しやすいため効率的に執筆ができるでしょう。
6.SEO効果が高いと期待されている
Qiitaは、SEOにも高い効果が期待されています。なぜなら、Googleが公開している「検索エンジン最適スタートガイド」に記載されている要項を、しっかり実装するよう工夫されているからです。
Qiitaにコンテンツを投稿することで、新たな読者を獲得しやすくなり、ユーザー数の増加が期待できます。
特に注目すべきは、Qiita内で自然に形成される内部リンクです。タグ機能や関連記事表示機能により、執筆者は関連するほかの投稿を見つけやすく、内部リンクを積極的に設置できます。また、フォロー機能やストック機能を通じたユーザー同士のつながりも、内部リンクの形成を促進させるでしょう。
7.ランキングや表彰プログラムでモチベーション維持しやすい
Qiitaには多様なランキング制度が設けられています。取り組みの成果が可視化されると、情報発信のモチベーションを維持しやすくなるでしょう。
記事関連では「いいね」数やストック数などが、ユーザー関連ではコントリビューション数や投稿記事数などが評価される仕組みです。
また、コミュニティに貢献した人を称える表彰プログラムに選出されると、受賞者名を公表してもらえるうえ、記念品も受け取れます。
8.フォローやストックで固定読者を増やしやすい
質の高い記事をQiitaに継続的に投稿すると、フォロー機能やストック機能を活用した固定読者の獲得が期待できます。優良なコンテンツの提供に集中することで、自然に読者との関係性を構築できます。
一方、個人ブログで固定読者を獲得するためには、SNSで発信するなどの積極的な宣伝活動が不可欠です。エンジニアとして働きながらブログ運営と宣伝活動を並行するのは、負担が大きいかもしれません。
9.イベントが活発化している
Qiitaでは年間を通じて公式イベントが開催されています。特にAdvent Calendarは代表的な取り組みです。
毎年12月に実施されるAdvent Calendarでは、25日間にわたって参加者が順番に記事を投稿し、コミュニティ全体が大いに盛り上がります。過去にはスポンサー企業による賞品提供や、運営からの特別企画なども実施されました。
数々の公式イベントを通じてプラットフォームへの参加者が増加しています。
10.ユーザー同士の交流が生まれやすい
Qiitaでは、コメント機能などを活用して、ユーザー間のコミュニケーションが活発に行われています。オンライン上での意見交換にとどまらず、勉強会や交流会といったオフラインでの集まりに発展するケースも多く、エンジニア同士の人脈形成に大いに役立つでしょう。
また、ユーザー同士が記事の内容を検討し、必要に応じて改善提案を行う環境により、長期的に掲載コンテンツの質が向上しています。
エンジニア向けのコミュニティサイトを知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
Qiitaのデメリット
Qiitaにはメリットもあれば、デメリットもあります。
- ランキング上位は人気の言語が多い
- 記事執筆に疲れてしまうこともある
- 収益化は期待できない
- エンジニア以外にはあまり知られていない
それぞれの内容を見ていきましょう。
ランキング上位は人気の言語が多い
Qiitaで投稿されているコンテンツは、一般的に人気のある言語に偏っている傾向があります。実際にQiitaを見てみると、JavaScriptやPythonなどの言語が多い傾向です。人気のない言語について知りたい方は、情報を集めるのが難しいでしょう。
また人気がない言語のコンテンツを作成しても、見てくれる人が少ないためランキング上位への表示は難しい状況です。
記事執筆に疲れてしまうこともある
Qiitaには、編集リクエスト機能とコメント機能があります。エンジニア同士の交流に役立つ機能ではありますが、他者からのフィードバックに対応しつつ分かりやすい記事を執筆しようとすると、時間が掛かり疲れてしまうでしょう。
読みやすさや分かりやすさなど、こだわりをもってしまうと労力を割かれてしまいます。
収益化は期待できない
Qiitaで情報発信するのみでは、直接的な収益化は期待できません。例えば、Qiitaはアフィリエイトリンクの掲載を禁止しています。
ただし、ポートフォリオとして活用するなら、Qiitaは十分な効果を発揮するでしょう。技術力のアピールを通じて案件獲得や転職活動につなげるなど、間接的な収益化ならば期待できます。
なお、フリーランスエンジニアの案件獲得には、弊社ITプロパートナーズがおすすめです。週2日・3日案件やエンド直案件、リモート案件などさまざまな案件を取り揃えているので、ぜひご活用ください。
エンジニア以外にはあまり知られていない
Qiitaはエンジニアコミュニティに特化したプラットフォームであり、一般の人における認知度は低い状況です。非エンジニア向けの情報発信や、より幅広い読者層にアプローチしたい場合には適していません。
そのため、個人ブログやSNSを併用した情報発信も、必要に応じて検討するとよいでしょう。おすすめの情報発信手段は、詳しく後述します。
エンジニアがQiiitaを今すぐ始めるべき3つの理由

エンジニアがQiitaを始めるべき理由は以下の3つです。
- 効率的に時間を使える
- 信憑性がある
- 登録者エンジニアの方々の質が高い
それぞれの内容を紹介します。
1.効率的に時間を使うことができる
初めに、プログラミングの世界では、エラーで動かなくなったり、解決方法が分からないような問題に突き当たることが多いですが、その問題は過去に誰かがすでに解決しているということがよくあります。
過去に解決したことのある問題を、一から取り組むのは非効率的です。シェア出来るものを増やすことで、本来取り組むべき課題に時間を使えます。効率的に仕事をこなすうえでもQiitaは有効なのでまだ始めていないのであれば、是非始めてください。
2.信憑性がある
次に、Qiiitaを開始する時期は、なるべく早い方がよいでしょう。
キュレーションサイトなどであると、統率がどこまで取れているか分かりませんし、キュレーション記事の執筆者は記事単価ベースで記事を生産しているに過ぎない場合が多いので、信ぴょう性が薄く、逆に混乱を招く恐れもあります。
その分、Qiitaは開かれたサイトではないので、信憑性のあるエンジニアの濃い話が聞けるでしょう。
3.クローズドな環境で登録者エンジニアの方々の質が高い
最後に、Qiitaの利用者は圧倒的にエンジニアの方が多く、クローズドの環境で意見がかかれていますので、極端に変な人がくるということはありません。
エンジニアの話はエンジニアに聞くのが一番確実なので、Qiitaに書かれている情報は、経験を基にした体験談が多いので、優秀なエンジニアのコーディングを見ることが可能です。また、アフィリエイターの存在もないことが、情報の質にもつながっていますね。
Qiitaの効果的な使い方と発信のコツ
質の高い記事を書くのは大切ですが、より多くの読者に届けるにはいくつかのポイントを押さえる必要があります。Qiitaで効果的な情報発信を行い、自身の技術力を適切にアピールするための具体的な方法を見ていきましょう。
1.プロフィールを充実させる
プロフィールの充実は、読者からの信頼獲得において重要です。得意なプログラミング言語や開発実績を具体的に記載しておくと、記事の信憑性が向上し、読者との信頼関係を構築できます。
適切なタグ設定も大切です。タグを活用することで検索結果での表示機会が増え、その情報を必要としている読者に記事が届きやすくなります。また、自身のSNSアカウントとQiitaを連携させると、記事の拡散力が強化されフォロワーの増加が見込めるでしょう。
2.継続的な発信を心掛ける
定期的な記事投稿は、コミュニティ内での認知度向上に直結します。簡潔な投稿でも構わないので、継続性を重視してください。
タイムライン上での露出機会が増加するため、読者からの反応を得やすくなります。また、記事作成を続けるうちに文章構成力や表現力が高まるでしょう。頻繁なアウトプットによる学習効率の向上も期待できます。
3.自身の得意領域に特化して発信する
特定の技術分野に焦点を絞った発信により、方向性やターゲットを明確化することが大切です。
専門性の高い記事を継続的に投稿すると、その分野における専門家としての地位を確立しやすくなります。自身の実際の開発経験や課題解決の過程を交えた発信により、ほかのユーザーとの差別化を図りましょう。
Qiitaに関するよくある質問
Qiitaに関するよくある質問として、技術ブログとの違いや、併用したい情報発信手段について解説します。
Qiitaは技術ブログの代わりになる?
Qiitaは技術ブログの一種ですが、技術ブログとしての利用方法に加えて、チームでの共同作業や、コードスニペットの共有など、より多くの機能を持っています。またSEOにも配慮されているため、検索エンジンで上位表示化がされやすい点が魅力です。
技術ブログとして知識を記録し、共有するための目的ならQiitaを利用するのもよいでしょう。なお、以下の記事でエンジニアが注目すべき個人ブログを紹介しているので、併せて参考にしてください。
Qiita以外でエンジニアが利用できる情報発信手段は?
エンジニアの情報発信手段には、個人ブログ以外にもYouTubeやX(旧Twitter)などもおすすめです。
YouTubeは、技術内容を映像と音で伝えられる点が魅力です。例えば、コーディング作業のデモンストレーションや、最新技術のレビュー動画などに活用するとよいでしょう。
Xは、簡潔な情報の投稿や、個人ブログやQiitaで書いた記事の拡散などに便利です。適切なハッシュタグを使用し、より多くのユーザーにアプローチしましょう。
まとめ
Qiitaは、エンジニアが自身の経験や知識を発信するとともに、さまざまな技術情報を効率的に収集できるプラットフォームです。
Qiitaを通じて新しい技術に触れ、ほかのエンジニアと交流することで、技術力の向上やキャリアアップにつながります。まずは情報収集から始めて、慣れてきたら積極的に自分の経験や知識を発信してみましょう。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)