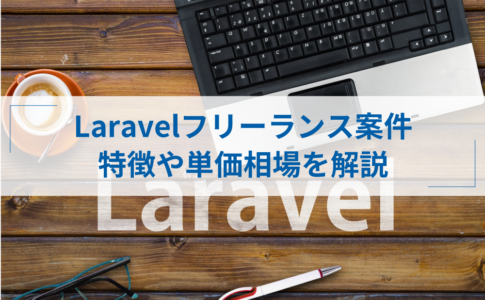こんにちは、ITプロマガジンです。
クラウドエンジニアは、インフラ領域でも注目されている職種ですが、負担の大きい仕事として知られているのも事実です。クラウドエンジニアに興味はあるけれど、「やめとけ」「きつい」といった声が気になって、もう一歩踏み切れない方もいるかもしれません。
本記事では、クラウドエンジニアが「やめとけ」と言われる理由を10個に分けて解説するとともに、その裏側にあるやりがいや将来性を詳しく紹介します。
ドンピシャ案件の探し方
「案件はたくさんあるはずなのに、なかなか自分の望む案件が見つからない…」
エンジニア市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいマッチングノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・事業会社の自社開発案件が多い
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
クラウドエンジニアはやめとけ・きついと言われる10の理由

クラウドエンジニアはやめとけ・きついと言われる主な理由は、以下の10点です。
- 緊急の障害対応の可能性がある
- 会社によっては夜勤がある
- 仕事の責任が重い
- 扱うサービスの種類が多い
- 幅広いスキルが求められる
- 特定のサービスの動向に左右される
- 資格の取得・更新が大変
- トレンドの変化が激しい
- チーム間の連携・コミュニケーションが必要
- 長期案件が多い
それぞれ詳しく解説します。
1.緊急の障害対応の可能性がある
クラウドエンジニアとしてシステムの保守・運用も担当していれば、もしサーバーやネットワークに障害が発生した場合、緊急対応が求められることになります。
クライアントのサーバーやネットワークでトラブルが起きたら、通常の業務が滞り、利用者からのクレームも考えられるので、一刻も早い対応が必要となります。
トラブルは夜間でも休日でも起こりえます。クラウドエンジニアは、日時に関係なく障害対応のために稼働しなければなりません。夜間・休日の緊急出勤の可能性は、身体的・精神的に大きなストレスを与えます。
2.会社によっては夜勤がある
クラウドエンジニアは「日中に開発・設計をする仕事」だと思われがちですが、勤務先によっては夜勤が発生するケースもあります。障害発生時の緊急対応とは別に、環境切替などさまざまな状況で夜勤が必要になるためです。
夜勤の手当があるものの、生活リズムが崩れやすく、体力的・精神的にきついと感じる人も少なくありません。さらに夜間帯はサポート体制が薄く、少人数での対応を強いられるといったプレッシャーもあり、「やめとけ」と考える人もいるようです。
3.仕事の責任が重い
上記の障害対応の件からも分かるように、クラウドエンジニアの責任は重大です。トラブルへの緊急対応はもちろん、トラブルが起きにくいシステムの構築と保守・運用が求められます。
クライアントの企業活動がストップする事態になれば、多大な損害を招きます。クラウドエンジニアは、こうした大きなプレッシャーのなかで業務を行わなければなりません。
4.扱うサービスの種類が多い
クラウドエンジニアの仕事は、扱うサービスの種類が多く、学習量も膨大です。例えば代表的なクラウドサービスであるAWS(Amazon Web Services)は、現在も新しいサービスが次々に追加されています。
クラウドエンジニアには「使えるサービスを増やせば終わり」というゴールはなく、常に新しい技術やサービスにアンテナを張り、学び続ける姿勢が求められます。とにかく手広く勉強し続けなければならず、精神的負担が大きくなるケースもあるようです。
5.幅広いスキルが求められる
クラウドエンジニアには、単なるクラウドの知識だけでなく、幅広いITスキルが求められます。
例えばインフラ構築を担当する場合は、仮想サーバーの設計・構築だけでなく、ネットワークの構成やセキュリティ対策、データベース、ミドルウェアの設定などさまざまな知識が必要です。
さらには提案力やコミュニケーション能力など、技術面以外のスキルも多く要求されます。こうした多くの知識・スキルが必要な点が、「きつい」「やめとけ」とされる理由の1つです。
6.特定のサービスの動向に左右される
クラウドエンジニアの仕事は、AWSやAzure、Google Cloudなど外部クラウドサービスの活用が前提です。そのため、上記サービスの仕様変更や、機能追加・廃止に大きく影響されます。
さらにはあるクラウドサービスに特化してキャリアを積むと、「スキルのロックイン」が発生する可能性があります。例えば「AWSは得意だけど、他のクラウド環境では力を発揮できない」といった状態です。
こうしたリスクを避けるには、どのクラウドサービスでも生かせる汎用的なスキルを意識的に磨く必要があります。
7.資格の取得・更新が大変
クラウドエンジニアは、資格の取得・更新も大変です。求められる資格としては、AWS認定資格、Google Cloud認定資格、Microsoft Azure認定資格などがあります。いずれも難易度が高く、学習段階で挫折してしまうことも少なくありません。
資格を取得するためには、クラウドに関する知識に加えて実務経験も必要です。一度認定されたとしても技術更新があるため、数年スパンで再認定が必要になる資格もあります。
8.トレンドの変化が激しい
ITエンジニア全般に共通する課題として、技術トレンドの変化が早い点が挙げられます。クラウド分野は特にスピードが速く、数年単位どころか、半年〜1年で主流の技術・サービスが入れ替わるケースもあるほどです。昨今ではAI(人工知能)の活用も広く見られるようになり、今後もその流れがさらに加速すると見られています。
トレンドの変化に対応するには、日常的に情報収集を行い、必要に応じて学習内容をアップデートし続けなければなりません。こうしたトレンドの変化についていく大変さが、「クラウドエンジニアはきつい」「やめとけ」と言われる理由の1つになります。
9.チーム間の連携・コミュニケーションが必要
クラウドエンジニアは技術職ではありますが、単独で黙々と作業していればよい職種ではありません。業務の性質上、多くの部署やチームと連携する場面が多く、高いコミュニケーション能力が求められます。
例えばシステム構築時には、アプリケーション開発チームや運用チーム、セキュリティ部門などさまざまな部署との連携が必要です。クラウド環境では設計や構成変更がすぐに反映されるため、連携ミスがそのままシステム障害につながるリスクもあります。
コミュニケーションが苦手な人にとっては、意外にストレスのかかる場面が多いかもしれません。
10.長期案件が多い
クラウドの案件は、クライアントの希望に沿ったシステム・サービスを構築するために工数が多くなり、対応期間も長くなる傾向にあります。保守・運用を任されるケースもあるため、より長期にわたってプロジェクトに携わります。
常駐先が相性の良いクライアントであれば問題ありませんが、「肌に合わない」と感じたり、業務上のトラブルが続いたりするとモチベーションの維持が難しくなるかもしれません。
やめとけとは言い切れないクラウドエンジニアの魅力
SNSなどでは「やめとけ」と言われることも多いクラウドエンジニアですが、その反面、将来性のある職業でもあります。以下、クラウドエンジニアの魅力を解説します。
経験できる仕事の幅が広い
クラウドエンジニアは、さまざまなスキルが自然と身に付くため、一概に「やめとけ」とも言い切れません。業務では、パブリッククラウドの運用だけでなく、ミドルウェアやネットワーク、セキュリティ、オンプレミスとの連携など幅広い知識とスキルが必要です。
幅広い業務経験を通じて、多角的な視点と実践力が自然と身に付くため、自分の成長を感じやすくなります。プレッシャーや学習の大変さはあるものの、こうした成長の実感を得ながらキャリアアップしたい人にとっては、やりがいのある環境です。
最新技術のスキルを身に付けやすい
クラウドエンジニアは、「学習が大変だからやめとけ」といったネガティブな面もありますが、その分最先端の技術に触れながらスキルを磨けるという魅力もあります。
例えばAWSやAzure、Google Cloudなどのプラットフォームでは、日々新しいサービスやアップデートがリリースされています。スピード感のある環境を、大変と感じるか楽しいと感じるかは人それぞれですが、好奇心旺盛な人にとってはやりがいのある職種です。
需要・将来性が高い
クラウドエンジニアは、「きつい」「やめとけ」と言われる一方で、今後も安定して求められる将来性の高い職種と言えます。クラウドサービスの需要は拡大しており、それによってクラウドエンジニアの社会的需要もますます高まるのが予想されるからです。
実際に、サービスの充実化にともない、クラウドサービスを導入する企業が増えています。総務省が情報通信サービスの利用状況について調査した「令和5年通信利用動向調査」によれば、クラウドサービスを導入している企業の割合は77.7%です。
導入した結果として、「非常に効果があった」「ある程度効果があった」とする企業は、導入企業全体の88.4%となっています。オンプレミスからクラウドへの移行の流れは、今後もさらに続くと見られています。
年収が高い傾向にある
クラウドエンジニアの需要が高まっているのに対して、人材が不足しているため、必然的に年収も高くなる傾向にあります。「求人ボックス 給料ナビ」によると、クラウドエンジニア(インフラエンジニア)の平均年収は約497万円です。
フリーランスでは、さらなる高収入も視野に入ります。弊社ITプロパートナーズに掲載されている案件を2つ紹介します。
| 案件名 | 【AWS/GoogleCloudPlatform】ファッションECにおけるクラウドエンジニア |
|---|---|
| 案件単価 | 〜600,000円/月(週4日〜5日) |
| 勤務地 | フルリモート |
| スキル・経験 | AWS/GCP等を利用したインフラ設計・構築経験,Webアプリケーションの開発・運用経験 |
| 職種・ポジション | バックエンドエンジニア,インフラエンジニア |
急成長中の越境ECスタートアップにて、インフラ全般(GCP中心)の最適化・パフォーマンス改善・運用体制整備などを担当する案件です。GCP/AWSを用いたインフラ設計・構築経験や、Webアプリ開発経験が必要で、想定月収は最大60万円になります。
| 案件名 | 【AWS】D2CクライアントにおけるDB開発 |
|---|---|
| 案件単価 | 〜900,000円/月(週5日) |
| 勤務地 | 基本リモート一部出社 |
| スキル・経験 | AWSでのtoCデータのDBの開発経験(5年以上) |
| 職種・ポジション | バックエンドエンジニア |
D2C事業を展開するクライアントの販売管理・在庫管理システムをフルスクラッチで開発する案件です。現在は基本設計フェーズで、詳細設計〜実装を担当できるバックエンドエンジニアを募集しているようです。AWS上でtoCデータを扱うDB開発経験が必要で、想定月収は最大90万円になります。
責任の重大さ、業務の大変さから「やめとけ」と言われる職種ですが、その分の見返りは十分見込める仕事です。
在宅で働きやすい
クラウドエンジニアは、在宅で働きやすい職種の1つです。クラウド環境はインターネット経由で構築・管理するのが前提のため、物理的にオフィスにいる必要がなく、多くの業務をオンラインで完結できます。
システムの設計・構築・運用、チームとのミーティングなども基本的にリモートで対応可能なため、フルリモートを導入している企業もあります。「自宅で働きたい」「地方に住みながら都内企業の案件に関わりたい」という人にもおすすめです。
フリーランスとして活躍しやすい
クラウドエンジニアは、フリーランスとしても活躍しやすい職種です。クラウド環境の設計・構築・運用といったスキルはクライアントからの需要が高く、フルリモートや週3日程度から稼働できるフリーランス向けの案件も多くあります。
ITプロパートナーズでは、クラウドエンジニア向けの高単価・リモート案件を多数掲載しています。週2〜3日の副業案件や、スキルに合ったプロジェクトを探したい方は、ぜひ一度案件をご確認ください。
クラウドエンジニアに向いている人の特徴

クラウドエンジニアに向いている人の特徴は、以下の通りです。
- 最新の技術に敏感な人
- コミュニケーション能力が高い人
- コツコツとデスクワークができる人
- 注意力があり細かなミスに気づける人
それぞれ詳しく解説します。
最新の技術に敏感な人
ITに関する最新の技術に敏感に反応する人は、クラウドエンジニアに向いています。
なぜなら、パブリッククラウドは日々更新されており、クラウドエンジニアは最新の技術情報をキャッチし、知識を常にアップデートしていく必要があるからです。また、クライアントにネットワークやサービスを提案する際には、最新技術を採用していることが望まれます。
こうしたアップデートの姿勢を苦に思わず、好んで行う人がクラウドエンジニアに向いていると言えるでしょう。
コミュニケーション能力が高い人
クラウドエンジニアに限りませんが、ITエンジニアの案件はチームでプロジェクトを進めていくことになります。大きなプロジェクトになれば、関わる人数も多くなり、異なる部署とのやり取りやスケジュール調整も複雑化するものです。
クライアントのヒアリングや提案の際には、エンジニアリングのスキル・知識とともにコミュニケーション能力も求められることになります。
逆にいうと、コミュニケーション能力の高いクラウドエンジニアは、どの現場でも重宝される存在になるということです。
コツコツとデスクワークができる人
クラウドエンジニアの作業のほとんどが、地道なデスクワークです。インフラ設計・システム構築・管理や会議の資料作成など、地味な作業の連続といってよいでしょう。
こうした地道なデスクワークが苦にならず、地味な裏方作業をコツコツと続けられる人がクラウドエンジニアに向いているのです。
注意力があり細かなミスに気づける人
クラウドにかかわるシステムのトラブルは、クライアント企業の事業に多大な影響を与えるリスクがあります。些細なミスが命取りにつながることがあるので、細心の注意を払える人がクラウドエンジニア向きと言えます。
自身がミスをしないことはもちろん、他者が書いたコードのミスに気づける注意力があると安心です。
クラウドエンジニアになるために必要なスキル
クラウドエンジニアになるために必要なスキルは、以下の通りです。
- クラウドの知識・スキル
- サーバーの知識・スキル
- ネットワークの知識・スキル
- ミドルウェアの知識・スキル
- オンプレミスの知識・スキル
クラウドサービスを取り扱う知識・スキルは、クラウドエンジニアなら必須となります。Amazonが提供するAWS、MicrosoftのAzure、GoogleのGCPには、それぞれ特徴があり、それらを生かしてシステムを構築できます。
サーバーの設計・構築のスキルも必要です。業務としては、サーバーへのOSインストール、ミドルウェアのインストール、パラメータの設定などがあります。サーバーOSは、Unix、Linux、Windows Serverなどが定番です。
ITインフラの通信に関する知識・スキルも、クラウドエンジニアに必須です。通信プロトコルであるTCP/IP、OSI参照モデルなどの知識・スキルが求められます。
OSとアプリケーションの仲介役にあたるミドルウェアの知識・スキルも欠かせないでしょう。Webサーバー、アプリケーションサーバー、データベース管理システムなどの設計・実装のスキル・経験も積んでいくべきです。
オンプレミスとは、システムを自社で保有・管理する運用形態ですが、この形態からクラウドに移行する案件も豊富です。その意味で、クラウドエンジニアはオンプレミスの知識・スキルにも習熟する必要があります。
ただしオンプレミス環境でもクラウド環境でも、基本技術は同じであり、応用も十分に可能です。
クラウドエンジニアの将来性

結論としては、クラウドエンジニアの将来性は高いと言えます。根拠は、前述の総務省「令和5年 通信利用動向調査」の調査結果です。過去の資料のデータと合わせると、クラウドサービスの導入率は、以下のように推移しています。
- 令和元年:64.7%
- 令和2年:68.7%
- 令和3年:70.4%
- 令和4年:72.2%
- 令和5年:77.7%
※「全体的に利用している」「一部の事業用又は部門で利用している」の回答率の合計
上記からも分かるように、クラウドサービスは年々拡大しつつあり、今後もさらに成長すると考えてよいでしょう。
クラウド技術の進化は止まることなく、次々と新しい技術・サービスが登場しています。クラウドエンジニアは、これら最先端の領域に携われるため、学び続ける意欲のある人にとってはキャリアを伸ばしやすい職種です。
クラウドエンジニアとして働いている人の体験談
次に、実際にクラウドエンジニアとして働いている人の意見をX(旧Twitter)から見ていきましょう。
良い口コミ
「やめとけ」という意見があるクラウドエンジニアですが、肯定的な口コミも多く見られます。
需要が伸びている
クラウドを扱える人材の需要はどんどん伸びている クラウドエンジニアは増え続けているものの、人材の供給が需要の伸びに追いついていない でも、欲しがられるのは方針を決めて作業に切り出せる人、作業を自動化できる人だね 最初は作業ができる人でよいから、知識をつけてステップアップしてほしい
— あずきつね?AWS/Azure/GCP (@azktn) May 1, 2022
クラウドサービスを活用したシステム・サービス開発などの仕事は増える一方なのに、求められる人材はそれに比例して増えていない現実があります。クラウドエンジニアの社会的需要は強く、これからも伸びるようです。
市場価値が高い
Salesforceエンジニアが市場価値高いと言われてますが、AWSやAzureも価値が高いし、総じてクラウドエンジニアが伸びてますね!プログラミング理解してる人はブラックボックスのクラウドでも懸念事項や飲み込みが早いです。web系の方がイメージできてキラキラしてますがクラウドの方が穴場という。
— ぺろ@Salesforceエンジニア (@perogineer) September 17, 2022
AWS、Azure、GCPとクラウドサービスが充実している現在、クラウドエンジニアの市場価値も高まっているようです。Web系エンジニアのほうが目立っている傾向はありますが、クラウドエンジニアにも陽が当たりつつあるのです。
悪い口コミ
続いて、否定的な口コミを見ていきましょう。
業務範囲が幅広く大変
エンジニアにはいっぱい種類があるのに、クラウドエンジニアだけ唐突に幅広くなるのは何故?ネットワーク、サーバ、データベース、ストレージ、セキュリティ、色々含まれている。全部カバーすると実質フルスタックに近いのでは。
— うめめ (@beConjuror) September 27, 2022
クラウドエンジニアの業務上、どうしても対応すべき範囲が広くなってしまいます。その分、負担感は大きいのでしょう。
休日・夜間に緊急対応が必要なことがある
オンプレ時代のインフラエンジニアが人気無かったというのはよく分かるんですけどもw、今のクラウドは最新技術が真っ先に集約される上に需要が非常に大きい花形分野ですから、クラウドエンジニアは相当お薦めな職種ではありますねー。
— 勝又健太|エンジニア系YouTuber|雑食系エンジニア|「Web系エンジニアになろう」著者 (@poly_soft) February 17, 2022
ただし休日夜間のオンコール対応には覚悟が必要ですがw
クラウドエンジニアは夜間や休日の緊急障害への対応も求められることがあり、そのことを覚悟する必要があるわけです。時間を選ばない突発的な対応を強いられる可能性があることが、「きつい」と言われる理由の1つと言えそうです。
クラウドエンジニアを目指す人におすすめの資格
クラウドエンジニアを目指す人におすすめの資格に、クラウドサービスを提供する各社が主催する認定資格があります。
AWS認定資格
AWS認定資格は、AWSに関する知識・スキルを証明するためのものです。大まかに、以下の4つのカテゴリーに分かれています。
| カテゴリー | レベル | 資格 |
|---|---|---|
| Foundational | 基礎(事前の経験不要) | ・Cloud Practitioner ・AI Practitioner |
| Associate | 中級(AWSやオンプレミスの実務経験があるエンジニア向け) | ・SysOps Administrator ・Developer ・Solutions Architect ・Data Engineer ・Machine Learning Engineer |
| Professional | 上級(2年以上のAWSクラウド経験者向け) | ・Solutions Architect ・DevOps Engineer |
| Specialty | 専門(特定の分野を深く掘り下げたい方向け) | ・Advanced Networking ・Machine Learning Security |
クラウドエンジニアにとって、転職の際にアピールできるだけでなく、日常の業務でも役立てられます。
Microsoft Azure認定試験
Microsoftの認定資格は、実践的なITスキルと業務に必要な能力を証明するための認定制度です。クラウド、開発、データ、セキュリティなど、需要の高い分野で通用するスキルを習得し、キャリアアップに活用できます。
実務に即した知識と技術力を評価する形式で、年1回の更新が推奨されています。Azureの知識・スキルを認定するものも多く、基礎レベルの試験・資格としては「Microsoft Certified: Azure Fundamentals」(試験コード:AZ-900)がおすすめです。
クラウドエンジニア関連では、以下のような試験があります。
| 試験コード | レベル | 内容 |
|---|---|---|
| AZ-900 | 基礎 | Microsoft Azureの基礎知識 |
| AZ-500 | 中級 | セキュリティ対策・運用・アクセス制御の知識 |
| AZ-700 | 中級 | ネットワーク構成・設計・運用の知識 |
| AZ-104 | 中級 | クラウドインフラの構成や管理の知識 |
| AZ-800 | 中級 | Windows Server環境の管理に関する知識 |
| AZ-801 | 中級 | より高度なハイブリッドサービス、セキュリティの知識 |
| AZ-305 | 上級 | クラウド上で実用的かつ安全性・拡張性のあるシステムアーキテクチャを設計するための知識 |
自分のレベルや関心のある分野に合わせて試験を受けられます。
Google Cloud認定資格
Google Cloud 認定資格は、クラウド技術に関する知識とスキルを客観的に証明できる認定制度です。クラウドエンジニアをはじめとしたクラウド人材へのニーズが高まる昨今、スキルを可視化し、キャリアアップに直結する資格として注目されています。
大まかに、以下の3つのレベルに分かれています。
- 基礎的な認定資格(Cloud Digital Leaderなど)
- アソシエイト認定資格(Associate Cloud Engineerなど)
- プロフェッショナル認定資格(Professional Cloud Architectなど)
Credlyのデジタルバッジにより、資格をオンライン上で可視化・共有可能です。
まとめ
クラウドエンジニアは、確かに責任が重く、継続的な学習や緊急対応など大変な面も多くあります。しかしその反面、最新技術に触れられる環境や将来性、高い報酬などの魅力も持ち合わせています。
「やめとけ」という声の背景を正しく理解しつつ、自分の適性や目指す働き方と照らし合わせて考えれば、後悔のないキャリア選択につながるはずです。もし「挑戦したい」と感じたら、まずは資格取得や副業案件から一歩を踏み出すのもよいでしょう。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)